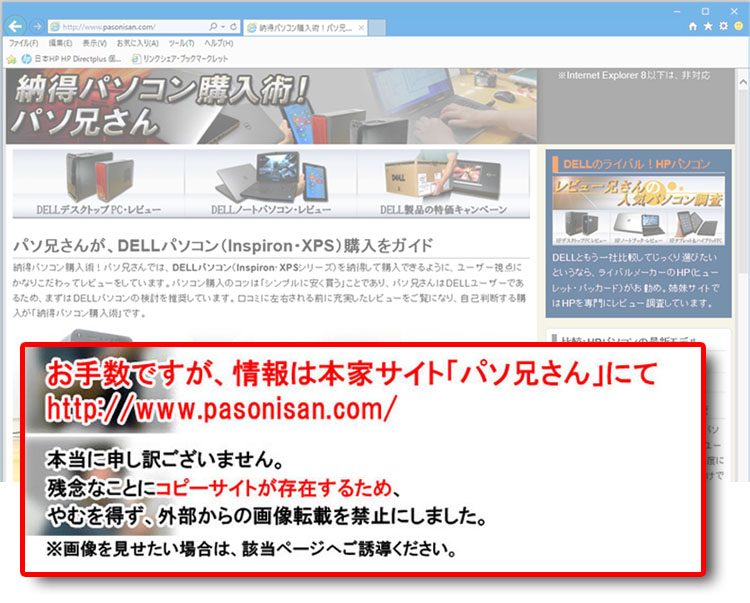

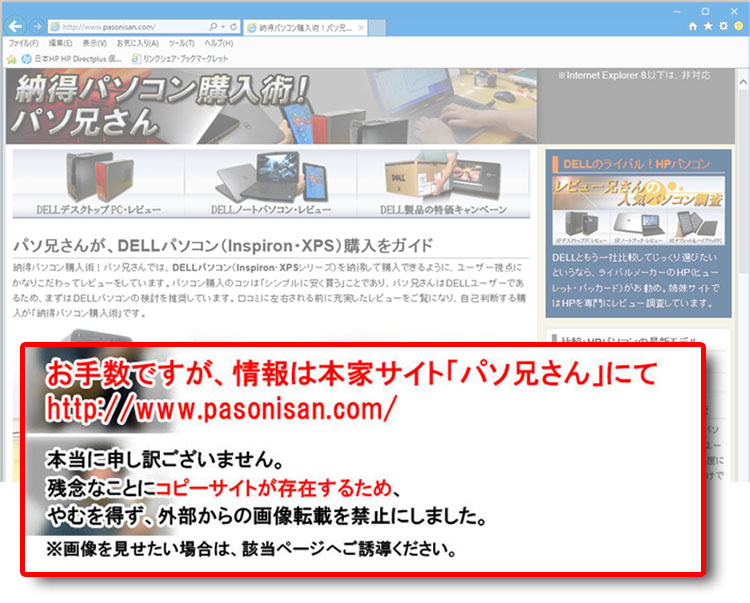
- HOME
- DELLパソコン・モバイル旅行記
- 東京都
- 江戸城(千代田区・中央区ほか)
江戸城
平安時代末期、江戸重継が桜田郷に居館を構えたのが後の江戸城の基礎になったと言われるが諸説ある。室町時代、太田道灌が江戸氏の勢力を衰退させ、1456年、その支配地に江戸城を築いた。
1486年、太田道灌が誅殺された後、主君 扇谷上杉氏の城となるが、1524年、小田原北条氏に奪取される。1590年、豊臣秀吉によって北条氏が滅ぶと、徳川家康が江戸に入封され入城した。1603年に江戸幕府を開府、天下普請の町作りが始まり1604年に日本橋を起点とする五街道を整備、1607年には天守が完成した。1636年、徳川家光の代で江戸城の総構えが完成する。
概要~江戸城の基礎知識
- 江戸城 ~ 秩父氏から徳川氏までの経緯(現在のページ)
- 外堀に配置された見附の概要
- 外堀(水堀)の消失と、国史跡指定地
- 江戸城の石垣石
江戸城の外堀と見附 1(日本橋川)
- 雉子橋門 ~ 雉をこの付近の鳥小屋で飼育していたことに由来 補足事項に「堀留」
- 一橋門 ~ 小田原北条氏時代から橋は架けられていた、側には一橋徳川家屋敷跡
- 神田橋門 ~ 鬼門に位置する見附、将軍が寛永寺に参詣する御成道
- 常盤橋門 ~ 日光街道・奥州街道につながる江戸五口のひとつ、国指定史跡
江戸城の外堀と見附 2(外濠川・汐留川・溜池まで)
- 呉服橋門 ~ 門前の町名が呉服町であったことに由来する
- 鍛冶橋門 ~ 門外の町名が南鍛冶町であったことに由来、狩野探幽の屋敷があった
- 数寄屋橋門 ~ 南町奉行所近くの見附
- 山下門 ~ 1636年に高松藩 生駒高俊によって築造
- 幸橋門 ~ 外濠川と汐留川の合流地点の見附
- 虎ノ門 ~ 外桜田門から続く「小田原道」の見附
- 溜池 ~ 堰を設けて築いた溜池は、江戸初期の上水源であり外堀でもある
江戸城の外堀と見附 3(国史跡指定地 + 消滅した飯田濠まで)
- 赤坂門と弁慶堀 ~ 大山道につながる、江戸城の城門のなかでも優れた見附
- 喰違見附と真田堀 ~ 戦国期以来の古い形態の見附、武田家旧臣・小幡景憲の築造とされる
- 四谷門と市谷堀 ~ 甲州街道の通過点である見附、百姓家が四軒あったことに由来
- 市谷門と牛込堀 ~ 津山藩 森長継によって築造、土橋に石垣残る
- 牛込門 ~ 徳島藩 蜂須賀忠英により築造、名称は戦国時代の牛込城が由来か
- 飯田濠 ~ 牛込揚場であった堀、昭和47年の市街地再開発事業で消滅
江戸城の外堀と見附 4(神田川に置かれた見附)
- 外堀として利用された神田川
- 小石川門 ~ 岡山藩 藩主・池田光政によって築造、近くに神田上水の懸樋あり
- 筋違門 ~ 将軍が上野寛永寺に詣でる時に渡る見附、中山道と御成道が筋違いに交差
- 浅草門 ~ 神田川の最下流に位置、浅草観音への道筋
天然要害の隅田川と、隅田川に面した島
- 天然要害の大川(隅田川)
- 箱崎島 ~ 田安徳川家の下屋敷跡
- 霊岸島 ~ 鎮座していた霊巌寺に因む、松平越前守の中屋敷跡
- 石川島 ~ 石川重次が拝領、後に長谷川平蔵の提案で人足寄場が置かれた島
- 佃島 ~ 江戸幕府より干潟を拝領した漁民らが、1644年四方の島を築造
江戸の運河
その他:江戸城 縄張り内の史跡・旧跡、江戸の町
- 北町奉行所 ~ 徳川幕府三奉行のひとつ。時代劇で有名な遠山景元が執務
秩父氏から小田原北条氏までの経緯
江戸城は砂州が広がる海に面した武蔵野台地に築城された。はじめは館であるが、その基礎を築いたのが平良文流・関東八平氏のひとつである秩父氏。12世紀初期、秩父重綱が武蔵国秩父郡を中心に勢力を持っており、その4男である江戸重継が荏原郡桜田郷(千代田区霞が関2丁目付近)に居住し、江戸荘の開発を行っている。重継の居館場所は明らかではないが江戸城本丸か西の丸あたりと推測されている。江戸重継は「江戸冠者」「江戸貫主」と呼ばれており、近隣を支配している同族で庶家の「豊島氏・葛西氏」らを統括していたと考えられる。
※江戸城の始まりには諸説ある。江戸重継の居館は桜田郷ではなく、江戸郷という説がある。確かに江戸氏を名乗っているわけだし頷ける。江戸とは、埋め立てられる前の日比谷入江へ注いでいた平川の河口付近(和田倉門あたり)を指す言葉とされ、、範囲は神田山の裾部から南の小半島である江戸前島までとされる。※神田山は駿河台であり御茶ノ水駅あたり、江戸前島は中央区日本橋・京橋・銀座・新橋あたりの小半島。半島の中央線が中央通り(東海道・中山道)である。
江戸郷に江戸氏の館があったのなら、江戸氏の館跡が江戸城の始まりではない事になる。立地的には神田山に館が置かれそうだがどうであろうか・・・。その場合、後の太田道灌による築城が江戸城の始まりとなる。
江戸重長の居館時代
平安時代末期、重継の子である江戸重長は、1180年に平家打倒の兵を挙げた源頼朝に従い、さらに武蔵国の支配を強めた。鎌倉幕府が滅亡する1333年では、江戸氏や豊島氏は新田義貞の軍に参加しており、この頃には幕府を見限っていたことがわかる。幕府滅亡後は新田方から離れ足利尊氏に従った。上杉禅秀の乱(1416~1417)や永享の乱(1438)では、江戸氏・豊島氏は活躍し勢力を伸ばしたが、太田道灌によってその勢力をそがれてしまう。江戸氏は分散し江戸の地を去った。その後の江戸氏であるが、惣領家が世田谷木田見(喜多見)へ移ったとも庶家の木田見流が江戸氏を継承したとも言われるが、徳川家康の家臣となり喜多見氏に改めた。
太田道灌の築城から、小田原北条氏の支配まで
室町時代中期、関東管領職は上杉氏によって世襲されていたが、上杉家は山内・犬懸・宅間・扇谷の四家に分かれていた。犬懸家である上杉禅秀の乱(1416年~1417年)のあと、犬懸・宅間は没落、山内と扇谷の2強となり両家が拮抗するようになった。扇谷上杉氏(上杉定正)の家宰は太田道真で、その子が太田道灌である。享徳の乱(1454年~1482年)が勃発すると、古河公方・足利成氏の勢力が下総方面で活発化する。1456年、御殿山城(太田道灌館)を居館としていた当時25歳の太田道灌は、急ぎ江戸城を築城開始する。諸説あるが、江戸氏の館跡に江戸城を築城したという。
1486年、太田道灌が主君の上杉定正に誅殺されると、定正の養子である上杉朝良が江戸城を居城とする。朝良の養子である上杉朝興の時、太田資高(道灌の孫)が小田原北条氏(北条氏綱)に内応し江戸城を包囲し、朝興は河越城へ逃亡する。北条氏は江戸城を武蔵国支配の拠点と定め、本丸に富永氏、二の丸に遠山氏、三の丸に太田氏を配した。北条氏の城となっても大きな改修はなく、太田道灌が築いた江戸城をほぼそのまま利用したと考えられる。
徳川家康の江戸入封
1590年、豊臣秀吉によって小田原北条家は滅亡し、同年、徳川家康が江戸に入封する。関東八カ国を与えられた大名にとって当時の江戸城はあまりにも貧素な城であったが、秀吉への配慮があってか応急的な修理しか行っていない。1600年の関ヶ原合戦で勝利してもすぐには大改修を行っていない。豊臣家への戦略を練っており、意識は関西にあったようだ。
1603年、徳川家康は江戸幕府を開府し、天下普請として諸大名を動員。1604年に日本橋を起点とする五街道を整備。この年に神田山を崩して日本橋南方地域の埋め立てたり、日本橋の架橋を行っている。江戸前島の中央線を通して、京橋、新橋を経由する道が東海道である。現在では中央通りと呼ばれている。
江戸城の改修と城下町の建設を始める。寺を追い出し本丸を拡張、城下では武家地や町人地を整備した。台地に屋敷を造り、低湿地を埋め立てて職人町を造っている。現在では不明瞭ながらも、高台の地域を「山の手」、低地にある町を「下町」と呼んでいる。江戸城に通じていた平川(後の日本橋川)を利用し、手始めに造られた堀が道三堀である。道三堀は呉服橋の近くにあり、船入り堀(運河)で、江戸に初めて造られた人工水路の堀である。1606年に二の丸・三の丸の整備、外堀では1606年(慶長11年)に雉子橋から「溜池」までの堀が構築される。1607年には天守が完成した。
徳川家康は1615年に豊臣家を滅ぼし、1616年6月1日に没する(享年75歳)。1636年(寛永13年)に天下普請により江戸城の総構えが完成する。1657年の明暦の大火によって天守閣は焼け落ち、再建されることはなかった。

江戸城が築城された地勢。縄張りの中央には武蔵野台地の南端、西側では多摩丘陵に連なる下末吉(しもすえよしだいち)台地があり、これらの高台から東方へ低地や入江が広がっている。平川が日比谷入江を経由して海に流れ込んでいたため、その流路が低地や砂州になっていた。小田原北条氏の江戸城は土塁の城で、日比谷は入江のまま、日本橋や京橋あたりは海面と同じ高さの湿地帯であった。
かつては砂州で形成された江戸前島があり、南方へ突き出した小半島であった。北からは後の日本橋川の元となる平川が注いでおり、平川の河口および江戸前島の西側は日比谷入江であった。日比谷公園の池、日比谷濠・馬場先濠・和田倉濠など皇居外苑(西の丸 下)周辺の堀は、日比谷入江の名残りである。日比谷入江は和田倉門あたりまであったようで、和田とはワダ(海)であり、海に面した倉というのが名称の由来である。現在においても日比谷入江跡は江戸前島跡よりも低地である。
江戸前島の東側は太田道灌が海上輸送のため整備したと言われる商港の江戸湊があった。江戸前島の東岸も埋め立てて土地を拡張するが、東岸の海岸線あたりに運河となる楓川を開削している。
 国土地理院Webより色別標高図。2024年現在のものであるが、小半島である江戸前島の輪郭が薄っすらと確認できる。江戸前島の西は外堀(外濠川)から低地で日比谷入江の名残、東は楓川から低地で江戸湊の名残が感じられる。また南端は新橋(芝口門)のあたりであることも確認できる。隅田川の中洲だった江戸中島(霊岸島あたり)も周囲よりは微高地である。
国土地理院Webより色別標高図。2024年現在のものであるが、小半島である江戸前島の輪郭が薄っすらと確認できる。江戸前島の西は外堀(外濠川)から低地で日比谷入江の名残、東は楓川から低地で江戸湊の名残が感じられる。また南端は新橋(芝口門)のあたりであることも確認できる。隅田川の中洲だった江戸中島(霊岸島あたり)も周囲よりは微高地である。
家康・秀忠時代の普請
 徳川家康(初代将軍:在任1603年~1605年)、徳川秀忠(2代将軍:在任1605年~1623年)時代の普請は次の通り。
徳川家康(初代将軍:在任1603年~1605年)、徳川秀忠(2代将軍:在任1605年~1623年)時代の普請は次の通り。
1603年、家康が江戸幕府。1604年に日本橋を起点とする五街道を整備。1607年に天守が完成。外堀では、1606年-1607年に雉子橋から溜池までの堀が構築される。しかし、神田山(現・駿河台あたりの丘陵地)を切り崩して日比谷入江(日比谷公園・新橋周辺)を埋め立てた工事により、牛込(現・飯田橋駅近く)から流れている旧平川(後の日本橋川)は下流で洪水を起こすようになった。
 旧平川は最下流部で日比谷入江に注ぐ川であったが、船河原橋(飯田橋あたり)にて工事により東へ流れを変えさせ隅田川へ注ぐようになり、これは後の神田川になった。江戸城の周囲を流れていた旧平川は後の日本橋川の原型になった言われる。
旧平川は最下流部で日比谷入江に注ぐ川であったが、船河原橋(飯田橋あたり)にて工事により東へ流れを変えさせ隅田川へ注ぐようになり、これは後の神田川になった。江戸城の周囲を流れていた旧平川は後の日本橋川の原型になった言われる。
このように1618年(元和4年)、平川の洪水対策および外堀を兼ねた神田川が造られた。神田川の流路を船河原橋(飯田橋近く)あたりで東に曲げて、駿河台を掘り抜いた流路から隅田川へ流している。「飯田町遺跡周辺の歴史」の説明板では1620年のこととしている。この工事により地続きだった神田山が「駿河台、本郷台、湯島台」に分断されそれぞれ独立の台地となった。
平川は流路が埋め立てられ堀留で締め切られ、下流に続いていた平川は独立した堀になった。神田川の小石川門から分岐する水路のようなものはあったようだ(赤線の位置)が、2000年の飯田町遺跡発掘調査によれば、1657年の明暦の大火直後に埋め立てられたことがわかっている。この水路は1903年に再び開削されて現在に至っている。
家光時代の天下普請

1636年、徳川家光(第3代将軍:在任1623年~1651年)による天下普請で、江戸城の総構えが完成する。雉子橋から虎ノ門までの外堀石垣化は西国外様大名(前田・細川・池田・黒田家など)により行われた。
そして、赤坂から牛込にかけての外堀掘削と土塁構築は東国大名が行った。この区域の水堀は川ではないので水循環が悪く、特に市谷から牛込の堀は土砂が堆積しやすく蓮が茂りやすい状態だった。そのため天下普請の後、大名の手伝普請によって頻繁に堀さらいが行われた。
【 江戸城 探索TOP および目次 】



