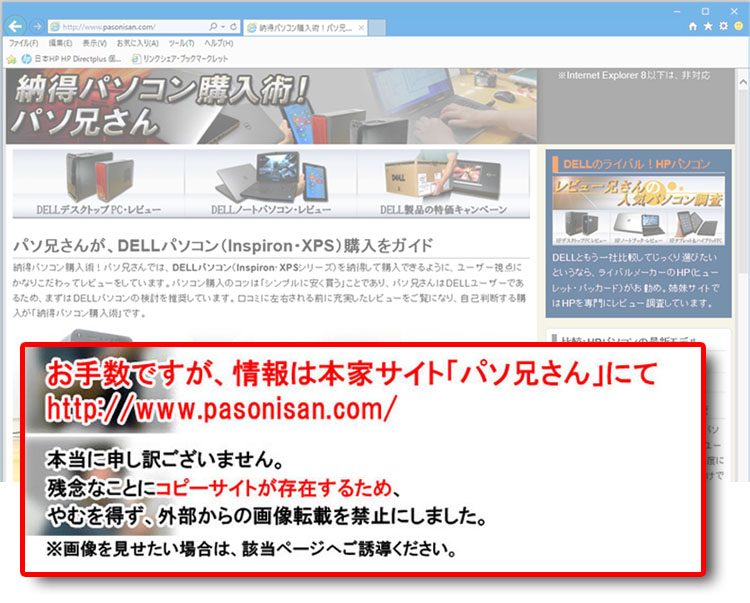

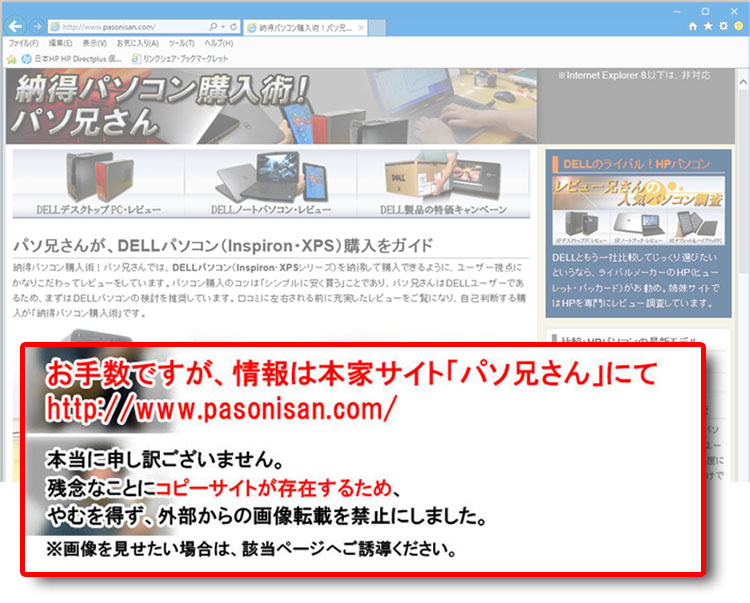
- HOME
- DELLパソコン・モバイル旅行記
- 東京都
- 江戸城(千代田区・中央区ほか)
江戸城 外堀の見附
筋違門(すじかいもん)
筋違橋は1676年(延宝4年)に架けられ、徳川将軍が将軍家墓所である上野寛永寺に詣でる時に渡る橋であった。日光東照宮への社参でも通行している。将軍は江戸城の大手門から出て神田橋門を通り、筋違門を抜けて上野に向かっていた。このように徳川将軍が参詣などで通る道筋のことを御成道(おなりみち)と言った。【 江戸城の外堀に配置された見附の位置 】
 1871年(明治4年)の筋違門。
1871年(明治4年)の筋違門。
 2024年現在の筋違門跡。廃駅となった旧・万世橋駅である。もうこの位置に橋は無く、近くの万世橋が神田川を渡る橋になっている。
2024年現在の筋違門跡。廃駅となった旧・万世橋駅である。もうこの位置に橋は無く、近くの万世橋が神田川を渡る橋になっている。
 JR中央線に沿った道は旧中山道であり、本郷や板橋に向かう中山道と御成道が筋違いに交差していた地点のため、筋違門と呼ばれた。門内(城内側)には火除のための広小路があり、8つの口に通じているので「八つ小路」と俗に呼ばれていた。
JR中央線に沿った道は旧中山道であり、本郷や板橋に向かう中山道と御成道が筋違いに交差していた地点のため、筋違門と呼ばれた。門内(城内側)には火除のための広小路があり、8つの口に通じているので「八つ小路」と俗に呼ばれていた。
 1872年に筋違門が取り壊され、翌年にはその石材を再利用し、この筋違橋の場所に最初の「萬世橋」を築造した。これは当時の東京府知事・大久保忠寛が「よろずよばし」と命名したのだが、大衆は「まんせいばし」と読むようになった。ほかには眼鏡橋とも呼ばれた。
1872年に筋違門が取り壊され、翌年にはその石材を再利用し、この筋違橋の場所に最初の「萬世橋」を築造した。これは当時の東京府知事・大久保忠寛が「よろずよばし」と命名したのだが、大衆は「まんせいばし」と読むようになった。ほかには眼鏡橋とも呼ばれた。
1903年(明治36年)に、現在の位置に2つめとなる万世橋が架け直された。筋違橋の場所に架けられていた初代の万世橋は「元万世橋」と改名したが、後に撤去され、そこには橋が架けられなくなった。1923年(大正12年)の関東大震災で万世橋が被災すると、1930年(昭和5年)に石とコンクリート混成のアーチ橋に架け替えられた。
 現在の万世橋。南詰には2006年まで交通博物館があった。
現在の万世橋。南詰には2006年まで交通博物館があった。
 ほとんどの人々が命名者が意図した「よろずよばし」とは読めなかったようだ。それか、言い難くてあえて呼ばなかったのかもしれない。
ほとんどの人々が命名者が意図した「よろずよばし」とは読めなかったようだ。それか、言い難くてあえて呼ばなかったのかもしれない。
 昌平橋からみた現在の万世橋。筋違橋があったのは、この両橋の中間あたり。
昌平橋からみた現在の万世橋。筋違橋があったのは、この両橋の中間あたり。
 筋違門跡は旧万世橋駅でもある。この駅舎が利用され、2013年にmAAch ecute(マーチエキュート) 神田万世橋が開業した。
筋違門跡は旧万世橋駅でもある。この駅舎が利用され、2013年にmAAch ecute(マーチエキュート) 神田万世橋が開業した。
 mAAch ecuteと万世橋。
mAAch ecuteと万世橋。
 神田川と旧万世橋駅。この高架に中央線の線路が敷かれている。
神田川と旧万世橋駅。この高架に中央線の線路が敷かれている。
 ちょうど中央線の列車が走行してきたので撮影。
ちょうど中央線の列車が走行してきたので撮影。
 関東大震災で焼失した万世橋駅。
関東大震災で焼失した万世橋駅。
 1930年(昭和5年)に完成した万世橋。
1930年(昭和5年)に完成した万世橋。
 万世橋より北は江戸城の城外となる(中央通り-国道17号)。JR総武線が見え、秋葉原電気街につながっている。休日には歩行者天国となる。
万世橋より北は江戸城の城外となる(中央通り-国道17号)。JR総武線が見え、秋葉原電気街につながっている。休日には歩行者天国となる。
 筋違門から神田川(江戸城外堀)に沿って東へ進むと浅草橋門にたどり着く。そこは神田川の最下流であり、隅田川へ合流するポイントとなっている。また、その間には土手が築かれており、柳原土手と呼ばれていた。
筋違門から神田川(江戸城外堀)に沿って東へ進むと浅草橋門にたどり着く。そこは神田川の最下流であり、隅田川へ合流するポイントとなっている。また、その間には土手が築かれており、柳原土手と呼ばれていた。
柳原土手(やなぎはらどて)
筋違門から浅草門までの約1.1kmに渡り、外堀・神田川の南岸に「柳原土手」が築かれていた。柳並木があったことが名称の由来である。最初に、土手に沿って住み始めたのは大名や旗本などの武士であったが、江戸後期になると商人や職人で栄え始める。
 柳原土手と土手下の柳森神社。神田川に跨り南北を結ぶ和泉橋。1794年には火除け地が設けられている。
柳原土手と土手下の柳森神社。神田川に跨り南北を結ぶ和泉橋。1794年には火除け地が設けられている。
 浅草門までの柳原土手。
浅草門までの柳原土手。
土手の以南では町屋が建ち並び、人々は土手の上を通行していた。土手の下では古着や古道具を売る葦簀張りの店が並んでいたという。扱われた柳原物は「安かろう悪かろう」と言われた。岩本町周辺では古着屋多く、現在に至るまで、岩本町・神田須田町・東神田の一帯は衣料の町として発展している。
 江戸時代後期、柳原土手に沿って古着を扱う床店(露店)。日本橋富沢町とともに、江戸市中の古着を扱う市場の一つとして知られ、「既製服問屋街発祥の地」となっている。
江戸時代後期、柳原土手に沿って古着を扱う床店(露店)。日本橋富沢町とともに、江戸市中の古着を扱う市場の一つとして知られ、「既製服問屋街発祥の地」となっている。
1873年(明治6年)に柳原土手は崩された。1881年(明治14年)に「岩本町古着市場」が開設され、多い時には400軒も古着屋が軒を連ねたという。そして東京の衣類産業の中心地となった。洋服が日常衣類となり既製服の需要が中心になると、洋服の町へと変貌した。太平洋戦争では空襲によって焼き尽くされたが、戦後に復興が始まり繊維メーカーが集まるようになった。
柳森神社(柳森稲荷神社)
 土手下で河岸の柳森神社。1458年、太田道灌が江戸城の鬼門除けとして、京都の伏見稲荷を勧請して創建したという。この際、多くの柳をこの地に植えたとされる。5代将軍の徳川綱吉の母、桂昌院(けいしょういん)が信仰した福壽神が祀られている。
土手下で河岸の柳森神社。1458年、太田道灌が江戸城の鬼門除けとして、京都の伏見稲荷を勧請して創建したという。この際、多くの柳をこの地に植えたとされる。5代将軍の徳川綱吉の母、桂昌院(けいしょういん)が信仰した福壽神が祀られている。
 柳森神社境内にある富士塚の痕跡。1960年(昭和35年)に富士塚は取り壊され現存していない。富士講の名残りである石碑群が残されているのみ。
柳森神社境内にある富士塚の痕跡。1960年(昭和35年)に富士塚は取り壊され現存していない。富士講の名残りである石碑群が残されているのみ。
和泉橋
 和泉橋に到着。津藩 藤堂和泉守の上屋敷前に向かう通りに架かっていたので、和泉橋と呼ばれる。1892年(明治25年)に鉄橋となり、関東大震災後の復興事業で1927年(昭和2年)に架橋されたのが現在の和泉橋である。
和泉橋に到着。津藩 藤堂和泉守の上屋敷前に向かう通りに架かっていたので、和泉橋と呼ばれる。1892年(明治25年)に鉄橋となり、関東大震災後の復興事業で1927年(昭和2年)に架橋されたのが現在の和泉橋である。
柳原通り
 和泉橋から美倉橋までの柳原通りで開催されていた、岩本町・東神田ファミリーバザール。年二回開催される。関東大震災後、この通りでは東北より出稼ぎに来た大工たちによって看板建築が多く造られた。和泉橋の西側の柳原通りでは、「岡昌裏地ボタン店、海老原商店」に看板建築が今も残っている。
和泉橋から美倉橋までの柳原通りで開催されていた、岩本町・東神田ファミリーバザール。年二回開催される。関東大震災後、この通りでは東北より出稼ぎに来た大工たちによって看板建築が多く造られた。和泉橋の西側の柳原通りでは、「岡昌裏地ボタン店、海老原商店」に看板建築が今も残っている。
 岡昌裏地ボタン店
岡昌裏地ボタン店
 海老原商店。
海老原商店。
美倉橋は、新シ橋なのか?
 神田川に架かり、清洲橋通り上にある美倉橋。寛文年間(1670年)以降の江戸古地図には、「新シ橋」という橋が近い位置に架けられている。正保年間(1644年~1650年)には記載はなく、承応年間(1653年~1655年)になって「くわんはし」なるものが記載されるようになる。
神田川に架かり、清洲橋通り上にある美倉橋。寛文年間(1670年)以降の江戸古地図には、「新シ橋」という橋が近い位置に架けられている。正保年間(1644年~1650年)には記載はなく、承応年間(1653年~1655年)になって「くわんはし」なるものが記載されるようになる。
柳原土手にも外濠石垣が敷かれていた
 浅草見附側から始まる柳原通り(開智日本橋学園中学・高等学校の南東角)。かつてはここから柳原土手が続いていたばずだが、起点の位置にモニュメント的な江戸城の石垣石が置いてある。説明板によると、平成19年・20年の発掘調査にて、ここから50m~60mほど行ったところから出土した石とのこと。たぶん、開智日本橋学園中学の敷地内。柳原土手にも外濠石垣が敷かれていたという新発見となった。
浅草見附側から始まる柳原通り(開智日本橋学園中学・高等学校の南東角)。かつてはここから柳原土手が続いていたばずだが、起点の位置にモニュメント的な江戸城の石垣石が置いてある。説明板によると、平成19年・20年の発掘調査にて、ここから50m~60mほど行ったところから出土した石とのこと。たぶん、開智日本橋学園中学の敷地内。柳原土手にも外濠石垣が敷かれていたという新発見となった。
【 江戸城 探索TOP および目次 】



