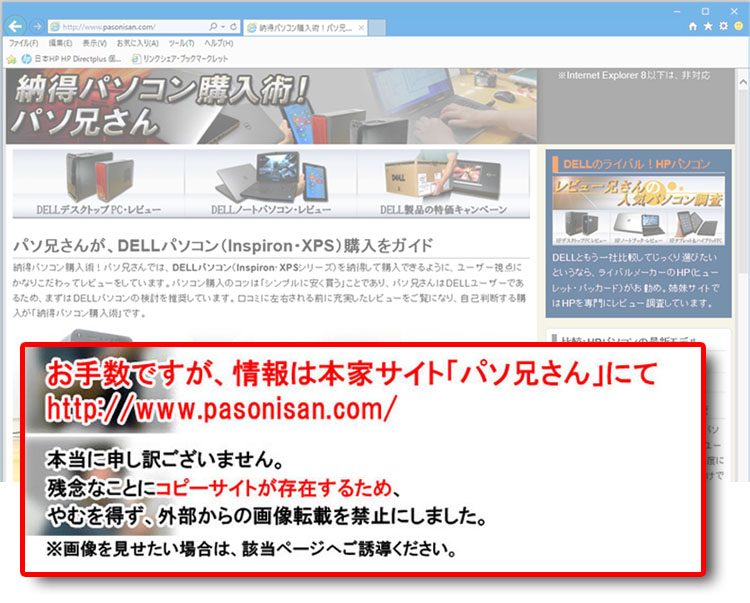

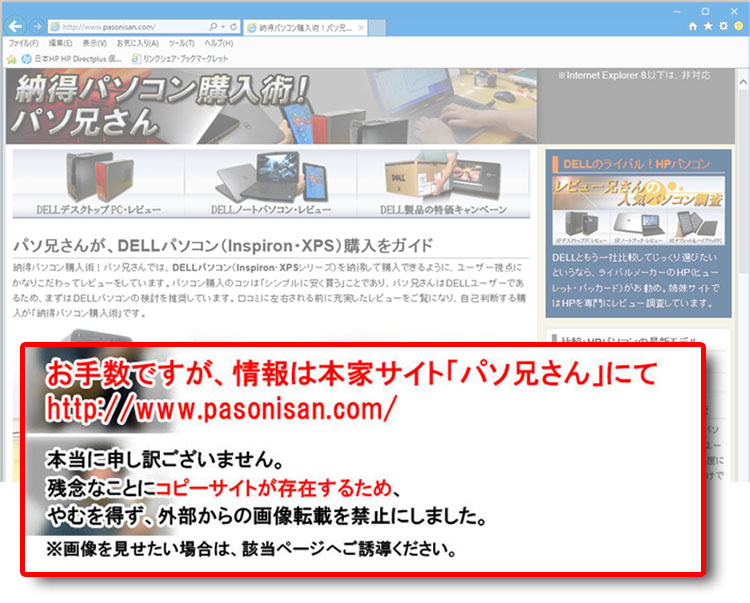
- HOME
- DELLパソコン・モバイル旅行記
- 東京都
- 江戸城(千代田区・中央区ほか)
江戸城の基礎知識
江戸城 ~ 外堀(水堀)の消失と、国史跡指定地
 かつては水堀に囲まれた総構えであり、利用した河川は、神田川、日本橋川、そして日本橋川から分岐した外濠川、溜池の堰を上流とする汐留川。それぞれ隅田川に注ぐ方面が下流になっている。
かつては水堀に囲まれた総構えであり、利用した河川は、神田川、日本橋川、そして日本橋川から分岐した外濠川、溜池の堰を上流とする汐留川。それぞれ隅田川に注ぐ方面が下流になっている。
神田上水が整備されるまで主な上水であった溜池も外堀の一部として利用。溜池は汐留川よりも高地にあり、堰を設けて汐留川へ水が流れる。
弁慶堀 - 真田堀 - 市谷堀 - 牛込堀 - 飯田堀は、川ではなく見附の土橋で区切られ独立した池になっている。土橋に設置された堰によって水位が調整された。外堀で最も水位の高い「真田堀」から堰を通して低地の「牛込堀」、飯田堀へ流れて神田川に合流する。明治時代以降の埋め立てにより、現在、水堀として残されているのは一部である。
埋め立てられて消失した外堀
 明治期から昭和期にかけて埋め立てられた外堀が「赤いライン」のところ。水堀が残っている所は「青ライン」で示した。「外濠川-汐留川-溜池」は完全一致ではないが概ね外堀通りに、真田堀は上智大学の運動場、市谷堀の一部は外濠公園グラウンドに、飯田堀は市街地再開発事業のビル建設で消失して地下水路が通っている。
明治期から昭和期にかけて埋め立てられた外堀が「赤いライン」のところ。水堀が残っている所は「青ライン」で示した。「外濠川-汐留川-溜池」は完全一致ではないが概ね外堀通りに、真田堀は上智大学の運動場、市谷堀の一部は外濠公園グラウンドに、飯田堀は市街地再開発事業のビル建設で消失して地下水路が通っている。
堀留から北側の水路は江戸時代に埋め立てられたが、1903年に再び開削され、現在は神田川とつながっている。なお、牛込堀に新見附橋(土橋)が架けられ堀が仕切られたので、牛込堀の一部が新たに新見附堀と呼ばれるようになった。そのため、新見附橋は江戸時代の見附とはまったく関係ない。
 四ツ谷駅に展示されていた外堀埋め立てMAP。溜池の埋め立てが最も早く1889年(明治22年)。
四ツ谷駅に展示されていた外堀埋め立てMAP。溜池の埋め立てが最も早く1889年(明治22年)。
国指定史跡の江戸城 外堀跡
 外堀跡における国の史跡指定地は、赤坂門から牛込門に至る西方の堀、そして虎ノ門付近に点在する石垣エリア、常盤橋門跡である。指定地は総構えの30%ほどの約4kmとなっている。
外堀跡における国の史跡指定地は、赤坂門から牛込門に至る西方の堀、そして虎ノ門付近に点在する石垣エリア、常盤橋門跡である。指定地は総構えの30%ほどの約4kmとなっている。
1911年(明治44年)、喰違から牛込までの土手遊歩道を、江戸城外堀として永久保存するため公園化が計画された。1923年(大正12年)の関東大震災後、市谷堀の一部埋め立てなどもあり、これが後の四谷駅から飯田橋駅(牛込)に至る約2kmの外濠公園となっている。1927年(昭和2年)、新見附橋から牛込橋までの区域が「東京市立土手公園」として開設。
1935年~1937年に「雉子橋から幸橋までの外堀」を史跡指定する動きがあった。しかし、東京-品川間の鉄道路線増設計画や戦争により見送られた。
 戦後、1956年に赤坂門~牛込門までの外堀が国指定史跡の江戸城外堀跡となり、約4kmの規模がある。この赤坂門から牛込門へ続く外堀は、1636年に徳川家光の命により東国大名52家が分担して普請した。この区間の外堀は起伏のある地形(山の手)を巧みに取り入れており、溜池から延びる谷筋(赤坂~喰違)、旧紅葉川の谷筋(市谷~牛込)を利用している。見附と結ぶ橋はすべて土橋となっている。
戦後、1956年に赤坂門~牛込門までの外堀が国指定史跡の江戸城外堀跡となり、約4kmの規模がある。この赤坂門から牛込門へ続く外堀は、1636年に徳川家光の命により東国大名52家が分担して普請した。この区間の外堀は起伏のある地形(山の手)を巧みに取り入れており、溜池から延びる谷筋(赤坂~喰違)、旧紅葉川の谷筋(市谷~牛込)を利用している。見附と結ぶ橋はすべて土橋となっている。
喰違から四谷にかけては、江戸城の外堀でもっとも高台であったため大規模な掘削工事となった。掘り出された大量の土は谷の埋め立てに利用され、武家地や町屋の拡張に利用されたと考えられる。また、堀工事の1/7を負担した仙台藩伊達家では、5700人の人足を動員したという。
 赤坂門から牛込門までの堀。明治期以降、一部が埋め立てられ2つに分かれたことで発生した新見附堀や、明治期にかけられた橋名が由来の弁慶堀があるので、江戸時代に呼ばれた名称ではないことに留意しておこう。
赤坂門から牛込門までの堀。明治期以降、一部が埋め立てられ2つに分かれたことで発生した新見附堀や、明治期にかけられた橋名が由来の弁慶堀があるので、江戸時代に呼ばれた名称ではないことに留意しておこう。
 現在では一部埋め立てられているが、起伏の激しいこの堀では湧き水や玉川上水の水を湛えていた。最も水位の高い真田堀と、最も低い牛込門東側(神田川側)との水面高低差は約20mもある。そのため、四谷門・市谷門・牛込門の土橋に堰を設けて水位を調整し、水深を一定に保っていた。
現在では一部埋め立てられているが、起伏の激しいこの堀では湧き水や玉川上水の水を湛えていた。最も水位の高い真田堀と、最も低い牛込門東側(神田川側)との水面高低差は約20mもある。そのため、四谷門・市谷門・牛込門の土橋に堰を設けて水位を調整し、水深を一定に保っていた。
 各区域の堀普請を担当した大名家。
各区域の堀普請を担当した大名家。
【 江戸城 探索TOP および目次 】



