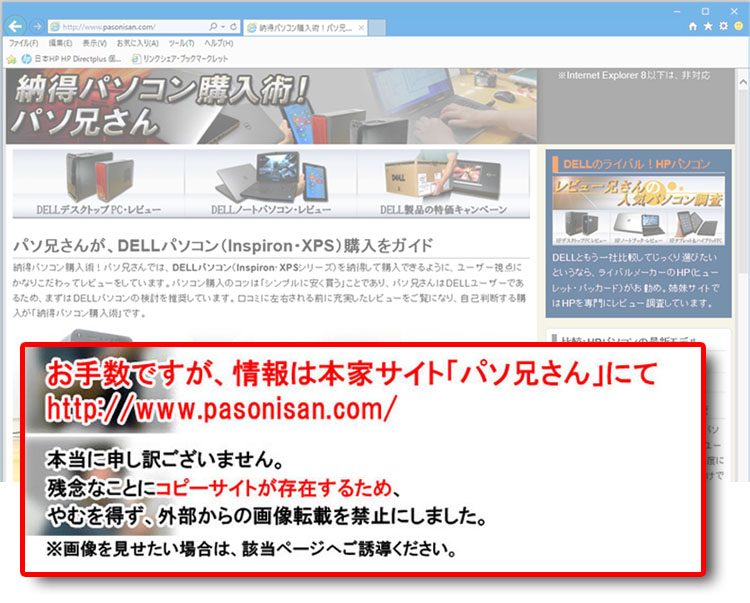

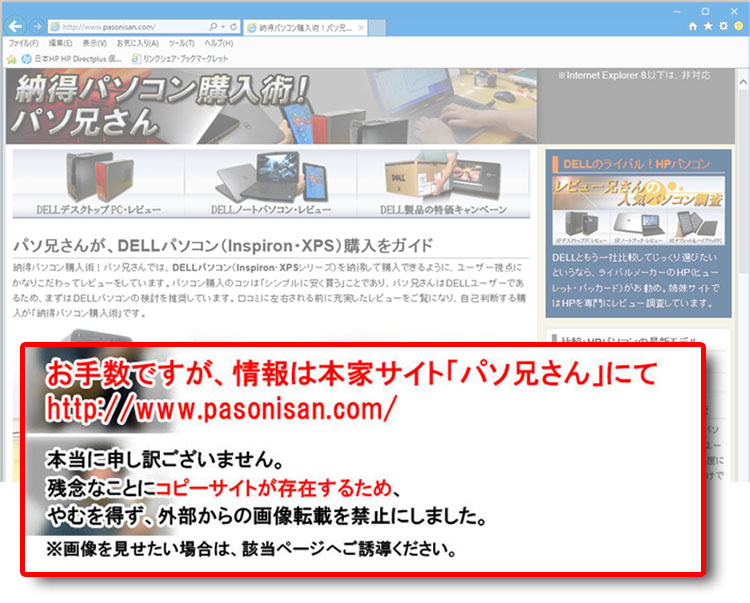
- HOME
- DELLパソコン・モバイル旅行記
- 東京都
- 江戸城(千代田区・中央区ほか)
江戸の運河
浜町堀・竜閑川
浜町堀(浜町川)は中央区日本橋浜町から千代田区岩本町あたりまで流れていた運河。岩本町あたりで西側の竜閑川と接続しL字型の流路となっている。江戸時代初頭に浜町堀の開削が始まり、1691年には竜閑川と接続した。竜閑川は竜閑橋のところで、外堀の日本橋川と接続している。【 江戸城の東端の運河 】
 組合橋あたり浜町堀の一部は、元吉原遊廓のお歯黒どぶ(遊女の逃亡を防ぐ堀)にも利用され、末広稲荷神社の近くにある入江橋で分岐する堀は元吉原の堀割である。
組合橋あたり浜町堀の一部は、元吉原遊廓のお歯黒どぶ(遊女の逃亡を防ぐ堀)にも利用され、末広稲荷神社の近くにある入江橋で分岐する堀は元吉原の堀割である。
日光街道(奥州街道)の第一橋であった緑橋は、浜町堀に架かる代表的な橋であった。これが由来で、西岸を西緑河岸、東岸を東緑河岸という。浜町堀は戦後に埋め立てられ、跡地は浜町川緑道となった。
 箱崎川 接続点から竜閑川 接続点までの浜町堀を歩いてみる。つまり下流から上流側へ進む。首都高6号の架線下が箱崎川で、リムジンバス保管所あたりが浜町堀との接続点である。
箱崎川 接続点から竜閑川 接続点までの浜町堀を歩いてみる。つまり下流から上流側へ進む。首都高6号の架線下が箱崎川で、リムジンバス保管所あたりが浜町堀との接続点である。
浜町堀
 浜町堀跡地である浜町川緑道。ここには川口橋が架かっていた。浜町堀跡は組合橋があった交差点まで高架下になっている。
浜町堀跡地である浜町川緑道。ここには川口橋が架かっていた。浜町堀跡は組合橋があった交差点まで高架下になっている。
 組合橋のあった交差点から撮影した、北への緑道。
組合橋のあった交差点から撮影した、北への緑道。
 弁慶像で知られる甘酒横丁に交差するところだが、江戸時代はここに橋も通りもない。
弁慶像で知られる甘酒横丁に交差するところだが、江戸時代はここに橋も通りもない。
 久松児童公園の入口。近年では車道だったようだが、2010年代頃より車道通行を禁止にして公園化された。この久松警察署前交差点のあたりに小川橋があった。そこには「小川橋の由来」の碑が建っている。1882年(明治15年)、「日本初の拳銃強盗犯」として知られた清水定吉の発砲で殉職した、久松警察署の巡査 小川佗吉郎の名にちなむという。
久松児童公園の入口。近年では車道だったようだが、2010年代頃より車道通行を禁止にして公園化された。この久松警察署前交差点のあたりに小川橋があった。そこには「小川橋の由来」の碑が建っている。1882年(明治15年)、「日本初の拳銃強盗犯」として知られた清水定吉の発砲で殉職した、久松警察署の巡査 小川佗吉郎の名にちなむという。
アプリの「大江戸今昔めぐり」では江戸末期の古地図なのに「小川橋」と記載されており、時代背景が可笑しな事になっているが、江戸切絵図には「難波橋」と記載されていた。この殉職事件によって難波橋から小川橋に改称したのであろうか。
 久松児童公園の北端あたりが高砂橋のあったところ。
久松児童公園の北端あたりが高砂橋のあったところ。
 栄橋があったところ。そして北へ向かう浜町堀跡の路地。
栄橋があったところ。そして北へ向かう浜町堀跡の路地。
 千鳥橋があったところ。東日本橋三丁目中央通りのプレートが目印で、跡地の路地が続く。この先、共栄会通りと交差するところが汐見橋。浜町堀跡の細い路地で路上喫煙する輩が多く、たばこパトロールのおじさん達がよく巡回している。
千鳥橋があったところ。東日本橋三丁目中央通りのプレートが目印で、跡地の路地が続く。この先、共栄会通りと交差するところが汐見橋。浜町堀跡の細い路地で路上喫煙する輩が多く、たばこパトロールのおじさん達がよく巡回している。
 日光街道(奥州街道)の第一橋であった緑橋は、株式会社三上アパレルのあたりにあった。その細い路地が浜町堀跡。代表的な橋であったのだから旧跡地を示す案内板くらい置くべきだと思うのだが・・。浜町堀に沿って通る「みどり通り」は、この緑橋にちなんでいる。
日光街道(奥州街道)の第一橋であった緑橋は、株式会社三上アパレルのあたりにあった。その細い路地が浜町堀跡。代表的な橋であったのだから旧跡地を示す案内板くらい置くべきだと思うのだが・・。浜町堀に沿って通る「みどり通り」は、この緑橋にちなんでいる。
 竹森神社に続く浜町堀跡の路地。
竹森神社に続く浜町堀跡の路地。
 竹職人の町ともいわれた小伝馬町三丁目の守護神、竹森神社。江戸時代ではこの付近に竹藪が多く、それに因んで竹森神社と称したという。「江戸七森」のひとつに数えられており、ほかには「椙森神社、烏森神社、初音森神社、柳森神社、あずまの森、笹森神社」がある。
竹職人の町ともいわれた小伝馬町三丁目の守護神、竹森神社。江戸時代ではこの付近に竹藪が多く、それに因んで竹森神社と称したという。「江戸七森」のひとつに数えられており、ほかには「椙森神社、烏森神社、初音森神社、柳森神社、あずまの森、笹森神社」がある。
 竹森神社に隣接している龍閑児童遊園。ここが浜町堀と竜閑川の接続点で、浜町堀からL字に曲がって竜閑川となり、江戸城外堀の日本橋川につながっている。
竹森神社に隣接している龍閑児童遊園。ここが浜町堀と竜閑川の接続点で、浜町堀からL字に曲がって竜閑川となり、江戸城外堀の日本橋川につながっている。
竜閑川(神田八丁堀)
1691年、江戸城外堀に発し、隅田川に通じる堀割開削がされる。竜閑川は始め「神田堀、しろがね堀、神田八丁堀」などと呼ばれていたが、外堀と堀割の接点に井上竜閑(江戸城殿中接待役/旧幕府坊主)が住んでいたので竜閑川と呼ばれるようになった。もともとは橋が竜閑橋と呼ばれるようになって、それから橋の名称に因んで竜閑川と名付けられている。神田と日本橋を区分する境界になり、現在においては千代田区と中央区の区界になっている。
幕末(1857年)に埋立てられて一度は消失するが、明治時代(1883年)に再び開削された。戦後、瓦礫処理のために埋め立てが始まり、1925年(昭和25年)にすべての堀が埋め立てられた。
 始めに神田八丁堀と呼ばれた出来事は次の通り。明暦の大火(1657年)で江戸市中が大きな被害を受けた後、防火のための土手が八丁(約870m)にわたって築かれた。側には火除明地が作られたが、1691年、町人らの自費により明地を堀に開削した。これが神田八丁堀(後の改称:竜閑川)である。
始めに神田八丁堀と呼ばれた出来事は次の通り。明暦の大火(1657年)で江戸市中が大きな被害を受けた後、防火のための土手が八丁(約870m)にわたって築かれた。側には火除明地が作られたが、1691年、町人らの自費により明地を堀に開削した。これが神田八丁堀(後の改称:竜閑川)である。
 1945年~1950年の航空写真を見ると神田川への流路が確認できる。これは明治時代(1883年)に新規開削されたものなので、江戸時代にはない。
1945年~1950年の航空写真を見ると神田川への流路が確認できる。これは明治時代(1883年)に新規開削されたものなので、江戸時代にはない。
それでは、日本橋川(江戸城外堀)に向かって竜閑川の跡地を歩いていく。
 龍閑児童遊園のすぐ向かい。ここから竜閑川で、幽霊橋があったところ。竹藪が多く薄気味悪い風景が由来なのだろう。
龍閑児童遊園のすぐ向かい。ここから竜閑川で、幽霊橋があったところ。竹藪が多く薄気味悪い風景が由来なのだろう。
 元吉原遊廓のメインストリート「大門通り」に交差する地点が、甚兵衛橋があった所。
元吉原遊廓のメインストリート「大門通り」に交差する地点が、甚兵衛橋があった所。
 人形町通りと交差する地点が、九道橋のあった所。その南側(写真でいうと左)の角が伝馬町牢屋敷で、吉田松陰終焉の地で知られる。
人形町通りと交差する地点が、九道橋のあった所。その南側(写真でいうと左)の角が伝馬町牢屋敷で、吉田松陰終焉の地で知られる。
 伝馬町牢屋敷跡の北側、駐車場が広がっているあたりに、待合橋があった。十思スクエア(屋敷跡かつ旧 十思小学校の校舎)が見えるが、古地図をみるとその手前に土手が築かれていたようだ。
伝馬町牢屋敷跡の北側、駐車場が広がっているあたりに、待合橋があった。十思スクエア(屋敷跡かつ旧 十思小学校の校舎)が見えるが、古地図をみるとその手前に土手が築かれていたようだ。
 首都高1号線上野線に接する「地蔵橋南東児童遊園」の所に地蔵橋があった。ここの説明板のタイトルでは「神田八丁堀跡」と書かれているが、後に竜閑川と呼ばれる堀のことである。
首都高1号線上野線に接する「地蔵橋南東児童遊園」の所に地蔵橋があった。ここの説明板のタイトルでは「神田八丁堀跡」と書かれているが、後に竜閑川と呼ばれる堀のことである。
 首都高を挟んで西側に地蔵橋公園があり、竜閑川埋立記念碑が建つ。竜閑川の跡地は続く。
首都高を挟んで西側に地蔵橋公園があり、竜閑川埋立記念碑が建つ。竜閑川の跡地は続く。
 日本橋から北へ延びる中山道(中央通り)と交差する地点に今川橋はあった。日本橋から出発し、東海道以外の街道を通るならば、初めて渡る橋が今川橋であった。架設されたのは天和年間(1681~1683)と記録が残っている。当時地元町人の代表であった名主、今川善右衛門の尽力により橋が架けられた事が名称由来とされる。1950年に竜閑川が埋め立てられるが、同時に今川橋も解体され長い歴史を閉じた。
日本橋から北へ延びる中山道(中央通り)と交差する地点に今川橋はあった。日本橋から出発し、東海道以外の街道を通るならば、初めて渡る橋が今川橋であった。架設されたのは天和年間(1681~1683)と記録が残っている。当時地元町人の代表であった名主、今川善右衛門の尽力により橋が架けられた事が名称由来とされる。1950年に竜閑川が埋め立てられるが、同時に今川橋も解体され長い歴史を閉じた。
 江戸名所図会(1834年)で描かれている、中山道、今川橋および竜閑川。竜閑川で運んだとみられる陶磁器を商う商人が描かれている。諸説あるが、安永年間(1772年-1781年)にこの付近で発売された和菓子が「今川焼き」で、評判となったため一般名称になったという。安永6年(1777年)に記された史料『富貴地座位』に「今川やき 那須屋弥平 本所」と書かれているが、これが現在知られる今川焼きと同じなのかは不明。
江戸名所図会(1834年)で描かれている、中山道、今川橋および竜閑川。竜閑川で運んだとみられる陶磁器を商う商人が描かれている。諸説あるが、安永年間(1772年-1781年)にこの付近で発売された和菓子が「今川焼き」で、評判となったため一般名称になったという。安永6年(1777年)に記された史料『富貴地座位』に「今川やき 那須屋弥平 本所」と書かれているが、これが現在知られる今川焼きと同じなのかは不明。
 東北新幹線、山手線などJR線の架線下あたりに乞食橋はあった。
東北新幹線、山手線などJR線の架線下あたりに乞食橋はあった。
 竜閑橋に続く今川小路。
竜閑橋に続く今川小路。
 鎌倉児童遊園のあたりが竜閑橋のあった所。江戸城外堀と竜閑川の接続点である。ここより西側は神田橋まで鎌倉河岸が広がっていた。もともと神田の堀に架けられていた橋が堀の埋め立てで不要になり、新しく開削された堀割(竜閑川)に移設されたのが竜閑橋であった。竜閑橋にちなみ竜閑川と呼ばれた。
鎌倉児童遊園のあたりが竜閑橋のあった所。江戸城外堀と竜閑川の接続点である。ここより西側は神田橋まで鎌倉河岸が広がっていた。もともと神田の堀に架けられていた橋が堀の埋め立てで不要になり、新しく開削された堀割(竜閑川)に移設されたのが竜閑橋であった。竜閑橋にちなみ竜閑川と呼ばれた。
 明治時代の竜閑橋。
明治時代の竜閑橋。
 大正15年(1926年)に造られた竜閑橋の一部が現地に残されている。鉄筋コンクリートトラスの橋では日本初であった。
大正15年(1926年)に造られた竜閑橋の一部が現地に残されている。鉄筋コンクリートトラスの橋では日本初であった。
浜町堀・竜閑川近辺の跡地
清水家 / 津山藩 松平三河守 屋敷跡
 蛎殻町周辺は堀割で囲まれた武家地であった。川口橋の近くの蛎殻町公園は清水家屋敷跡。さらに古くは津山藩 松平三河守の下屋敷があった。明治時代には豪商・杉村甚兵衛の屋敷となったが、関東大震災の時には近所の人々がその広い庭に逃げ込み助かった話も伝わっている。震災復興計画により、昭和6年、蛎殻町公園として開園した。
蛎殻町周辺は堀割で囲まれた武家地であった。川口橋の近くの蛎殻町公園は清水家屋敷跡。さらに古くは津山藩 松平三河守の下屋敷があった。明治時代には豪商・杉村甚兵衛の屋敷となったが、関東大震災の時には近所の人々がその広い庭に逃げ込み助かった話も伝わっている。震災復興計画により、昭和6年、蛎殻町公園として開園した。
笠間稲荷神社 東京別社
 高砂橋、難波橋(後の小川橋?)跡の近くに鎮座する笠間稲荷神社 東京別社(日本橋浜町)。日本三大稲荷のひとつ茨城県笠間稲荷神社(胡桃下稲荷、紋三郎稲荷)の東京別社である。当時、ここに笠間藩 牧野氏の屋敷があり、1860年、第8代藩主の牧野貞直が藩邸内に笠間稲荷神社を分祀した。関東大震災には社殿を焼失、再建後、昭和20年3月の東京大空襲で社殿が全焼しているが、同年12月には本殿を再建している。
高砂橋、難波橋(後の小川橋?)跡の近くに鎮座する笠間稲荷神社 東京別社(日本橋浜町)。日本三大稲荷のひとつ茨城県笠間稲荷神社(胡桃下稲荷、紋三郎稲荷)の東京別社である。当時、ここに笠間藩 牧野氏の屋敷があり、1860年、第8代藩主の牧野貞直が藩邸内に笠間稲荷神社を分祀した。関東大震災には社殿を焼失、再建後、昭和20年3月の東京大空襲で社殿が全焼しているが、同年12月には本殿を再建している。
元吉原
江戸のはじめ、1617年に葦の茂る湿地帯であったこの地を埋め立てて造成されたのが、最初の吉原遊廓(元吉原)である。当初は「葭原」と称した。1万4千坪を堀で囲んだ遊郭は江戸一の歓楽街であったが、明暦の大火(1657年)に焼失し39年間の歴史を閉じた。浅草の山谷に移転したのが新吉原と呼ばれる。元吉原の跡地は新和泉・住吉・高砂・浪花(難波)の4町の商業地となった。
 浜町堀を挟んで笠間稲荷神社(牧野氏の屋敷跡)の西側が、元吉原の跡地。高砂町から難波町(富沢町~人形町2丁目の一部)の範囲だったようだ。南端には元吉原堀割(お歯黒どぶ)があり、明暦の大火(1657年)後、新吉原に移転した後は運河として利用していたようだ。
浜町堀を挟んで笠間稲荷神社(牧野氏の屋敷跡)の西側が、元吉原の跡地。高砂町から難波町(富沢町~人形町2丁目の一部)の範囲だったようだ。南端には元吉原堀割(お歯黒どぶ)があり、明暦の大火(1657年)後、新吉原に移転した後は運河として利用していたようだ。
 大門通りの稲荷橋跡から見た、東西に延びる元吉原堀割跡の路地。古地図を見ると、橋詰に稲荷社があったようだが今はない。写真右側が東側で、浜町堀と接続する所には入江橋があった。写真左側の方面が「笹巻毛抜」の創業地。笹巻毛抜は寿司で江戸の名物と歌われた江戸三鮨のひとつ。現在は笹巻けぬきすし総本店として神田に移転している。
大門通りの稲荷橋跡から見た、東西に延びる元吉原堀割跡の路地。古地図を見ると、橋詰に稲荷社があったようだが今はない。写真右側が東側で、浜町堀と接続する所には入江橋があった。写真左側の方面が「笹巻毛抜」の創業地。笹巻毛抜は寿司で江戸の名物と歌われた江戸三鮨のひとつ。現在は笹巻けぬきすし総本店として神田に移転している。
この元吉原堀割の河岸は、「住吉町裏河岸、へっつい河岸、難波町裏河岸」と呼ばれていた。へっついとは竈(かまど)の事で、竈門を取り扱う店が多かったという。
 大門通り。交差しているのは現在の末廣通りで、末廣神社が鎮座する通り。
大門通り。交差しているのは現在の末廣通りで、末廣神社が鎮座する通り。
 末廣神社。江戸時代初期、葭原(元吉原)八力町の地主神として信仰されてきた。明暦の大火で吉原が移転してからは、その跡地である新和泉・住吉・高砂・浪花(難波)の4ヶ所の産土神・氏神となった。延宝3年(1675)、社殿を修復した際、扇が発見され喜んだ氏子たちが社号を「末廣」と付けた。
末廣神社。江戸時代初期、葭原(元吉原)八力町の地主神として信仰されてきた。明暦の大火で吉原が移転してからは、その跡地である新和泉・住吉・高砂・浪花(難波)の4ヶ所の産土神・氏神となった。延宝3年(1675)、社殿を修復した際、扇が発見され喜んだ氏子たちが社号を「末廣」と付けた。
後日更新
【 江戸城 探索TOP および目次 】



