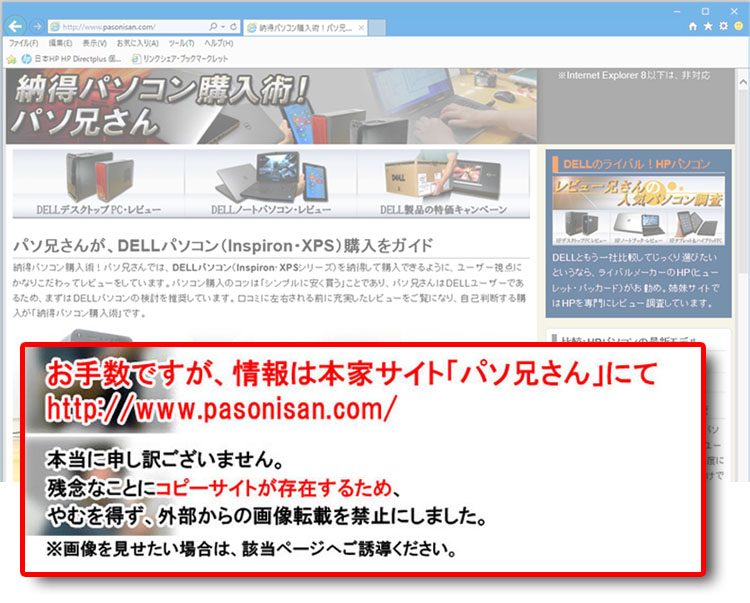

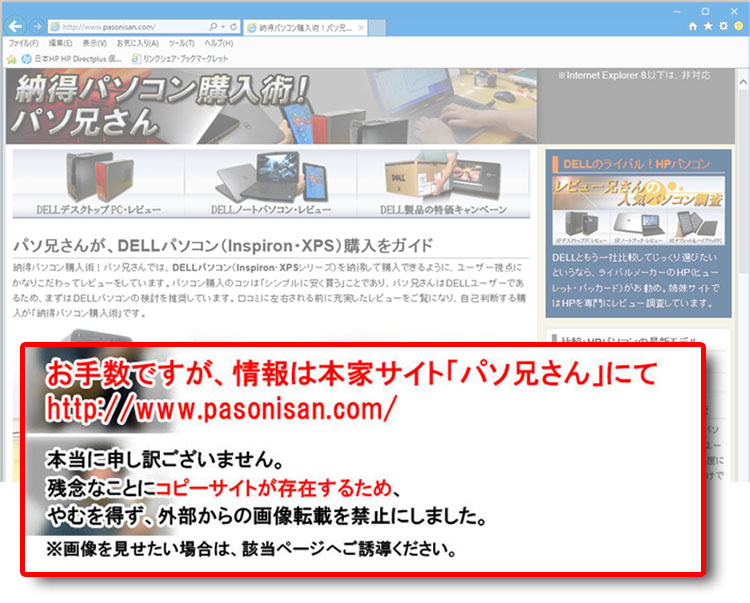
- HOME
- DELLパソコン・モバイル旅行記
- 東京都
- 江戸城(千代田区・中央区ほか)
江戸城 外堀
溜池
江戸城外堀南方、虎ノ門を越えた汐留川の上流には、堰を設けて築いた溜池があった。これは江戸初期の上水源であり外堀としても機能していた。この堰(溜池落口)から滝のように水が流れており、汐留川の水源となっていた。落口とは小さな滝のようなものを指す。溜池は埋め立てられ現在では面影がない。【 江戸城の外堀に配置された見附の位置 】
 明治時代初期の溜池落口の様子。
明治時代初期の溜池落口の様子。
 溜池落口から赤坂門までが溜池の規模。溜池跡(外堀通り)を歩くと「首相官邸、山王日枝神社、衆議院議長公邸」の台地高まりが確認できる。溜池は、堤を作って周囲から集めた湧水を堰き留めた人工の池である。江戸城の外堀でもあるが、溜めた水を上水として利用した。溜池を築造したのは、紀伊和歌山藩主 浅野幸長(よしなが)とされるが詳細不明。港区のHPによれば1606年頃という。
溜池落口から赤坂門までが溜池の規模。溜池跡(外堀通り)を歩くと「首相官邸、山王日枝神社、衆議院議長公邸」の台地高まりが確認できる。溜池は、堤を作って周囲から集めた湧水を堰き留めた人工の池である。江戸城の外堀でもあるが、溜めた水を上水として利用した。溜池を築造したのは、紀伊和歌山藩主 浅野幸長(よしなが)とされるが詳細不明。港区のHPによれば1606年頃という。
※溜池が上水として利用されたのは、小石川上水(1617年~後に拡張して神田上水)、玉川上水(1653年頃)が開かれるまでの間である。
 古地図によって溜池の形状が異なっており、この古地図ではまだ「大溜」は描かれていない。どうやら、明暦の大火(1657年)以降、徐々に溜池の埋め立てが進んで周囲は変化を遂げている。土砂の流入や塵芥の沈殿も進んでいた。山王日枝神社の東隣にあった二本松藩丹羽家の上屋敷は、もともと谷が入り込んだ地形であったが、溜池の埋め立てにより屋敷地が拡大した。江戸中期には蓮が植えられ、琵琶湖や淀川から鯉や鮒を取り寄せて放したという話もあり、江戸名所として親しまれている。
古地図によって溜池の形状が異なっており、この古地図ではまだ「大溜」は描かれていない。どうやら、明暦の大火(1657年)以降、徐々に溜池の埋め立てが進んで周囲は変化を遂げている。土砂の流入や塵芥の沈殿も進んでいた。山王日枝神社の東隣にあった二本松藩丹羽家の上屋敷は、もともと谷が入り込んだ地形であったが、溜池の埋め立てにより屋敷地が拡大した。江戸中期には蓮が植えられ、琵琶湖や淀川から鯉や鮒を取り寄せて放したという話もあり、江戸名所として親しまれている。
 この古地図では、溜池落口近くに、少し欠けて分岐した池(大溜)があり、側に「馬場」が設けられている。馬用に確保した水源なのかもしれない。周囲がだんだん埋め立てられて、町屋や馬場・紺屋物干場などができたらしいので、これは後期の地図だと思われる。
この古地図では、溜池落口近くに、少し欠けて分岐した池(大溜)があり、側に「馬場」が設けられている。馬用に確保した水源なのかもしれない。周囲がだんだん埋め立てられて、町屋や馬場・紺屋物干場などができたらしいので、これは後期の地図だと思われる。
 これは数寄屋橋にあったパネル写真で時代の明記がなかったが、明治時代で工部大学校があった頃の地図のようだ。わかりやすいように着色してみたが、溜池がだいぶ細くなっているようだ。
これは数寄屋橋にあったパネル写真で時代の明記がなかったが、明治時代で工部大学校があった頃の地図のようだ。わかりやすいように着色してみたが、溜池がだいぶ細くなっているようだ。
1875年(明治8年)頃から干潟となり、周囲は湿地帯の荒れ地となった。明治時代以降、埋め立てられた外堀のうち、溜池が最も早く1889年(明治22年)に埋め立てられた。溜池の名残りは、「首相官邸、山王日枝神社、衆議院議長公邸」の台地高まりくらい。
溜池落口
 櫓台跡側の歩道橋から、赤坂一丁目交差点を臨む。その付近に、潮の干満で海水を含んだ汐留川の水が溜池に逆流しないように設けた堰「溜池落口」があったという。
櫓台跡側の歩道橋から、赤坂一丁目交差点を臨む。その付近に、潮の干満で海水を含んだ汐留川の水が溜池に逆流しないように設けた堰「溜池落口」があったという。
 とりあえず溜池落口があったとされる位置へ。溜池と汐留川の間に位置する溜池落口は少し高まりの場所にあるため、その両脇(東西)はそれぞれ下り坂になっているそうだが、現在では、判るような判らないようなという規模である。かつて虎ノ門から溜池落口まで登り坂であったが、現在ではかなり平坦な印象がある。
とりあえず溜池落口があったとされる位置へ。溜池と汐留川の間に位置する溜池落口は少し高まりの場所にあるため、その両脇(東西)はそれぞれ下り坂になっているそうだが、現在では、判るような判らないようなという規模である。かつて虎ノ門から溜池落口まで登り坂であったが、現在ではかなり平坦な印象がある。
 古地図で溜池落口のどんぴしゃポイントを探ったら、特許庁の東の小道だそうで、延岡藩 内藤家 上屋敷跡に向かって登り坂になっている。江戸時代にこの道はない。
古地図で溜池落口のどんぴしゃポイントを探ったら、特許庁の東の小道だそうで、延岡藩 内藤家 上屋敷跡に向かって登り坂になっている。江戸時代にこの道はない。
赤坂門までの溜池
 溜池落口のすぐ先にあった大溜跡へ向かう。大溜への分岐点は特許庁前交差点のあたり。
溜池落口のすぐ先にあった大溜跡へ向かう。大溜への分岐点は特許庁前交差点のあたり。
 首都高の高架下あたりの溜池交差点。茂みに囲われている北側の高台には内閣総理大臣公邸が建ち、幕末では越後村上藩 内藤家の屋敷だったようだ。
首都高の高架下あたりの溜池交差点。茂みに囲われている北側の高台には内閣総理大臣公邸が建ち、幕末では越後村上藩 内藤家の屋敷だったようだ。
 溜池山王駅の地上あたり。首相官邸の高台も確認できる。
溜池山王駅の地上あたり。首相官邸の高台も確認できる。
 首相官邸は、峰山藩京極家および村上藩内藤家の屋敷跡にまたがっている。溜池山王駅は港区と千代田区の境界に建設されている。駅名では港区が「溜池駅」、千代田区が「山王下駅」を希望したため対立し、「溜池山王駅」で決着した経緯がある。
首相官邸は、峰山藩京極家および村上藩内藤家の屋敷跡にまたがっている。溜池山王駅は港区と千代田区の境界に建設されている。駅名では港区が「溜池駅」、千代田区が「山王下駅」を希望したため対立し、「溜池山王駅」で決着した経緯がある。
 山王日枝神社。江戸城の裏鬼門に位置している。当時は当然のことながら溜池側からの参道は無く、反対側に表参道がある。
山王日枝神社。江戸城の裏鬼門に位置している。当時は当然のことながら溜池側からの参道は無く、反対側に表参道がある。
山王日枝神社が鎮座するこの小高い丘は、夜に星がよく見えることに由来して古くから「星が丘」と呼ばれていた。そして、太田道灌が築いた「星ヶ岡城」だったと伝わっている。江戸城の支城または砦として築造されても不思議ではない。※江戸城を築城した太田道灌は1457年に江戸城を居館としたとされる。鎌倉時代の江戸氏がすでに日枝神社を創建していたが、1478年、太田道灌が改めて江戸城内に「川越日枝神社」を勧請したことが山王日枝神社の起源である。
徳川家康が江戸入封すると、紅葉山(江戸城西の丸・宮内庁の近く)に遷座し江戸城の鎮守とした。1604年の江戸城改築で隼町に遷座し、庶民が参拝できるようになった。1657年の明暦の大火により社殿が焼失したため、1659年に溜池の現在地に遷座された。
 山王日枝神社と同じく星が丘に建つ東急キャピトルタワー。太田道灌が築いた「星ヶ岡城」の本丸跡という説がある。1884年(明治17年)から1945年(昭和20年)の空襲で焼失するまでは「星ヶ岡茶寮」があった所でもある。星ヶ岡茶寮は北大路魯山人ゆかりの料亭で、上級階級の社交場であった。
山王日枝神社と同じく星が丘に建つ東急キャピトルタワー。太田道灌が築いた「星ヶ岡城」の本丸跡という説がある。1884年(明治17年)から1945年(昭和20年)の空襲で焼失するまでは「星ヶ岡茶寮」があった所でもある。星ヶ岡茶寮は北大路魯山人ゆかりの料亭で、上級階級の社交場であった。
1963年、星ヶ岡茶寮跡地に東京ヒルトンホテル(後のキャピトル東急ホテル)が開業される。2006年に老朽化で取り壊され、2010年に現在の東急キャピトルタワーに建て替えられた。東京ヒルトンホテル時代には、来日したビートルズが最上階(10階)で宿泊したことで知られる。
 山王日枝神社から見下ろした溜池跡地。
山王日枝神社から見下ろした溜池跡地。
 山王日枝神社から北に少し進んだ所、山王グランドビルとプルデンシャルタワーの間にある「新坂」。この坂は江戸時代にはないが、溜池東側の高台を感じることのできる坂である。登った先、メキシコ大使館で直角に曲がる坂道だが、そのあたりは三河刈谷藩邸があった場所である。
山王日枝神社から北に少し進んだ所、山王グランドビルとプルデンシャルタワーの間にある「新坂」。この坂は江戸時代にはないが、溜池東側の高台を感じることのできる坂である。登った先、メキシコ大使館で直角に曲がる坂道だが、そのあたりは三河刈谷藩邸があった場所である。
新坂は、明治9年(1876年)の地図にもない。1884年の参謀本部の図では現在に近い道路が確認できるので、その頃にできた新しい坂なのだろう。官庁街に向かう役人、登校を急ぐ学生の様子から「遅刻坂」とも呼ばれている。
 新坂の南隣に建つ超高層ビル、プルデンシャルタワーは2002年の開業。杜撰な防火体制による火災事故で知られるホテルニュージャパン(1960~1982年)の跡地である。事故後は、都心の好立地でありながら長らく廃墟や駐車場だった。ちなみに溜池は軟弱な地盤なため、ビル建設に膨大な対策費用がかかるらしい。ホテルニュージャパンの経営ではないが、かつて敷地の地下には高級ナイトクラブ「ニューラテンクォーター」があり、1963年に力道山が刺されて後に亡くなる事件が起きている。
新坂の南隣に建つ超高層ビル、プルデンシャルタワーは2002年の開業。杜撰な防火体制による火災事故で知られるホテルニュージャパン(1960~1982年)の跡地である。事故後は、都心の好立地でありながら長らく廃墟や駐車場だった。ちなみに溜池は軟弱な地盤なため、ビル建設に膨大な対策費用がかかるらしい。ホテルニュージャパンの経営ではないが、かつて敷地の地下には高級ナイトクラブ「ニューラテンクォーター」があり、1963年に力道山が刺されて後に亡くなる事件が起きている。
ホテルニュージャパン以前では、1936年の二・二六事件では反乱部隊が宿所としていた料亭の「幸楽」跡、江戸末期は岸和田藩邸であった。
溜池の北端~松江藩松平家 上屋敷
 溜池を越えた先に赤坂門がある。溜池の北端の東側高台には、松江藩 松平出羽守の上屋敷があった。
溜池を越えた先に赤坂門がある。溜池の北端の東側高台には、松江藩 松平出羽守の上屋敷があった。
 溜池の北端、赤坂見附交差点。赤坂門に向かって登道になっているのが地勢の名残。
溜池の北端、赤坂見附交差点。赤坂門に向かって登道になっているのが地勢の名残。
 赤坂門跡に近い歩道橋から溜池の北端を撮影。窪地である事が確認でき、溜池の北東端に位置する松江藩 松平出羽守 上屋敷(衆議院議長ならびに参議院議長の公邸)の高台も確認できる。
赤坂門跡に近い歩道橋から溜池の北端を撮影。窪地である事が確認でき、溜池の北東端に位置する松江藩 松平出羽守 上屋敷(衆議院議長ならびに参議院議長の公邸)の高台も確認できる。
ちなみに、反対の西側(この撮影している方角)に500mほど進むと、「豊川稲荷 東京別院」がある。愛知県の豊川稲荷 妙厳寺の直轄別院。大岡越前守こと大岡忠相(1677年-1752年)が自邸の下屋敷で祀っていた屋敷稲荷を起源としている。文京区目白台1丁目5の豊川稲荷神社が大岡越前守の下屋敷と伝わっており、寺院は明治20年(1887年)に現在地に移転している。
 松江藩松平家 上屋敷の石垣(衆議院議長公邸 正門側の一部だけ)。
松江藩松平家 上屋敷の石垣(衆議院議長公邸 正門側の一部だけ)。
 上屋敷の石垣ならびに、江戸城の石垣。埋め込まれているプレートには、「閑院宮邸になったあと、明治20年に皇室より東京女学館に貸与され開校した」と書かれている。その後は麹町に移り、関東大震災後は渋谷御料地に移ったとある。
上屋敷の石垣ならびに、江戸城の石垣。埋め込まれているプレートには、「閑院宮邸になったあと、明治20年に皇室より東京女学館に貸与され開校した」と書かれている。その後は麹町に移り、関東大震災後は渋谷御料地に移ったとある。
【 江戸城 探索TOP および目次 】



