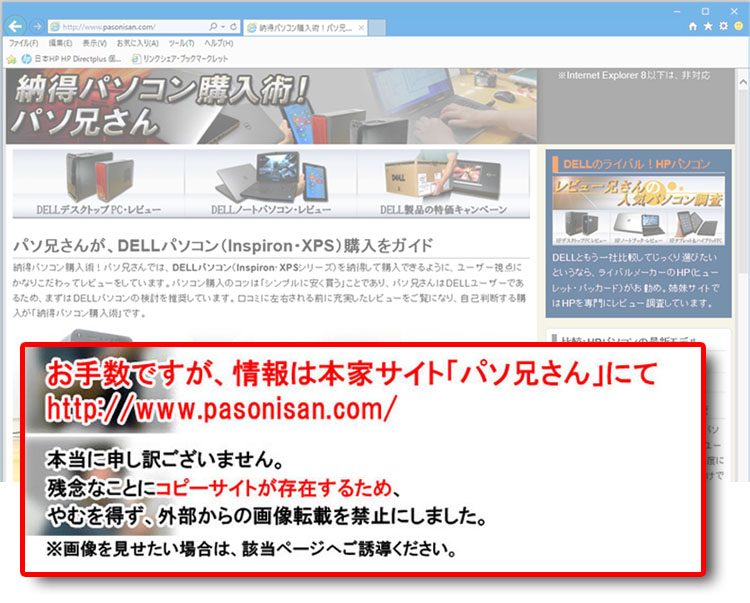

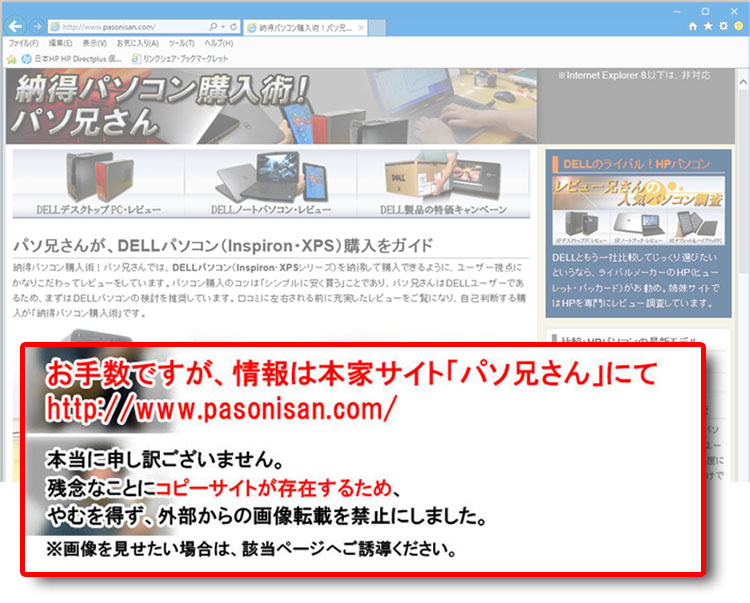
- HOME
- DELLパソコン・モバイル旅行記
- 東京都
- 江戸城(千代田区・中央区ほか)
江戸城 天然要害の隅田川と、隅田川に面した島
箱崎島
江戸城 縄張り内に配置された、隅田川(大川)河口付近の島を巡る。隅田川の西岸、茅場町側の八丁堀と新堀(後の日本橋川)の河口であった江戸中島は、徳川家康によって埋め立て地となった。それは新堀を隔てて北側を箱崎島、南側を霊岸島といった。
 田安徳川家の下屋敷があった箱崎島には現在、首都高速9号深川線と2層の隅田川大橋が架かるが江戸時代には無い橋である。また江戸時代の永代橋は箱崎島地域から架かっていたが、現在は霊岸島から架かっている(赤線:江戸時代の架橋位置、白線:現在の位置)。箱崎島と霊岸島は豊海橋(とよみばし)によって結ばれていた。現在架かっている位置は、江戸時代の時よりも河口側に寄っている。
田安徳川家の下屋敷があった箱崎島には現在、首都高速9号深川線と2層の隅田川大橋が架かるが江戸時代には無い橋である。また江戸時代の永代橋は箱崎島地域から架かっていたが、現在は霊岸島から架かっている(赤線:江戸時代の架橋位置、白線:現在の位置)。箱崎島と霊岸島は豊海橋(とよみばし)によって結ばれていた。現在架かっている位置は、江戸時代の時よりも河口側に寄っている。
霊岸島は亀島川と新堀(日本橋川)に囲われた島で、北側の掘割は新堀と呼ばれた。福井藩・松平越前守の中屋敷があり、屋敷を囲む「コの字型」の小規模な堀は越前堀と呼ばれた。なお、三代藩主の松平忠昌が霊岸島に屋敷を拝領した当初は下屋敷であった可能性があるという。1660年に豪商・河村瑞賢が開削したとされる新川は、亀島川と隅田川を結んでおりこの一帯では酒問屋が軒を連ねていた。
箱崎島の堀と橋
江戸時代の箱崎島では「隅田川、箱崎川、新堀」に囲まれており、北部には、御三卿のひとつ、田安徳川家の箱崎下屋敷があった。箱崎島における現在の町名は「日本橋箱崎町」であるが、この地域は富岡八幡宮の氏子が多い。地名の由来は定かではないが、筥崎宮(福岡県福岡市東区箱崎)との関連性や、田安徳川家の下屋敷にあった箱崎池(箱池)が指摘されている。
 江戸時代、箱崎島には5つの橋(赤文字)が架けられていた。現在では永代橋が霊岸島のほうへ移設。霊岸島を結ぶ橋として、現在では少し位置が変わっているが湊橋と豊海橋が架かっている。
江戸時代、箱崎島には5つの橋(赤文字)が架けられていた。現在では永代橋が霊岸島のほうへ移設。霊岸島を結ぶ橋として、現在では少し位置が変わっているが湊橋と豊海橋が架かっている。
もちろん江戸時代に、隅田川大橋や首都高速9号線は架かっていない。昭和46年、首都高速6号線の下にあった箱崎川が埋め立てられ、永久橋、崩橋(後に箱崎橋)が消滅している。
ちなみに開削によって、新堀・八丁堀の上流にあたる堀留(飯田川)が神田川とつながってからは、新堀・八丁堀は「日本橋川」と呼ばれる。また、この八丁堀は後に桜川と呼ばれる堀とは別なので留意されたし。
箱崎川
 箱崎島の西側を流れていた箱崎川跡。箱崎JCTの下あたり。昭和46年までは箱崎川があったが埋め立てられた。ここから真っすぐ伸びているのが首都高速9号線でこの先、隅田川大橋と二層となる。
箱崎島の西側を流れていた箱崎川跡。箱崎JCTの下あたり。昭和46年までは箱崎川があったが埋め立てられた。ここから真っすぐ伸びているのが首都高速9号線でこの先、隅田川大橋と二層となる。
 首都高速9号線沿いの道。かつて箱崎川が流れていた場所である。
首都高速9号線沿いの道。かつて箱崎川が流れていた場所である。
 陸上で首都高速9号線と隅田川大橋が重なっている場所で、ここが「田安徳川家の箱崎下屋敷跡」があったところ。
陸上で首都高速9号線と隅田川大橋が重なっている場所で、ここが「田安徳川家の箱崎下屋敷跡」があったところ。
永久橋 跡
 箱崎川にかかる橋として、元禄年間(1688年から1704年)に架橋された「永久橋」があった。今は首都高速6号線のガード下(箱崎川の位置)で駐車場になっている。直角に曲がる道にその名残がある。右側にはやたらと入口の小さい永久稲荷神社が鎮座している。
箱崎川にかかる橋として、元禄年間(1688年から1704年)に架橋された「永久橋」があった。今は首都高速6号線のガード下(箱崎川の位置)で駐車場になっている。直角に曲がる道にその名残がある。右側にはやたらと入口の小さい永久稲荷神社が鎮座している。
 これが永久稲荷神社・・・・。一本の石柱は鳥居だろうか、参道に家が建ってしまったようだ。創建年代は不詳だが、箱崎町河岸の産土神で崇敬を受けてきたという。
これが永久稲荷神社・・・・。一本の石柱は鳥居だろうか、参道に家が建ってしまったようだ。創建年代は不詳だが、箱崎町河岸の産土神で崇敬を受けてきたという。
崩橋 跡
この撮影ポイントの箱崎川第一公園あたりに、箱崎川に架かる「崩橋」があったようだ。後に箱崎橋と呼ばれるが、昭和46年の埋め立てで箱崎川が消えると橋も消えた。そしてここは箱崎川、亀島川、新堀、八丁堀の合流点。
 目の前、亀島川の上流には日本橋水門が設置されている。
目の前、亀島川の上流には日本橋水門が設置されている。
 同ポイントから、新堀と湊橋を眺める。
同ポイントから、新堀と湊橋を眺める。
 同ポイントから、八丁堀(日本橋川)を眺める。頭上では首都高速6号線がここで日本橋川に沿ってカーブする。
同ポイントから、八丁堀(日本橋川)を眺める。頭上では首都高速6号線がここで日本橋川に沿ってカーブする。
湊橋
 江戸時代と大体近い位置に架かる湊橋。新堀の西側で、箱崎島と霊岸島を結ぶ橋である。名称は江戸湊に因んでいる。
江戸時代と大体近い位置に架かる湊橋。新堀の西側で、箱崎島と霊岸島を結ぶ橋である。名称は江戸湊に因んでいる。
 湊橋から八丁堀(日本橋川)を見渡す。箱崎川跡に沿っている首都高速6号線がここで日本橋川に沿って通るようになる。この先、江戸橋で首都高速1号と首都高速都心環状線と交差する。
湊橋から八丁堀(日本橋川)を見渡す。箱崎川跡に沿っている首都高速6号線がここで日本橋川に沿って通るようになる。この先、江戸橋で首都高速1号と首都高速都心環状線と交差する。
 今度は隅田川方面を臨むと、新堀(日本橋川)とその河口の豊海橋が見える。
今度は隅田川方面を臨むと、新堀(日本橋川)とその河口の豊海橋が見える。
豊海橋
 対岸の霊岸島を結ぶ豊海橋。江戸時代ではもう少し河口側に架橋されていたようだ。また、永代橋は現在、この向かいの霊岸島から架かっているが、江戸時代はこの撮影ポイントあたりの箱崎島から架かっていた。高尾稲荷神社で祀られている遊女・二代目高尾太夫の遺体はこの辺で引き上げられたようだ。
対岸の霊岸島を結ぶ豊海橋。江戸時代ではもう少し河口側に架橋されていたようだ。また、永代橋は現在、この向かいの霊岸島から架かっているが、江戸時代はこの撮影ポイントあたりの箱崎島から架かっていた。高尾稲荷神社で祀られている遊女・二代目高尾太夫の遺体はこの辺で引き上げられたようだ。
 豊海橋から20mほど離れたところに「日本銀行創業の地」の碑が建っている。江戸時代であれば永代橋の西詰の位置であるが、この碑には「明治15年10月、この地で日本銀行は開業した。明治29年に日本橋本石町に移転した」と記載されている。ちなみに、江戸時代の高尾稲荷神社は日本銀行創業の地にあった。
豊海橋から20mほど離れたところに「日本銀行創業の地」の碑が建っている。江戸時代であれば永代橋の西詰の位置であるが、この碑には「明治15年10月、この地で日本銀行は開業した。明治29年に日本橋本石町に移転した」と記載されている。ちなみに、江戸時代の高尾稲荷神社は日本銀行創業の地にあった。
高尾稲荷神社
 新堀の北岸に高尾稲荷神社が鎮座している。前述の通り、元は江戸時代に架かっていた永代橋の西詰にあったが、80mほど西にずれた現在の位置に移転している。この神社では江戸時代、花街吉原の三浦屋で受け継がれた最高位「太夫」の遊女、二代目高尾太夫を祀っている。全国でも珍しく実物の頭蓋骨を御神体として安置している。社殿は昭和20年3月の空襲で焼失したが再建され、昭和51年、令和4年の二度にわたる建て直しが行われた。
新堀の北岸に高尾稲荷神社が鎮座している。前述の通り、元は江戸時代に架かっていた永代橋の西詰にあったが、80mほど西にずれた現在の位置に移転している。この神社では江戸時代、花街吉原の三浦屋で受け継がれた最高位「太夫」の遊女、二代目高尾太夫を祀っている。全国でも珍しく実物の頭蓋骨を御神体として安置している。社殿は昭和20年3月の空襲で焼失したが再建され、昭和51年、令和4年の二度にわたる建て直しが行われた。
 創建の言い伝えはこうある。仙台藩主・伊達綱宗が大金三千両を積んで高尾太夫を身請けしたが、綱宗の意には従わなかった。1659年12月、綱宗の怒りを買い、隅田川の三又の船中にて吊るし切りにされ川に捨てられた。遺体が北新堀河岸(現在の豊海橋付近)に流れ着き、当地に庵を構えていた僧侶がその遺体を手厚く葬ったという。ただし、この話の真偽には諸説ある。
創建の言い伝えはこうある。仙台藩主・伊達綱宗が大金三千両を積んで高尾太夫を身請けしたが、綱宗の意には従わなかった。1659年12月、綱宗の怒りを買い、隅田川の三又の船中にて吊るし切りにされ川に捨てられた。遺体が北新堀河岸(現在の豊海橋付近)に流れ着き、当地に庵を構えていた僧侶がその遺体を手厚く葬ったという。ただし、この話の真偽には諸説ある。
※隅田川、小名木川、箱崎川を三叉(みつまた)と言った。現在の日本橋中洲付近である。
 高尾稲荷神社から北120mあたりにある中央区立箱崎公園。古地図を見ると、三河吉田藩・下総古河藩の屋敷跡の位置にある。公園内には昭和12年、吉田松陰をリスペクトする小学生の遺言を実現し建てられた「吉田松陰の銅像」が置かれている。平成22年にここへ移設したとある。
高尾稲荷神社から北120mあたりにある中央区立箱崎公園。古地図を見ると、三河吉田藩・下総古河藩の屋敷跡の位置にある。公園内には昭和12年、吉田松陰をリスペクトする小学生の遺言を実現し建てられた「吉田松陰の銅像」が置かれている。平成22年にここへ移設したとある。
永代橋
 現在では対岸の霊岸島に永代橋が架けられているが、江戸時代に架かっていた場所は箱崎島である。ちょうどこの説明板が置かれている位置である。永代橋は隅田川に架橋された5つの橋のうち4番目となる。※千住大橋(1594年)、両国橋(1659年 or 1661年)、新大橋(1693年)、永代橋(1698年)、吾妻橋(1774年)
現在では対岸の霊岸島に永代橋が架けられているが、江戸時代に架かっていた場所は箱崎島である。ちょうどこの説明板が置かれている位置である。永代橋は隅田川に架橋された5つの橋のうち4番目となる。※千住大橋(1594年)、両国橋(1659年 or 1661年)、新大橋(1693年)、永代橋(1698年)、吾妻橋(1774年)
諸説あるが、5代将軍 徳川綱吉の50歳を祝う記念事業として架けられた。上野寛永寺の根本中堂造営で余った木材を使ったとされ、普請は関東郡代(浅草橋門となりに役宅あり)の伊奈忠順。名称は永代島(現在の江東区富岡)にちなむ。「永代寺につながる橋、江戸幕府が末永く代々続くように願掛けした」などという話もあるが、「永代島につながる橋」が正しいと思われる。
 歌川広重が描いた東都名所永代橋全図。1702年、赤穂浪士が吉良上野介屋敷へ討ち入りしたが、吉良上野介の首を掲げて泉岳寺へ向かった際に永代橋を渡っている。1807年、深川富岡八幡宮で祭礼が行われた際、押し寄せる群衆の重みに橋が耐え切れず、落橋事故が起きている。
歌川広重が描いた東都名所永代橋全図。1702年、赤穂浪士が吉良上野介屋敷へ討ち入りしたが、吉良上野介の首を掲げて泉岳寺へ向かった際に永代橋を渡っている。1807年、深川富岡八幡宮で祭礼が行われた際、押し寄せる群衆の重みに橋が耐え切れず、落橋事故が起きている。
 西詰めに旗が立つ高尾稲荷社江戸時代に架かっていた永代橋の近くに高尾稲荷神社(遊女高尾太夫を祀る神社)がある。
西詰めに旗が立つ高尾稲荷社江戸時代に架かっていた永代橋の近くに高尾稲荷神社(遊女高尾太夫を祀る神社)がある。
永代橋が現在の場所に変えられたのは1897年の事で、道路橋としては初めてとなる鋼鉄橋に生まれ変わった。現在の永代橋は1926年(大正15年)に震災復興事業により架けられたもので「帝都東京の門」と言われた。永代橋のデザインは柳橋でも採用されている。
【 江戸城 探索TOP および目次 】



