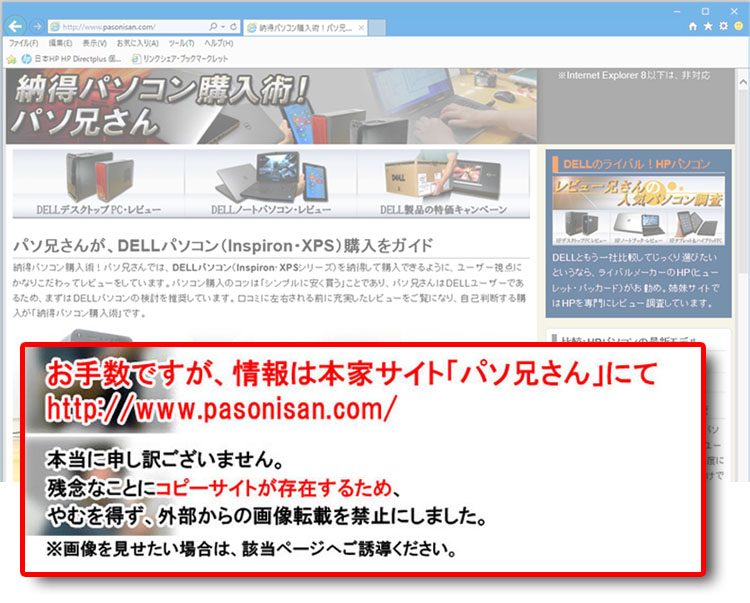

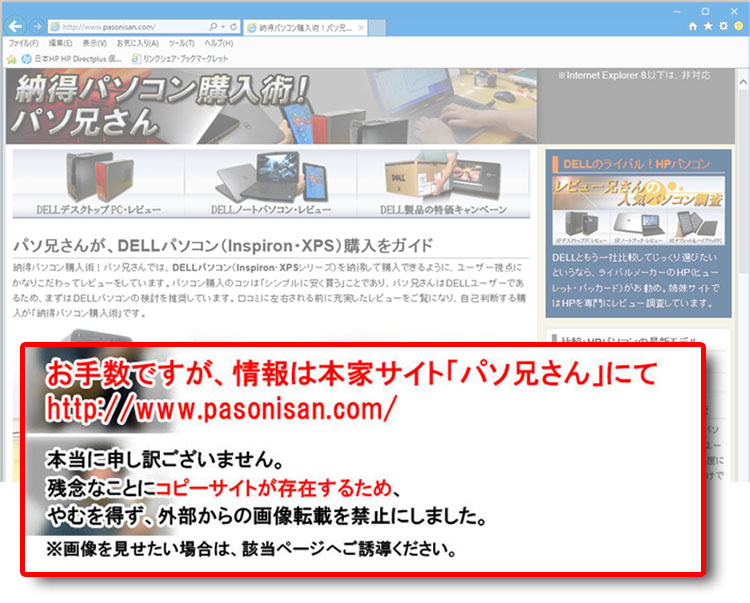
- HOME
- DELLパソコン・モバイル旅行記
- 東京都
- 江戸城(千代田区・中央区ほか)
江戸城 天然要害の隅田川と、隅田川に面した島
佃島
江戸幕府より隅田川河口部の干潟を拝領した漁民らが、1644年、石垣で周囲を固め100間(180m)四方の島を築造したのが佃島という。1766年の「佃島由緒書」にも記されている。
1582年、信長の同盟者であった徳川家康は堺に投宿していたが本能寺の変が伝えられ、三河国への帰還をめざした(伊賀越え)。大阪へ向かうが川が増水し途方にくれた。その時に摂津国西成郡佃村(大阪市西淀川区)の庄屋(漁師とも)である孫右衛門が多数の舟を出して一行を助けた。孫右衛門には後に森の姓を与えている。
1590年に家康が江戸入封。老中の安藤対馬守を通じて森孫右衛門に出府を促した。家康のお供をすることになり、佃村の隣の大和田村から腕の立つ漁師33名を連れてきたとされる。1613年、「網引御免証文」が与えられたので漁民たちは自由に漁業を営み、 年貢が免除されていた。佃島の漁民が保存食として佃煮を作り、小魚がたくさん獲れた時や余った時に佃煮を売りに出して広まったとされる。いずれにしても佃島や佃煮の起源には諸説ある。
 佃島は2つの小島から成り、佃小橋で結ばれている。人足寄場であった北の石川島とは橋で結ばれてはいない(現在のような住吉小橋は無い)。また石川島と佃島はそれぞれ別の場所から渡し(佃之渡し / 寄場之渡し)が出ており、隅田川の左岸(汐見地蔵尊・湊第一児童遊園)に船で渡っていた。
佃島は2つの小島から成り、佃小橋で結ばれている。人足寄場であった北の石川島とは橋で結ばれてはいない(現在のような住吉小橋は無い)。また石川島と佃島はそれぞれ別の場所から渡し(佃之渡し / 寄場之渡し)が出ており、隅田川の左岸(汐見地蔵尊・湊第一児童遊園)に船で渡っていた。
古地図にも載っていたが、佃煮屋の天安本店(天保8年(1837)創業)と、佃源田中屋は江戸時代から同所で製造販売を続けている。そのほか近くには安政6年(1859年)創業の「つくだに丸久」がある。
 佃公園にあった佃島MAP(江戸末期)では、3つの小島から成っているが、だいたいの古地図では2つの小島になっているが詳細不明。ちなみに、佃島の渡し船場はもう少し南側であった。
佃公園にあった佃島MAP(江戸末期)では、3つの小島から成っているが、だいたいの古地図では2つの小島になっているが詳細不明。ちなみに、佃島の渡し船場はもう少し南側であった。
 石川島と佃島を隔てている、佃島の北の堀(佃堀)。
石川島と佃島を隔てている、佃島の北の堀(佃堀)。
 隅田川と佃堀の境界線、住吉水門。
隅田川と佃堀の境界線、住吉水門。
 佃島の東の堀(佃小橋の北側)
佃島の東の堀(佃小橋の北側)
 佃小橋の北側に佃住吉講(住吉神社の祭礼を運営する団体)による注意書き。1798年、江戸幕府により建立を許された大幟が埋設されている場所とのこと。神輿の海中渡御と船渡御が行われる際、高さ20mに及ぶ6本の大幟が佃島に立ったといい、歌川広重『名所江戸百景』の「佃しま住吉乃祭」でも描かれている。江戸城からも大幟が見えたといわれる。
佃小橋の北側に佃住吉講(住吉神社の祭礼を運営する団体)による注意書き。1798年、江戸幕府により建立を許された大幟が埋設されている場所とのこと。神輿の海中渡御と船渡御が行われる際、高さ20mに及ぶ6本の大幟が佃島に立ったといい、歌川広重『名所江戸百景』の「佃しま住吉乃祭」でも描かれている。江戸城からも大幟が見えたといわれる。
 東の小島と結んでいた佃小橋。ただし、現在は埋め立てにより小島になっていない。
東の小島と結んでいた佃小橋。ただし、現在は埋め立てにより小島になっていない。
 佃島の東の堀(佃小橋の南側)
佃島の東の堀(佃小橋の南側)
 佃公園(佃堀広場)が佃島の最南端。新月陸橋(佃大橋通り)以南は明治時代以降の埋め立て地である。
佃公園(佃堀広場)が佃島の最南端。新月陸橋(佃大橋通り)以南は明治時代以降の埋め立て地である。
 かつての佃島の最南端から石川島方面を見る。都市化の落差が見ものとなっている。
かつての佃島の最南端から石川島方面を見る。都市化の落差が見ものとなっている。
 住吉神社。1590年に家康が江戸入封すると、「伊賀越え」で脱出の手助けをした摂津国西成郡佃村(大阪市西淀川区)の森孫右衛門および、佃村の隣の大和田村から腕の立つ漁師33名を連れてきたとされるが、この折、摂津国西成郡佃村の住吉神社(現・田蓑神社)を勧請している。この時、神主の平岡好次が江戸に移った。
住吉神社。1590年に家康が江戸入封すると、「伊賀越え」で脱出の手助けをした摂津国西成郡佃村(大阪市西淀川区)の森孫右衛門および、佃村の隣の大和田村から腕の立つ漁師33名を連れてきたとされるが、この折、摂津国西成郡佃村の住吉神社(現・田蓑神社)を勧請している。この時、神主の平岡好次が江戸に移った。
 森稲荷神社。摂津国佃村から移り住んだ森一族が、邸宅内で祀っていた稲荷神を起源とする神社。
森稲荷神社。摂津国佃村から移り住んだ森一族が、邸宅内で祀っていた稲荷神を起源とする神社。
 於咲稲荷神社(おさき)と、波除稲荷神社(なみよけ)。鳥居が共用のため1つの神社に見えるが、境内では社殿が2棟並んて鎮座している。向かい側には佃天台地蔵尊があり、そこの大銀杏あたりが佃島の最東端であった。
於咲稲荷神社(おさき)と、波除稲荷神社(なみよけ)。鳥居が共用のため1つの神社に見えるが、境内では社殿が2棟並んて鎮座している。向かい側には佃天台地蔵尊があり、そこの大銀杏あたりが佃島の最東端であった。
佃島の以南、拡張および東京湾の澪浚(みおさらい)目的で、海底の土砂(浚渫土)を利用し埋め立てが行われた。船舶の航路を確保するため、底面をさらう浚渫(しゅんせつ)工事であった。明治中期から昭和初期にかけて行われ、「月島、勝どき、晴海」が築造されている。1963年(昭和38年)には「豊海町」の埋め立て地が完成。
【 江戸城 探索TOP および目次 】



