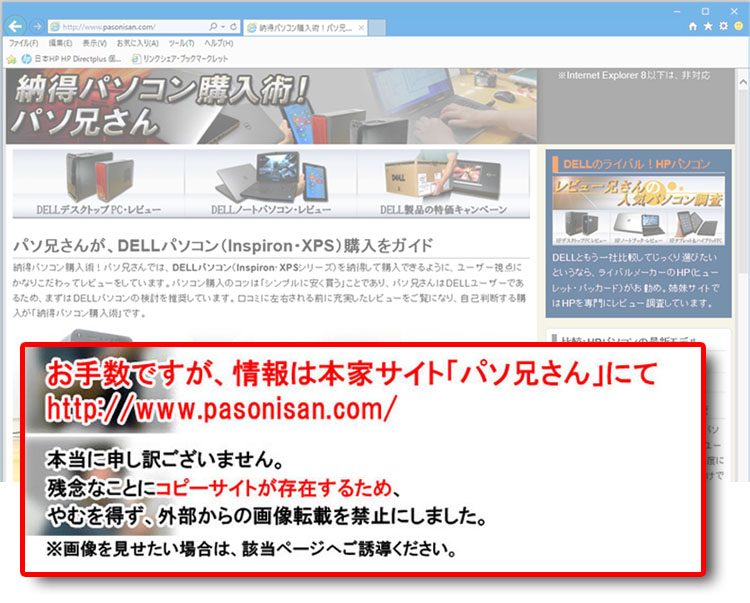

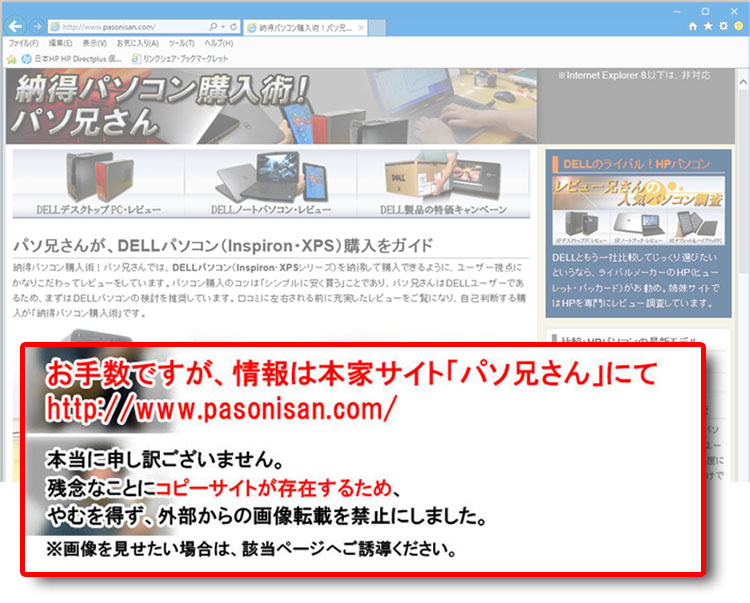
- HOME
- DELLパソコン・モバイル旅行記
- 東京都
- 江戸城(千代田区・中央区ほか)
江戸城 天然要害の隅田川と、隅田川に面した島
霊岸島
隅田川の西岸、茅場町側の八丁堀と新堀(後の日本橋川)の河口であった江戸中島は埋め立て地となったが、新堀を隔てて北側を箱崎島、南側を霊岸島といった。
 霊岸島は新堀(日本橋川)・亀島川に囲まれた島で、名称はかつて鎮座していた霊巌寺に因む。表記は「霊巌島」でもよいのだが、もっぱら霊岸島(れいがんじま)の表記が多いのでそうする。
霊岸島は新堀(日本橋川)・亀島川に囲まれた島で、名称はかつて鎮座していた霊巌寺に因む。表記は「霊巌島」でもよいのだが、もっぱら霊岸島(れいがんじま)の表記が多いのでそうする。
霊岸島北側の掘割は新堀と呼ばれた。霊岸島には福井藩・松平越前守の中屋敷があり、屋敷を囲む「コの字型」の小規模な堀は越前堀と呼ばれた。なお、三代藩主の松平忠昌が霊岸島に屋敷を拝領した当初は下屋敷であった可能性があるという。
箱崎島を結ぶ橋として湊橋と豊海橋が架かっている(これは箱崎島の項で紹介)。霊岸島を囲む1kmの亀島川に架けられた橋は、霊岸橋、亀島橋、高橋の3つで、亀島橋以外、現在では架橋の位置が少し変わっている。ほか亀島川に架けられた橋には、南高橋、新亀島橋があるが江戸時代には無い。また現在では永代橋が霊岸島に架けられているが、江戸時代は箱崎島に架けられていた。
 1632年「武州豊嶋郡江戸庄図」に描かれている霊巌寺。福井藩・松平越前守屋敷の北側に隣接していたようだ。この頃はまだ新川が開削されていない。
1632年「武州豊嶋郡江戸庄図」に描かれている霊巌寺。福井藩・松平越前守屋敷の北側に隣接していたようだ。この頃はまだ新川が開削されていない。
後に霊岸島(霊巌島)と呼ばれるこの埋め立て地の小島に、1624年、霊巌和尚が霊巌寺を開山した。霊巌和尚は駿河国沼津に生まれ下総国生実の大巌寺で修行を積んだ人物で、後に浄土宗総本山知恩院の住職となっている。霊巌寺は30年余りこの地に鎮座していたが、明暦の大火(1657年)で焼失し深川へ移転した。跡地は町人地になった。そして昭和46年には町名の変更で霊巌寺の地名も消えた。
福井藩・松平越前守屋敷跡(中屋敷)
 松平越前守屋敷地は三方が「越前堀」と呼ばれる入堀に囲まれていた。入堀は護岸の石積みで、20~30mほどの規模があり運河として利用されていたという。明治以降になると堀は徐々に埋められていき、関東大震災(1923年)後は大部分が埋められ戦後には完全消滅した。越前堀という町名も改められ「新川」となった。
松平越前守屋敷地は三方が「越前堀」と呼ばれる入堀に囲まれていた。入堀は護岸の石積みで、20~30mほどの規模があり運河として利用されていたという。明治以降になると堀は徐々に埋められていき、関東大震災(1923年)後は大部分が埋められ戦後には完全消滅した。越前堀という町名も改められ「新川」となった。
 越前堀児童公園の一部が福井藩・松平越前守屋敷跡。史跡としては何も残っていない。往時を偲ぶ「越前堀」の名はこの公園のみに引き継がれている。しかし、この公園が松平越前守屋敷跡に掛っている部分は1/3ほどしかなくて中途半端である。
越前堀児童公園の一部が福井藩・松平越前守屋敷跡。史跡としては何も残っていない。往時を偲ぶ「越前堀」の名はこの公園のみに引き継がれている。しかし、この公園が松平越前守屋敷跡に掛っている部分は1/3ほどしかなくて中途半端である。
 越前堀児童公園の様子
越前堀児童公園の様子
 新川2丁目で出土した、越前堀の護岸に用いられていた石垣石が越前堀児童公園で展示されている。出土した場所の地図は上記のとおりで、越前堀の南西部(八重洲通り-463号線)にあった石垣石のようだ。出土場所のピンポイントをGoogleMAPで確認したところ、住宅マンションの「グレースレジデンス東京」が建っている場所で、古地図と照らし合わせると、松平越前守屋敷の玄関口であった。そこには越前堀に橋が架けられていた。
新川2丁目で出土した、越前堀の護岸に用いられていた石垣石が越前堀児童公園で展示されている。出土した場所の地図は上記のとおりで、越前堀の南西部(八重洲通り-463号線)にあった石垣石のようだ。出土場所のピンポイントをGoogleMAPで確認したところ、住宅マンションの「グレースレジデンス東京」が建っている場所で、古地図と照らし合わせると、松平越前守屋敷の玄関口であった。そこには越前堀に橋が架けられていた。
 中央大橋から北西に通る八重洲通り(463号線)が南西部の越前堀とされる。
中央大橋から北西に通る八重洲通り(463号線)が南西部の越前堀とされる。
 石垣石が出土したグレースレジデンス東京の向かいの八重洲通り(463号線)。説明板などないが、ここに松平越前守屋敷の玄関口を結ぶ橋があったようだ。
石垣石が出土したグレースレジデンス東京の向かいの八重洲通り(463号線)。説明板などないが、ここに松平越前守屋敷の玄関口を結ぶ橋があったようだ。
松平越前守屋敷に関して見るべき遺構は何も無い。ついで程度に屋敷地跡に位置する「於岩稲荷田宮神社」と、小田原の武家屋敷から移植されたカヤを後ほど見て回る。もちろん、跡地にあるということ以外は松平越前守屋敷と関係はない。
於岩稲荷田宮神社
 松平越前守屋敷跡地に鎮座する、新川 於岩稲荷田宮神社(おいわいなりたみやじんじゃ)は四谷怪談のお岩を祀っている神社。元は新宿区左門町の於岩稲荷田宮神社(田宮家跡地)であるが、1879年(明治12年)に火災に遭い、この地(東京都中央区)に移転した。この近くに芝居小屋があり、四谷怪談を上演する歌舞伎役者らが当地に移転させたといわれる。1952年(昭和27年)に旧地新宿の於岩稲荷田宮神社が再興されたため、現在は新宿区と中央区に2つ存在している。新川 於岩稲荷田宮神社は戦災で焼失したがこれも再建されている。
松平越前守屋敷跡地に鎮座する、新川 於岩稲荷田宮神社(おいわいなりたみやじんじゃ)は四谷怪談のお岩を祀っている神社。元は新宿区左門町の於岩稲荷田宮神社(田宮家跡地)であるが、1879年(明治12年)に火災に遭い、この地(東京都中央区)に移転した。この近くに芝居小屋があり、四谷怪談を上演する歌舞伎役者らが当地に移転させたといわれる。1952年(昭和27年)に旧地新宿の於岩稲荷田宮神社が再興されたため、現在は新宿区と中央区に2つ存在している。新川 於岩稲荷田宮神社は戦災で焼失したがこれも再建されている。
於岩稲荷田宮神社の創建年代は不明であるが、四谷左門町に屋敷を構えていた田宮家の屋敷神(稲荷神の祠)を起源としている。左門町は、『四谷怪談』に登場する田宮伊右衛門(婿養子)とその妻「お岩」が居住していた地であるが、史実のお岩は物語と違って夫婦仲睦まじく健気な女性であったといわれている。左門町という地名は、お岩の父・田宮又左衛門がその由来だろう。
『東海道四谷怪談』の原典とされた『四谷雑談集』では、失踪したお岩の祟りによって伊右衛門の関係者が葬られ、田宮家滅亡後、跡地に奇怪な事件が起きるが於岩稲荷を創建して追善仏事を行ったところ収まったというストーリー。実際の田宮家は続いており、関係者の女性が失踪した事件をモデルにしたという考察もある。さらにアレンジが加わった『東海道四谷怪談』では舞台が豊島区雑司が谷となっており、なぜ東海道が付くのか全く持って不明である。
小田原城主・大久保氏の時代のカヤ
 新川1丁目のオフィスビル・東京ダイヤビル1号館。敷地にあるカヤが何か関係ありそうと近づいてみたが、松平越前守屋敷跡地にあるというだけで関係ないものだった。説明板によると、西海子小路(小田原市南町)の武家屋敷より移植したもので、江戸時代後期・小田原城主・大久保氏の時代のカヤとのこと。
新川1丁目のオフィスビル・東京ダイヤビル1号館。敷地にあるカヤが何か関係ありそうと近づいてみたが、松平越前守屋敷跡地にあるというだけで関係ないものだった。説明板によると、西海子小路(小田原市南町)の武家屋敷より移植したもので、江戸時代後期・小田原城主・大久保氏の時代のカヤとのこと。
霊岸橋(永代通り)
 日本橋茅場町と新川地区(霊岸島)を結ぶ、亀島川に架かる霊岸橋。現在では江戸時代と架橋の位置が少し変わっており、北30mほどのところにあった。現在の霊岸橋では「永代通り」として江戸城大手門に直通しているが、江戸時代にはそのような道は無い。
日本橋茅場町と新川地区(霊岸島)を結ぶ、亀島川に架かる霊岸橋。現在では江戸時代と架橋の位置が少し変わっており、北30mほどのところにあった。現在の霊岸橋では「永代通り」として江戸城大手門に直通しているが、江戸時代にはそのような道は無い。
 亀島川の上流。日本橋川(新堀と八丁堀)との合流点手前に日本橋水門がある。江戸時代に架けられていた霊岸橋の位置に近い。一方、亀島川の河口には亀島川水門があり、高潮発生時には洪水を防ぐためこの2つの門で亀島川を完全に閉め切ることができる。
亀島川の上流。日本橋川(新堀と八丁堀)との合流点手前に日本橋水門がある。江戸時代に架けられていた霊岸橋の位置に近い。一方、亀島川の河口には亀島川水門があり、高潮発生時には洪水を防ぐためこの2つの門で亀島川を完全に閉め切ることができる。
亀島橋(八重洲通り)
 江戸時代とほぼ同じ位置にある亀島橋。新川地区(霊岸島)を結ぶ橋で、亀島川が直角に折れ曲がる位置に架けられている。町触に橋普請の記載があり、1699年頃に亀島橋は架けられたとされる。関東大震災(1923年)に倒壊、1929年(昭和4年)に鋼上路アーチ橋が架けられるが戦時中に物資として高欄が供出された。現在の亀島橋は八重洲通りにあり東京駅八重洲口に直通するが、江戸時代にはそのような道は無い。
江戸時代とほぼ同じ位置にある亀島橋。新川地区(霊岸島)を結ぶ橋で、亀島川が直角に折れ曲がる位置に架けられている。町触に橋普請の記載があり、1699年頃に亀島橋は架けられたとされる。関東大震災(1923年)に倒壊、1929年(昭和4年)に鋼上路アーチ橋が架けられるが戦時中に物資として高欄が供出された。現在の亀島橋は八重洲通りにあり東京駅八重洲口に直通するが、江戸時代にはそのような道は無い。
江戸時代の八丁堀(現・日本橋川)では町奉行配下の与力同心の組屋敷があり、新川では酒屋問屋を中心とした問屋が多かった。そのため、新川と交わる亀島川は物資を運ぶ船の往来が多く栄えていた。
 亀島橋から観た亀島川下流方面。高橋および石川島(現・中央区佃)のタワー群が見える。亀島川の名称由来だが、瓶(カメ)を売るものが多くいたため「亀島」と呼ばれた説と、亀に似た小島があったからという説もある。
亀島橋から観た亀島川下流方面。高橋および石川島(現・中央区佃)のタワー群が見える。亀島川の名称由来だが、瓶(カメ)を売るものが多くいたため「亀島」と呼ばれた説と、亀に似た小島があったからという説もある。
 亀島橋から観た日本橋川に合流する亀島川上流方面。手前に新亀島橋が見えるが江戸時代には架けられていない橋である。
亀島橋から観た日本橋川に合流する亀島川上流方面。手前に新亀島橋が見えるが江戸時代には架けられていない橋である。
 今度は(江戸時代にはない)新亀島橋から観た日本橋川に合流する亀島川上流方面。霊岸橋と日本橋水門が見える。新亀島橋が初めて架けられたのは明治15年で木橋だったと記録されている。関東大震災後、鋼桁の近代橋に架けかえられた。
今度は(江戸時代にはない)新亀島橋から観た日本橋川に合流する亀島川上流方面。霊岸橋と日本橋水門が見える。新亀島橋が初めて架けられたのは明治15年で木橋だったと記録されている。関東大震災後、鋼桁の近代橋に架けかえられた。
高橋(鍛冶橋通り)
 新川地区(霊岸島)を結ぶ、現在の高橋。江戸時代では南30mほどのところに架橋されていた。
新川地区(霊岸島)を結ぶ、現在の高橋。江戸時代では南30mほどのところに架橋されていた。
 高橋から観た亀島川の上流方面。奥でかろうじて亀島橋が見えるが、そこから直角に水路が曲がっている。
高橋から観た亀島川の上流方面。奥でかろうじて亀島橋が見えるが、そこから直角に水路が曲がっている。
 高橋から観た、亀島川河口側。江戸時代にはなかった南高橋が架けられており、河口には亀島川水門が見える。さらに奥には石川島(現・中央区佃)のビル群。
高橋から観た、亀島川河口側。江戸時代にはなかった南高橋が架けられており、河口には亀島川水門が見える。さらに奥には石川島(現・中央区佃)のビル群。
 高橋から亀島川の河口へやや進むと少し窪んだ護岸が目に留まるが、これは亀島川から分流する八丁堀(桜川)の名残り。後に日本橋川の一部となる八丁堀とは別の運河である。八丁堀(桜川)は、楓川と亀島川を連絡する運河として1612年に開削されたといわれる。 1960年代、段階的に埋立が始まり完全に姿を消した。
高橋から亀島川の河口へやや進むと少し窪んだ護岸が目に留まるが、これは亀島川から分流する八丁堀(桜川)の名残り。後に日本橋川の一部となる八丁堀とは別の運河である。八丁堀(桜川)は、楓川と亀島川を連絡する運河として1612年に開削されたといわれる。 1960年代、段階的に埋立が始まり完全に姿を消した。
新川
 新川の河口付近跡地に新川公園があり「新川の碑」が建立されている。1660年に豪商・河村瑞賢が開削したとされる新川は、新川1丁目の3番から4番の間に存在していた運河で亀島川と隅田川を結んでいた。上流の西から、一の橋、二の橋、三の橋、と3つの橋が架けられた。この一帯では酒問屋が軒を連ねていた。昭和23年に埋め立てられ消滅した。
新川の河口付近跡地に新川公園があり「新川の碑」が建立されている。1660年に豪商・河村瑞賢が開削したとされる新川は、新川1丁目の3番から4番の間に存在していた運河で亀島川と隅田川を結んでいた。上流の西から、一の橋、二の橋、三の橋、と3つの橋が架けられた。この一帯では酒問屋が軒を連ねていた。昭和23年に埋め立てられ消滅した。
※河村瑞賢(1618-1699年)は伊勢出身の土木作業を営む商人で、江戸の治水や海運の功労者。船で江戸へ運ばれる物資を荷揚げするために新川を開削したという。一の橋の北詰に河村瑞賢の屋敷があったという。
 新川公園の北隣、新川一丁目東町会事務所の所にかつて渡海稲荷神社(わたみいなりじんじゃ)が鎮座しており、1704年に創建されたという。
新川公園の北隣、新川一丁目東町会事務所の所にかつて渡海稲荷神社(わたみいなりじんじゃ)が鎮座しており、1704年に創建されたという。
 新川公園から西へ向かい、その跡地を歩く。船着き場であった新川公園のすぐ西には三ノ橋があった。
新川公園から西へ向かい、その跡地を歩く。船着き場であった新川公園のすぐ西には三ノ橋があった。
 鍛冶橋通りに交差するが、この細い路地が新川の流路。この路地は途中でビルに阻まれ中断されるがそのあたりが二の橋があった場所である。
鍛冶橋通りに交差するが、この細い路地が新川の流路。この路地は途中でビルに阻まれ中断されるがそのあたりが二の橋があった場所である。
 新川のど真ん中であった路地は中断されたので、右岸あたりから再び西へ進む。
新川のど真ん中であった路地は中断されたので、右岸あたりから再び西へ進む。
 新川大神宮に遭遇。
新川大神宮に遭遇。
 1625年、慶光院周清上人が二代将軍 / 徳川秀忠から江戸代官町に屋敷を賜り、邸内に創建したのが新川大神宮の起源。明暦の大火(1657年)で類焼し、この霊岸島で再建された。産土神としてとくに酒問屋の信仰が篤かった。昭和20年の戦災で焼失するが、酒問屋らにより昭和27年に社殿が再建された。新川大神宮からさらに西、大通りに交差するあたりが「一ノ橋」の位置。
1625年、慶光院周清上人が二代将軍 / 徳川秀忠から江戸代官町に屋敷を賜り、邸内に創建したのが新川大神宮の起源。明暦の大火(1657年)で類焼し、この霊岸島で再建された。産土神としてとくに酒問屋の信仰が篤かった。昭和20年の戦災で焼失するが、酒問屋らにより昭和27年に社殿が再建された。新川大神宮からさらに西、大通りに交差するあたりが「一ノ橋」の位置。
【 江戸城 探索TOP および目次 】



