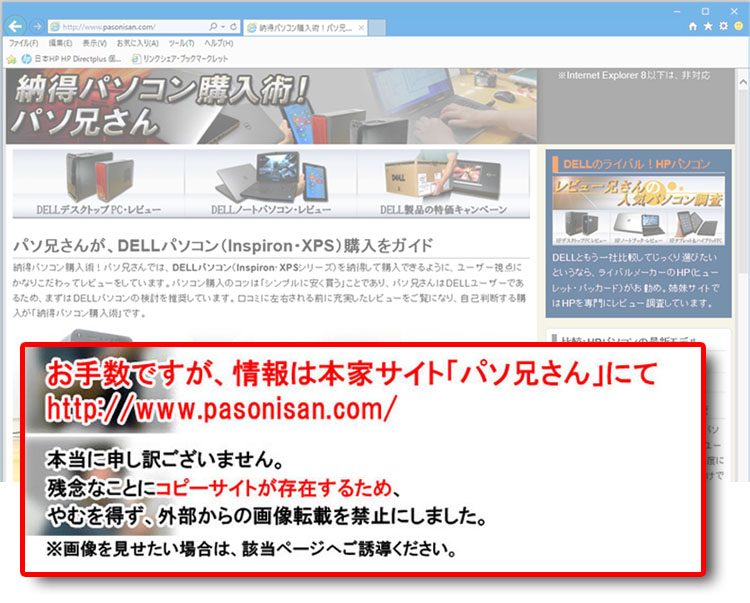

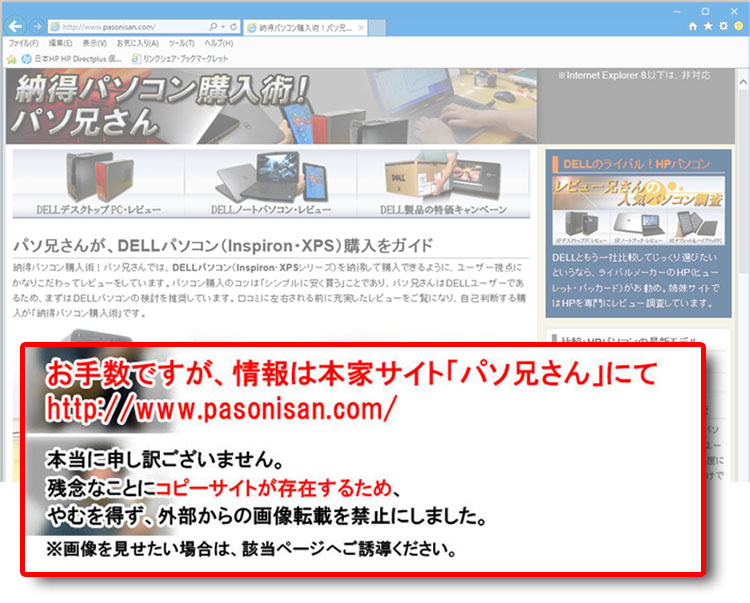
- HOME
- DELLパソコン・モバイル旅行記
- 東京都
- 江戸城(千代田区・中央区ほか)
江戸城 天然要害の隅田川と、隅田川に面した島
天然要害の大川(隅田川)
 江戸城の総構えと、運河の水堀。江戸城の中心や西部では、武蔵野台地や谷戸を利用した「山の手」なので、堀は曲面や尖った構造が多く防御に徹している。それに対し、江戸城の東端である「下町」は埋め立て地であるため、運河となった堀や町並みは直線的に区画されている。
江戸城の総構えと、運河の水堀。江戸城の中心や西部では、武蔵野台地や谷戸を利用した「山の手」なので、堀は曲面や尖った構造が多く防御に徹している。それに対し、江戸城の東端である「下町」は埋め立て地であるため、運河となった堀や町並みは直線的に区画されている。
 下町の堀は、見附の配置された外堀(日本橋川・外濠川・汐留川)から分岐して大川(隅田川)へ注いでおり、これは防御というよりも運河(水路)である。そして町屋(グレーの色分け)で占められている。下町に武家屋敷(黄色)が見られるが、これは明暦の大火(1657年)の影響で下町へ移転したためである。
下町の堀は、見附の配置された外堀(日本橋川・外濠川・汐留川)から分岐して大川(隅田川)へ注いでおり、これは防御というよりも運河(水路)である。そして町屋(グレーの色分け)で占められている。下町に武家屋敷(黄色)が見られるが、これは明暦の大火(1657年)の影響で下町へ移転したためである。
大川(隅田川)
天然の要害であるが江戸城東端の隅田川。江戸時代では浅草寺近くの吾妻橋(大川橋)あたりから下流を「大川」と呼んでいた(以下、隅田川と呼称)。隅田川西岸には浅草や蔵前など大規模な河岸が整備され、舟運の重要地となった。

両国橋から隅田川の下流(南方)を臨む
徳川家康が江戸入封してから明暦の大火(1657年)まで、江戸城東側の隅田川には防衛のため橋は無く、かなり離れた場所に架橋された千住大橋だけであった。明暦の大火後の市区改正により、両国橋、新大橋、永代橋が架橋され、それにより隅田川東岸では深川や本所などの市街地が発展した。
江戸時代まで、隅田川に架橋された5つの橋
江戸時代、隅田川に架橋された順は次の通り。千住大橋(1594年)、両国橋(1659年 or 1661年)、新大橋(1693年)、永代橋(1698年)、吾妻橋(1774年) 江戸時代、明暦の大火(1657年)以降、江戸城東端に架けられた橋は、両国橋、新大橋、永代橋の3つ。しかも現在の位置とは微妙に変わっている(江戸時代の位置は赤線、現在のは白線で記した)。
江戸時代、明暦の大火(1657年)以降、江戸城東端に架けられた橋は、両国橋、新大橋、永代橋の3つ。しかも現在の位置とは微妙に変わっている(江戸時代の位置は赤線、現在のは白線で記した)。
江戸時代には存在しない橋には、中洲跡に架けられた清洲橋(1928年)、田安徳川家下屋敷跡(箱崎島)から架けられている隅田川大橋(1979年)がある。隅田川(両国橋以南)から更に東へ分岐する堀には、堅川、小名木川、仙台堀、油堀がある。
江戸時代、隅田川に面する島には、箱崎島、霊岸島、石川島、佃島があった。
両国橋 1659年/1661年~
 江戸時代の両国橋は1659年または1661年に架けられた。当初は「大橋」という名称であったが、武蔵国と下総国の国境にあったことから、俗称で両国橋と呼ばれていた。後に正式名称となった。
江戸時代の両国橋は1659年または1661年に架けられた。当初は「大橋」という名称であったが、武蔵国と下総国の国境にあったことから、俗称で両国橋と呼ばれていた。後に正式名称となった。
隅田川に架けられた橋としては千住大橋に次いで2番目。明暦の大火の後(1657年)、防災目的のためすぐに架けられた。1693年に新大橋が架けられるまでは、江戸城東端の隅田川では両国橋のみの時代がしばらく続いた。
 隅田川の河川敷、中央区立両国橋際児童遊園を南下しながら隅田川を巡る。首都高速7号小松川線が見えるがこれは1971年に開通したものだ。江戸時代であればここから見てちょうど目の前に両国橋があったはずだが、現在の両国橋は100mほど北に移っている。
隅田川の河川敷、中央区立両国橋際児童遊園を南下しながら隅田川を巡る。首都高速7号小松川線が見えるがこれは1971年に開通したものだ。江戸時代であればここから見てちょうど目の前に両国橋があったはずだが、現在の両国橋は100mほど北に移っている。
 歌川広重の「江都名所 両国橋納涼」と、東京開化名所の「両国橋大川ばた」
歌川広重の「江都名所 両国橋納涼」と、東京開化名所の「両国橋大川ばた」
両国川開きは1733年に始められた。5/28~8/28まで行われ、時々花火が打ち上げられた。花火は横山町の鍵屋と吉川町(東日本橋2丁目)の玉屋が請け負って技を競った。両国橋の上流で玉屋が、下流で鍵屋が打ち上げた。昭和37年に川開きは中止されたが、現在はさらに上流で「隅田川花火大会」が行われるようになった。
 両国橋の西詰めには火除け地として両国広小路(中央区東日本橋二丁目)が設けられ、江戸三大広小路のひとつに数えられる。他には下谷広小路(上野広小路)、雷門通りの浅草広小路がある。
両国橋の西詰めには火除け地として両国広小路(中央区東日本橋二丁目)が設けられ、江戸三大広小路のひとつに数えられる。他には下谷広小路(上野広小路)、雷門通りの浅草広小路がある。
火除け地とはいえ、空き地になれば目的外で人が集まり、見世物小屋や飲食店が立ち並び繁華街となった。明治座の前身である富田三兄弟の菰張芝居は、両国西広小路で始まっている。明治時代になると、両国橋の東に両国駅や両国国技館が造られ、繁華街は主に東両国へ移った。
 両国橋西交差点に「旧跡 両国広小路」の碑が建つ。ただし両国橋が架かる場所が江戸時代とは異なるため、当時の両国広小路はここより100mほど南にあった。
両国橋西交差点に「旧跡 両国広小路」の碑が建つ。ただし両国橋が架かる場所が江戸時代とは異なるため、当時の両国広小路はここより100mほど南にあった。
 当時の両国橋の西詰はこの辺となる。明治後期まで架橋はこの位置であった。現在、両国広小路跡の一画にはビルが建ち並び、すでに広小路の面影はない。
当時の両国橋の西詰はこの辺となる。明治後期まで架橋はこの位置であった。現在、両国広小路跡の一画にはビルが建ち並び、すでに広小路の面影はない。
新大橋 1693年~
 両国橋の下流に架けられた新大橋。江戸時代ではもう少し下流の方に架けられていた。
両国橋の下流に架けられた新大橋。江戸時代ではもう少し下流の方に架けられていた。
江戸時代、最初に新大橋が隅田川に架けられたのは1693年。5代将軍・徳川綱吉の生母・桂昌院が架橋することを綱吉に勧めたとされる。両国橋(当時の正式名称は大橋)に次ぐ架橋だったので「新大橋」と呼ばれた。ピントラス式鉄橋に変わったのは1912年のこと(現物は愛知県犬山市の博物館明治村で保存されている)。橋台の沈下により、1977年、現在の橋に架けかえられた。
関東大震災(1923年)では、隅田川の橋はことごとく焼け落ちていったが、新大橋だけは被災せずに多くの人命を救った。これにより、「人助け橋」と呼ばれた。水天宮の御神体も新大橋に救われたという。橋の西詰にある久松警察署浜町交番敷地裏に、「人助け橋の由来碑」が建つ。
 江戸時代に架かっていた新大橋の場所は、現在の橋の位置から200mほど南で、この中央区立中洲公園あたり。歌川広重の名所江戸百景 「大はしあたけの夕立」で描かれている。
江戸時代に架かっていた新大橋の場所は、現在の橋の位置から200mほど南で、この中央区立中洲公園あたり。歌川広重の名所江戸百景 「大はしあたけの夕立」で描かれている。
清洲橋(中洲の渡し跡) ※江戸時代には無し
 清洲橋は江戸時代にはない。当時は無人の中洲で、中洲(なかず)の渡しがあった。関東大震災の震災復興事業の1928年(昭和3年)、清洲橋の架橋で渡しは廃止された。
清洲橋は江戸時代にはない。当時は無人の中洲で、中洲(なかず)の渡しがあった。関東大震災の震災復興事業の1928年(昭和3年)、清洲橋の架橋で渡しは廃止された。
深川区清住町と日本橋区中洲町の両岸を結ぶ橋であるため、各一字の「清」と「洲」をとって清洲橋という名称が公募により決まった。筋骨隆々とした男性的イメージでデザインされた永代橋に対して、清洲橋は下垂曲線を描く女性的なイメージでデザインされている。このように対比的な組み合わせにより、永代橋と清洲橋をセットにして第一回選奨土木遺産に指定されている。
隅田川大橋 ※江戸時代には無し
 江戸時代に隅田川大橋はない。1979年、首都高速9号深川線建設にあわせて隅田川大橋が架橋された。
江戸時代に隅田川大橋はない。1979年、首都高速9号深川線建設にあわせて隅田川大橋が架橋された。
 古地図を見ると、東岸では首都高速9号深川線の高架下に沿って油堀(油堀川)への分岐点があった。油堀は永代寺や富岡八幡宮の北を流れる十五間川となる。しかし、油堀は首都高速が建造される以前の1975年に埋め立てられて消滅している。油堀の名称は、油堀河岸があり江東区の佐賀や福住に油問屋が多くあったことに由来する。
古地図を見ると、東岸では首都高速9号深川線の高架下に沿って油堀(油堀川)への分岐点があった。油堀は永代寺や富岡八幡宮の北を流れる十五間川となる。しかし、油堀は首都高速が建造される以前の1975年に埋め立てられて消滅している。油堀の名称は、油堀河岸があり江東区の佐賀や福住に油問屋が多くあったことに由来する。
 隅田川大橋ならびに首都高速9号線は西岸の箱崎島で、「田安徳川家の箱崎下屋敷跡」を通過している。さらに分岐する首都高速6号線の下には、箱崎島の堀であった箱崎川があったが昭和46年に埋め立てられている。箱崎島については後述する。
隅田川大橋ならびに首都高速9号線は西岸の箱崎島で、「田安徳川家の箱崎下屋敷跡」を通過している。さらに分岐する首都高速6号線の下には、箱崎島の堀であった箱崎川があったが昭和46年に埋め立てられている。箱崎島については後述する。
永代橋 1698年~
 江戸時代、永代橋の場所は、現在架かっている位置から北100mほどのところ。この説明板がある位置である。元来、大渡し(深川の渡し)があった位置だが永代橋の架橋により渡しは廃止された。1698年に架橋された永代橋は、隅田川に架橋された5つの橋のうち4番目となる。
江戸時代、永代橋の場所は、現在架かっている位置から北100mほどのところ。この説明板がある位置である。元来、大渡し(深川の渡し)があった位置だが永代橋の架橋により渡しは廃止された。1698年に架橋された永代橋は、隅田川に架橋された5つの橋のうち4番目となる。
※千住大橋(1594年)、両国橋(1659年 or 1661年)、新大橋(1693年)、永代橋(1698年)、吾妻橋(1774年)
築造由来には諸説あるが、5代将軍 徳川綱吉の50歳を祝う記念事業として架けられたという。上野寛永寺の根本中堂造営で余った木材を使ったとされ、普請は関東郡代(浅草橋門となりに役宅あり)の伊奈忠順。名称は永代島(現在の江東区富岡)にちなむ。「永代寺につながる橋、江戸幕府が末永く代々続くように願掛けした」などという話もあるが、「永代島につながる橋」が正しいと思われる。
 歌川広重が描いた東都名所永代橋全図。1702年、赤穂浪士が吉良上野介屋敷へ討ち入りしたが、吉良上野介の首を掲げて泉岳寺へ向かった際に永代橋を渡っている。1807年、深川富岡八幡宮で祭礼が行われた際、押し寄せる群衆の重みに橋が耐え切れず、落橋事故が起きている。
歌川広重が描いた東都名所永代橋全図。1702年、赤穂浪士が吉良上野介屋敷へ討ち入りしたが、吉良上野介の首を掲げて泉岳寺へ向かった際に永代橋を渡っている。1807年、深川富岡八幡宮で祭礼が行われた際、押し寄せる群衆の重みに橋が耐え切れず、落橋事故が起きている。
 西詰めに旗が見られるが、これは高尾稲荷社(遊女高尾太夫を祀る神社)。現在は近くに遷座されている。
西詰めに旗が見られるが、これは高尾稲荷社(遊女高尾太夫を祀る神社)。現在は近くに遷座されている。
 現在の永代橋は1926年(大正15年)に震災復興事業により架けられ、「帝都東京の門」と言われた。永代橋は筋骨隆々とした男性的イメージでデザインされ、その対比として清洲橋は下垂曲線を描く女性的なイメージでデザインされている。
現在の永代橋は1926年(大正15年)に震災復興事業により架けられ、「帝都東京の門」と言われた。永代橋は筋骨隆々とした男性的イメージでデザインされ、その対比として清洲橋は下垂曲線を描く女性的なイメージでデザインされている。
 永代橋のデザインは柳橋でも採用されている。
永代橋のデザインは柳橋でも採用されている。
【 江戸城 探索TOP および目次 】



