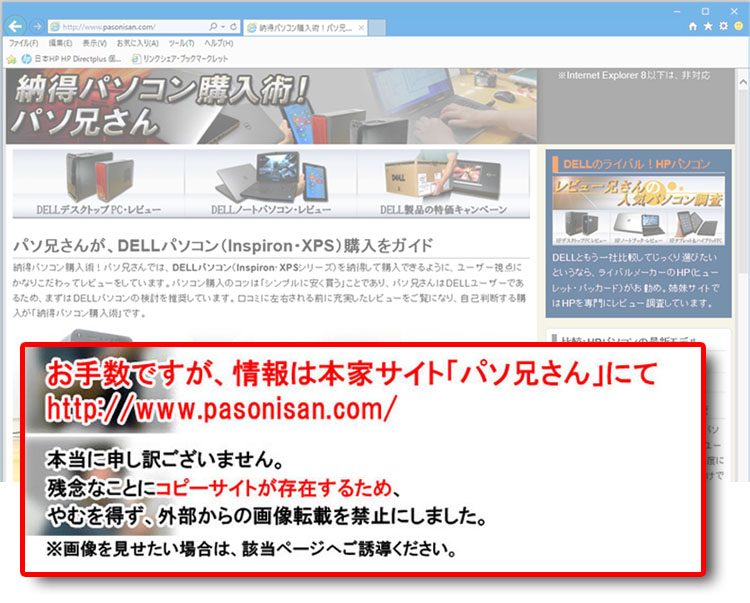

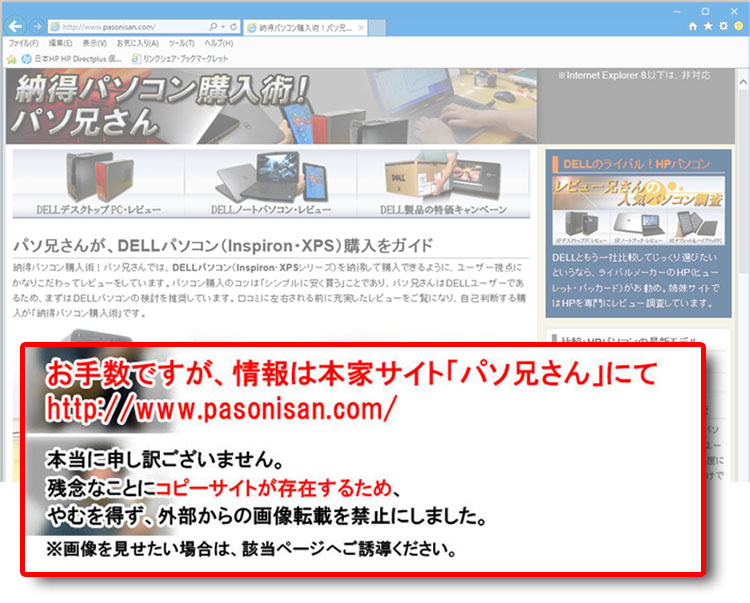
- HOME
- DELLパソコン・モバイル旅行記
- 東京都
- 江戸城(千代田区・中央区ほか)
江戸城 天然要害の隅田川と、隅田川に面した島
石川島
霊岸島の南東、現在の永代橋以南に広がる石川島(現在の東京都中央区佃二丁目)。江戸時代では隅田川の河口にあたる。石川島は、古くは森島や鎧島と呼ばれていた。旗本の石川八左衛門(石川重次)が徳川家光から拝領し、代々屋敷を構えた島なので「石川島」と呼ばれた。宇都宮釣天井事件(1622年)では、石川重次はその剛力で家光を危機から救った人物とされるが、釣天井が事実ではないし、第2代将軍徳川秀忠を襲った事件とされているし、あくまで伝説の話である。
1790年には長谷川宣以(鬼平こと長谷川平蔵)の提案により加役方 人足寄場(にんそくよせば)が置かれた。これは軽度犯罪者の教育や自立支援を行った施設であったが、強制収容所に近い問題もあった。他者に苦労させて利益を得ることを「油を絞る」というが、ここの「油しぼり」という職種が重労働だった事から生まれた言葉だという。1866年、油しぼりの利益で石川島に灯台が造られた。明治時代以降、東京の都市化に伴い施設は巣鴨に移転し「巣鴨プリズン」となった
※加役方(かやくかた)とは「火付盗賊改方」の略称、江戸市中を巡回して、放火・盗賊・ばくち打ちなどの検挙にあたった職名。
 佃公園(石川島の立地)に置かれている江戸時代末期の石川島と佃島の地図。
佃公園(石川島の立地)に置かれている江戸時代末期の石川島と佃島の地図。
 歌川広重が描いた東都名所永代橋全図。永代橋以南に広がる石川島と佃島が描かれている。
歌川広重が描いた東都名所永代橋全図。永代橋以南に広がる石川島と佃島が描かれている。
1853年、江戸幕府は水戸藩に命じて石川島に造船所を創業した。西洋式軍艦「旭日丸」「千代田形」などが建造されている。後に官営の石川島修船所となり閉鎖。1876年(明治9年)、石川島造船所(現・IHI)創立者の平野富二に払い下げられ、翌年、日本初の蒸気船「通運丸」を建造している。
1929年、自動車部門は石川島自動車製作所(いすゞ自動車)として独立している。1924年には石川島飛行機製作所を設立(現・立飛企業)し、立飛企業の前身、立川飛行機株式会社は戦時中、一式戦「隼」二型(キ43-II)や三型(キ43-III)を量産している。たま自動車(プリンス自動車)の創業者のひとり、田中次郎は立川飛行機の出身技師。
 明治時代、南側の佃島と合併して町名が「佃」となった。IHI(石川島播磨重工業)東京工場跡地に建つ超高層住宅地の、大川端リバーシティ21がなんとも異様な光景だ。
明治時代、南側の佃島と合併して町名が「佃」となった。IHI(石川島播磨重工業)東京工場跡地に建つ超高層住宅地の、大川端リバーシティ21がなんとも異様な光景だ。
 現在では霊岸島(中央区新川二丁目)と中央大橋でつかながっている。中央大橋は1994年に架橋され、隅田川に架かる橋では平成時代の第一号となった。隅田川はフランス・セーヌ川と友好河川で結ばれており、中央大橋の設計ををフランスのデザイン会社に依頼している。橋桁製作はもちろん石川島播磨重工業。
現在では霊岸島(中央区新川二丁目)と中央大橋でつかながっている。中央大橋は1994年に架橋され、隅田川に架かる橋では平成時代の第一号となった。隅田川はフランス・セーヌ川と友好河川で結ばれており、中央大橋の設計ををフランスのデザイン会社に依頼している。橋桁製作はもちろん石川島播磨重工業。
 中央大橋から永代橋を眺める。橋脚部にあるこの彫像はオシップ・ザッキン作の「メッセンジャー」。当時のパリ市長であったジャック・シラク(後に第22代フランス大統領)から贈られたもの。
中央大橋から永代橋を眺める。橋脚部にあるこの彫像はオシップ・ザッキン作の「メッセンジャー」。当時のパリ市長であったジャック・シラク(後に第22代フランス大統領)から贈られたもの。
 島北端の隅田川テラスは、セーヌ川にちなんでパリ広場と命名されている。
島北端の隅田川テラスは、セーヌ川にちなんでパリ広場と命名されている。
 パリ広場の階段護岸や自然石護岸では、直接、水に接することができる。江戸時代の石川島よりやや周囲を拡張していると思われる。
パリ広場の階段護岸や自然石護岸では、直接、水に接することができる。江戸時代の石川島よりやや周囲を拡張していると思われる。
 佃島と堀を挟んで北側にある公園は「人足寄場」の役所が置かれた場所。
佃島と堀を挟んで北側にある公園は「人足寄場」の役所が置かれた場所。
 人足寄場の南端、佃公園にある灯台型のモニュメント。今ではトイレに成っているが、かつて石川島の灯台があった場所である。1866年に清水純時(人足寄場奉行)によって六角二層の灯台が建てられた。石川島の渡し船はここから出ていた。灯台の建設では、重労働であった人足らの「油絞り」から益金が割られており、ひどい苦労をするという意味の「油を絞る」という言葉が生まれた。
人足寄場の南端、佃公園にある灯台型のモニュメント。今ではトイレに成っているが、かつて石川島の灯台があった場所である。1866年に清水純時(人足寄場奉行)によって六角二層の灯台が建てられた。石川島の渡し船はここから出ていた。灯台の建設では、重労働であった人足らの「油絞り」から益金が割られており、ひどい苦労をするという意味の「油を絞る」という言葉が生まれた。
【 江戸城 探索TOP および目次 】



