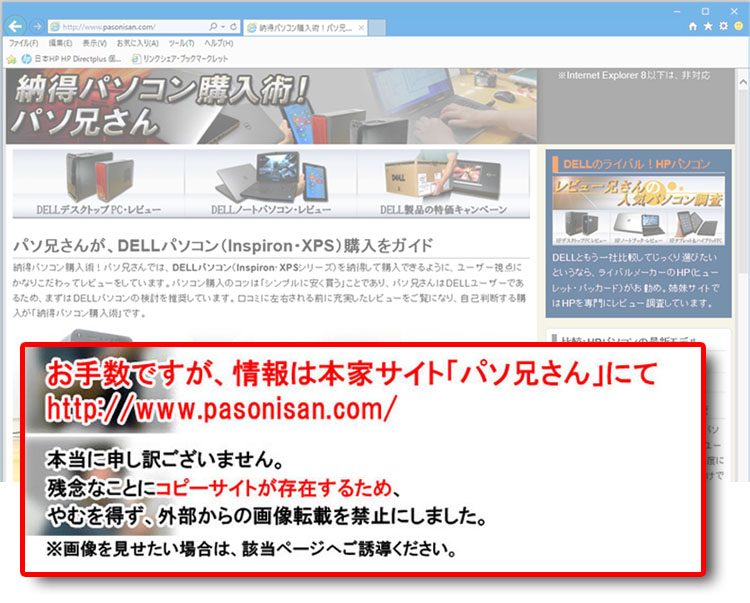

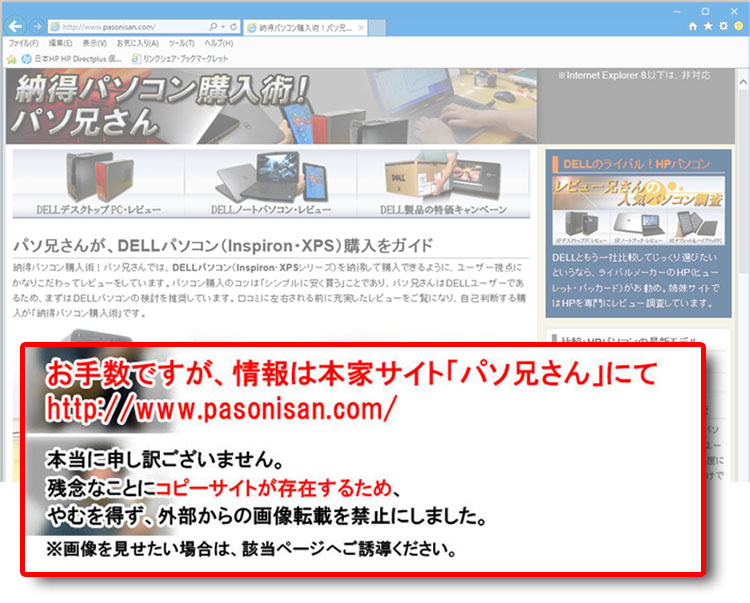
- HOME
- DELLパソコン・モバイル旅行記
- 東京都
- 江戸城(千代田区・中央区ほか)
江戸城 外堀の見附
雉子橋門
江戸城外堀は、雉子橋門から渦巻き形(のノ字)で時計回りに配置され、いくつかの諸門(見附)をめぐり、牛込門を経て神田川に合流する。その神田川も外堀であり浅草門を経て隅田川に合流する。一般的には、雉子橋門を「見附が置かれた外堀」の起点として紹介されることが多い。
徳川家康の時代、朝鮮からの使節を饗応するため好物の雉をこの付近の鳥小屋で飼育していた。これが雉子橋の名称由来になっている。1629年、徳川家康の次男「結城秀康」の六男・松平直良の普請で門が築造され、雉子橋が架けられた。外堀に配置された見附のうち最も江戸城本丸に近いため、厳重な警備が施されている。【 江戸城の外堀に配置された見附の位置 】
 日本橋川に架かる現在の雉子橋(きじばし)。
日本橋川に架かる現在の雉子橋(きじばし)。
現在の橋は関東大震災後の大正15年に架けられたもので、江戸時代の雉子橋はここより約100m上流にあり東西に架かっていた。現在の橋は場所も違うし水堀の南北に架かっている。
 古地図から江戸時代の雉子橋の位置を割り出すと、日産自動車販売 九段店のビルに架かる状態になる。写真では上流(堀留方面)を向いている。隅角部の石垣が一部残っている。
古地図から江戸時代の雉子橋の位置を割り出すと、日産自動車販売 九段店のビルに架かる状態になる。写真では上流(堀留方面)を向いている。隅角部の石垣が一部残っている。
 雉子橋の櫓門は1873年(明治6年)に撤去された。橋は1903年(明治36年)に鉄橋に架け替えられたが、1923年(大正12年)の関東大震災で被害を受けた。1925年(大正14年)に、下流100mの場所に変えて現在の鋼製アーチ橋が架けられた。
雉子橋の櫓門は1873年(明治6年)に撤去された。橋は1903年(明治36年)に鉄橋に架け替えられたが、1923年(大正12年)の関東大震災で被害を受けた。1925年(大正14年)に、下流100mの場所に変えて現在の鋼製アーチ橋が架けられた。
 雉子橋の枡形石垣は日本橋川と清水堀の間に跨っており、場所は今の内堀通りで首都高の高架下あたり。江戸城では外堀と内堀が最も接近している見附である。
雉子橋の枡形石垣は日本橋川と清水堀の間に跨っており、場所は今の内堀通りで首都高の高架下あたり。江戸城では外堀と内堀が最も接近している見附である。
 現地の案内板にあった古地図。雉子橋門から外堀の規模が大きくなっている。このように雉子橋門から水濠が始まっているのではなく、細いながらも北側の「堀留」まで続いている。しかし、これは防御の水堀というよりただの水路というべきか。
現地の案内板にあった古地図。雉子橋門から外堀の規模が大きくなっている。このように雉子橋門から水濠が始まっているのではなく、細いながらも北側の「堀留」まで続いている。しかし、これは防御の水堀というよりただの水路というべきか。
 現在の雉子橋の南詰に警視庁麹町分庁舎があるが、そこには石垣の建造物がある。ただし古地図をみると、この位置は水堀の中に位置していため、史跡でも再現でもなさそうだ。石材を利用しただけのものなのか詳細不明で紛らわしい存在である。
現在の雉子橋の南詰に警視庁麹町分庁舎があるが、そこには石垣の建造物がある。ただし古地図をみると、この位置は水堀の中に位置していため、史跡でも再現でもなさそうだ。石材を利用しただけのものなのか詳細不明で紛らわしい存在である。
 雉子橋から出土した石垣石は、市ヶ谷駅の江戸歴史散歩コーナー(東京メトロ南北線コンコース内)で見学できる。石積技法「打込みハギ」の再現展示となっている。
雉子橋から出土した石垣石は、市ヶ谷駅の江戸歴史散歩コーナー(東京メトロ南北線コンコース内)で見学できる。石積技法「打込みハギ」の再現展示となっている。
 雉子橋門から下流約300m先に一橋門がある。
雉子橋門から下流約300m先に一橋門がある。
 雉子橋門から一橋門の間にある外堀石垣。1636年の天下普請により、雉子橋から虎ノ門までの外堀石垣化が行われている。
雉子橋門から一橋門の間にある外堀石垣。1636年の天下普請により、雉子橋から虎ノ門までの外堀石垣化が行われている。
補足事項:堀留
江戸城外堀の見附は雉子橋門から一橋門方面へ渦巻き状に配置されているのだが、先述の通り、水路を含めば「堀留」が外堀の起点となる。見附巡りではないが、補足事項として散策してみる。
 堀留(ほりどめ)という呼び名から判るように、江戸城の改修で旧平川(現在の日本橋川)の流路は埋め立てられ、堀留(現在の新川橋がある位置)で締め切られていた。そのため堀留から続く時計回りの外堀は独立した堀になった。ちなみに、堀留の北に向かうと小石川門がある。
堀留(ほりどめ)という呼び名から判るように、江戸城の改修で旧平川(現在の日本橋川)の流路は埋め立てられ、堀留(現在の新川橋がある位置)で締め切られていた。そのため堀留から続く時計回りの外堀は独立した堀になった。ちなみに、堀留の北に向かうと小石川門がある。
 平川は流路が埋め立てられ堀留橋で締め切られ、下流に続いていた平川は独立した堀になった。だたし神田川の小石川門から分岐する水路のようなものはあったようだ(赤線の位置)。飯田町遺跡発掘調査(2000年)によれば、1657年の明暦の大火直後に埋め立てられたことがわかっている。現在では神田川から分流して日本橋川が流れているが、これは1903年に神田川~堀留橋までを再び開削したからである。
平川は流路が埋め立てられ堀留橋で締め切られ、下流に続いていた平川は独立した堀になった。だたし神田川の小石川門から分岐する水路のようなものはあったようだ(赤線の位置)。飯田町遺跡発掘調査(2000年)によれば、1657年の明暦の大火直後に埋め立てられたことがわかっている。現在では神田川から分流して日本橋川が流れているが、これは1903年に神田川~堀留橋までを再び開削したからである。
 雉子橋から堀留までは比較的小規模な外堀となっており、飯田川と呼ばれていた。
雉子橋から堀留までは比較的小規模な外堀となっており、飯田川と呼ばれていた。
 江戸時代、雉子橋から堀留までの間に、俎橋(まないた ばし)と蜻橋(こうろぎ ばし)の2つの橋が架けられている。堀留橋は見られないので後世に架けられた橋のようだ。
江戸時代、雉子橋から堀留までの間に、俎橋(まないた ばし)と蜻橋(こうろぎ ばし)の2つの橋が架けられている。堀留橋は見られないので後世に架けられた橋のようだ。
 現在の俎橋。
現在の俎橋。
俎橋は西方の九段坂(靖国通り)と結んでおり、現在も同じ位置に橋が架けられている。北の丸の田安門に至る橋であった。諸説あるが、橋が2枚のまな板を渡したような板橋であったことに名前の由来があるという。近くに台所町があったことに由来するという説もある。現在の俎橋は1983年(昭和58年)に鋼桁橋に架け直されたもの。九段坂は江戸時代の面影はなく、工事によって高低差が控えめになっている。
蜻橋は西方の冬青木坂(もちのきざか)と結んでいた。冬青木坂は、駐日フィリピン大使公邸(旧安田岩次郎邸)の南側の坂。蜻(とんぼ)と書いて「こうろぎ」と読むのが謎だ。現在、蜻橋の位置には橋は架かっていない。蜻橋の所からわずか北30mほどの上流に堀留橋が架けられたので、堀留橋が蜻橋の代替となったのだろう。堀留橋は専大通りに架けられた橋なので、蜻橋が架かっていた場所では不都合だったと思われる。
 こちらが堀留橋。専大通りに架かる橋であるが、古地図をみると江戸時代に堀留橋という橋は無く、橋も架かっていない。堀留橋の上流約120m(現在の新川橋あたり)で水路が途切れている。
こちらが堀留橋。専大通りに架かる橋であるが、古地図をみると江戸時代に堀留橋という橋は無く、橋も架かっていない。堀留橋の上流約120m(現在の新川橋あたり)で水路が途切れている。
 江戸時代には新川橋は架かっていない。現在の橋は昭和2年(1927年)に架けられた。江戸城の改修で旧平川(現在の日本橋川)の流路はここまで埋め立てられた。つまり、ここを本来の「堀留」というのが相応しいと思われる。1903年に再び開削されたので、現在では、日本橋川の上流として神田川(小石川門跡)までつながっている。再び開削した水路を新川として「新川橋」と呼んだのだろうか。
江戸時代には新川橋は架かっていない。現在の橋は昭和2年(1927年)に架けられた。江戸城の改修で旧平川(現在の日本橋川)の流路はここまで埋め立てられた。つまり、ここを本来の「堀留」というのが相応しいと思われる。1903年に再び開削されたので、現在では、日本橋川の上流として神田川(小石川門跡)までつながっている。再び開削した水路を新川として「新川橋」と呼んだのだろうか。
 新川橋から北上し、あいあい橋を越えると突き当りに神田川が見え、その合流点が小石川門跡である。ここは堀留より北側なので、江戸時代は外堀ではなく陸地であった(先述の通り、1657年の明暦の大火直後に埋め立てられた)。
新川橋から北上し、あいあい橋を越えると突き当りに神田川が見え、その合流点が小石川門跡である。ここは堀留より北側なので、江戸時代は外堀ではなく陸地であった(先述の通り、1657年の明暦の大火直後に埋め立てられた)。
 その埋め立てられた水路(堀留~小石川門の間)には、讃岐高松藩の上屋敷および中屋敷が置かれた。ちなみに高松藩の下屋敷は白金長者屋敷跡である。
その埋め立てられた水路(堀留~小石川門の間)には、讃岐高松藩の上屋敷および中屋敷が置かれた。ちなみに高松藩の下屋敷は白金長者屋敷跡である。
高松藩 初代藩主は、徳川光圀(水戸黄門)の同母兄の松平頼重。頼重は松平頼常(光圀の実子)を養子に迎え家督を譲った。一方、光圀は徳川綱條(頼重の実子)を養子に迎え家督を譲った。こういった水戸徳川家と高松藩との後継ぎトレードは何度か行われており、15代将軍の徳川慶喜は松平頼重の直系子孫である。
 日本橋川(当時は陸)を挟んで西に上屋敷、東に中屋敷が配置されている。1999年~2000年の飯田町遺跡発掘調査で、讃岐高松藩の上屋敷 庭園に造られた池跡が発見されている。神田上水を引き込んだ池であり、釣りをしていたと思われる漆塗りの浮きが出土している。そのほか、国元から運ばれたとされる庭石の景石や理平焼が出土している。また同調査で、江戸時代初期の石垣や土留め板の護岸跡(幅10mほどの堀)が発見されており、江戸城の改修で埋められた平川の名残と考えられている。
日本橋川(当時は陸)を挟んで西に上屋敷、東に中屋敷が配置されている。1999年~2000年の飯田町遺跡発掘調査で、讃岐高松藩の上屋敷 庭園に造られた池跡が発見されている。神田上水を引き込んだ池であり、釣りをしていたと思われる漆塗りの浮きが出土している。そのほか、国元から運ばれたとされる庭石の景石や理平焼が出土している。また同調査で、江戸時代初期の石垣や土留め板の護岸跡(幅10mほどの堀)が発見されており、江戸城の改修で埋められた平川の名残と考えられている。
堀留についての補足で話が脱線したが、次は雉子橋門から下流約300m先にある一橋門へ向かう。
【 江戸城 探索TOP および目次 】



