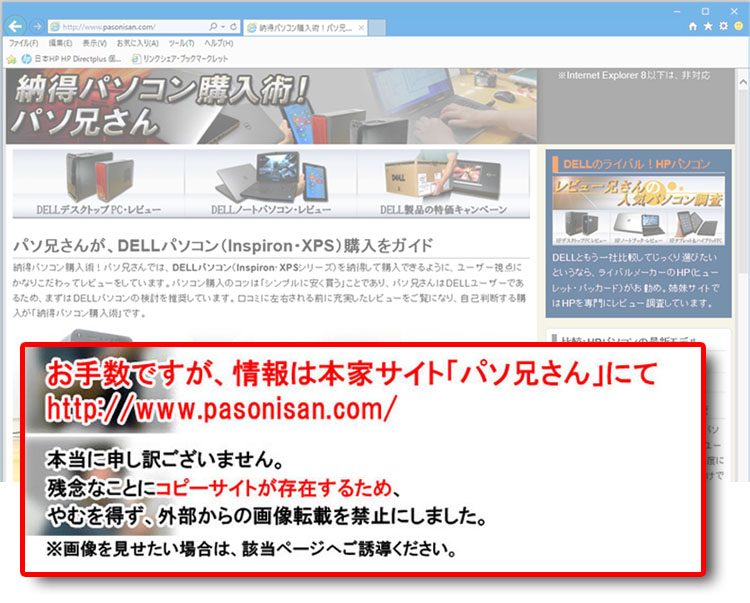

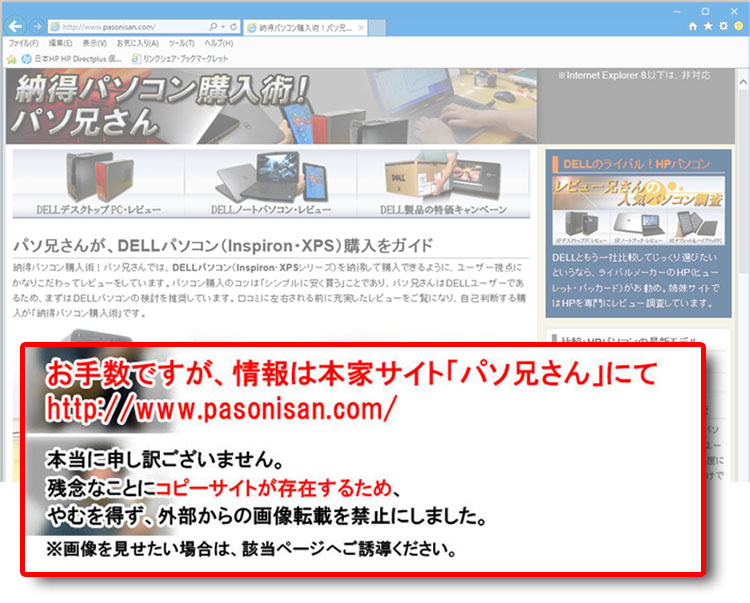
- HOME
- DELLパソコン・モバイル旅行記
- 東京都
- 江戸城(千代田区・中央区ほか)
江戸城 外堀の見附
外堀として利用された神田川
江戸城外堀では、雉子橋門~呉服橋門~赤坂門~牛込門と各見附を経て神田川に合流する。神田川は三鷹市井の頭池を水源とし、都心部を流れて隅田川へ注ぐ全長約25kmの都市河川である。
 神田川に置かれた見附は上流から順に「小石川門、筋違門、浅草門」の3つ。
神田川に置かれた見附は上流から順に「小石川門、筋違門、浅草門」の3つ。
船河原橋から小石川門まで
 現在の船河原橋は神田川を跨ぐ橋になっているが、江戸時代では北から流れて合流する神田川(旧名称:江戸川)の東西に架けられていた。船河原橋のある地点は、江戸城築城の際、洪水を防ぐために堀留まで旧平川を埋め立てた起点。そして神田川の流路を隅田川のある東に曲げる大工事が行われた地点である。
現在の船河原橋は神田川を跨ぐ橋になっているが、江戸時代では北から流れて合流する神田川(旧名称:江戸川)の東西に架けられていた。船河原橋のある地点は、江戸城築城の際、洪水を防ぐために堀留まで旧平川を埋め立てた起点。そして神田川の流路を隅田川のある東に曲げる大工事が行われた地点である。
 現在の船河原橋は昭和45年(1970年)に架けられたコンクリ-ト橋。飯田濠跡に建つビル「飯田橋ラムラ」の東隣。
現在の船河原橋は昭和45年(1970年)に架けられたコンクリ-ト橋。飯田濠跡に建つビル「飯田橋ラムラ」の東隣。
 北から流れてきた神田川(旧称:江戸川。1970年に神田川で統一)は、直角に東へ流れる神田川となる。この先、神田川の下流に進むと小石川門(水道橋駅近く)につながる。
北から流れてきた神田川(旧称:江戸川。1970年に神田川で統一)は、直角に東へ流れる神田川となる。この先、神田川の下流に進むと小石川門(水道橋駅近く)につながる。
飯田橋という地名
1590年(天正18年)、徳川家康が江戸の入封したとき、農村地帯だったこの土地を家康に案内したのが、「飯田喜兵衛」という人物だった。家康はこの一帯を「飯田町」と命名した。1881年(明治14年)に外堀を跨ぎ飯田町と結ぶ橋の「飯田橋」が架けられた。1928年(昭和3年)に「飯田橋駅」が開業すると、飯田町ではなく「飯田橋」が地名として浸透していった。
現在ある橋は、飯田橋と船河原橋だが、江戸時代では船河原橋だけである。旧称:江戸川の東西に架かっており、当時、ここに外堀を跨ぐ橋は無かった。
飯田橋の歩道橋から観る、神田川直角地点
神田川が東に向かって直角に曲がる地点「飯田橋」は非常に複雑な交差点である。まず歩道橋が枡形石垣ならぬ「枡形歩道橋」で方形の構えになっている。そんな歩道橋から各方面を眺めてみる。
 南西方面にJR飯田橋駅の東口、そして飯田橋ラムラ(RAMLA)のビル。本来なら飯田濠(牛込揚場)で、牛込堀から続いた水堀であったが、昭和47年の市街地再開発事業によって消滅した。
南西方面にJR飯田橋駅の東口、そして飯田橋ラムラ(RAMLA)のビル。本来なら飯田濠(牛込揚場)で、牛込堀から続いた水堀であったが、昭和47年の市街地再開発事業によって消滅した。
2020年までは現在の飯田橋駅 東口のところが駅ホームであったが、新宿駅方面の西200m(牛込門跡)に移設された。この従来の飯田橋駅ホームは外堀に沿った急カーブであったため、停車した電車とホームの隙間が広く、転落事故が起きていた。
 北方面。北から流れてくる旧称:江戸川。ここから直角に曲がり神田川と合流する川だが、名称は1970年に神田川で統一された。現在、旧称:江戸川を跨いでいる橋は五叉路の「飯田橋」。
北方面。北から流れてくる旧称:江戸川。ここから直角に曲がり神田川と合流する川だが、名称は1970年に神田川で統一された。現在、旧称:江戸川を跨いでいる橋は五叉路の「飯田橋」。
 南方面。奥に外堀(神田川)を跨ぐ船河原橋が見える。手前、自動車が走行している所が飯田橋。江戸時代ではここに外堀を跨ぐような橋は架けられていない。飯田橋が架けられたのは1881年(明治14年)。1908年(明治41年)には鉄橋に架け替えられた。関東大震災後、1929年(昭和4年)にコンクリート製の橋に替えられ現在に至っている。飯田橋という橋の名が町名として採用されたのは、1966年(昭和41年)のこと。
南方面。奥に外堀(神田川)を跨ぐ船河原橋が見える。手前、自動車が走行している所が飯田橋。江戸時代ではここに外堀を跨ぐような橋は架けられていない。飯田橋が架けられたのは1881年(明治14年)。1908年(明治41年)には鉄橋に架け替えられた。関東大震災後、1929年(昭和4年)にコンクリート製の橋に替えられ現在に至っている。飯田橋という橋の名が町名として採用されたのは、1966年(昭和41年)のこと。
 同じく南方。目白通り(東京都道8号千代田練馬田無線)と、2020年まで飯田橋駅ホームだった場所のガード下。神田川が直角に曲がる位置でもあり、外堀も東へ急カーブする位置である。この急カーブが電車降車時の落下事故を招いていた。
同じく南方。目白通り(東京都道8号千代田練馬田無線)と、2020年まで飯田橋駅ホームだった場所のガード下。神田川が直角に曲がる位置でもあり、外堀も東へ急カーブする位置である。この急カーブが電車降車時の落下事故を招いていた。
 飯田橋駅ホーム北端。外堀・神田川に沿っているため、このようなカーブ。現在は牛込見附の方に延長、移設したので、北端は使用されていない。またホーム北側では柵があり乗車・降車はできない。
飯田橋駅ホーム北端。外堀・神田川に沿っているため、このようなカーブ。現在は牛込見附の方に延長、移設したので、北端は使用されていない。またホーム北側では柵があり乗車・降車はできない。
小石川門へ向かう ~ 道中の市兵衛河岸
 小石川門のある東方面。手前に見えるのが船河原橋。現在では外堀(神田川)を跨いぐ橋だが江戸時代は違う。
小石川門のある東方面。手前に見えるのが船河原橋。現在では外堀(神田川)を跨いぐ橋だが江戸時代は違う。
 同じく小石川門のある東方面。古地図をみると、神田川の流路は、この平べったいビル群と車道の方にあったようだ。右側、JR線の土手は江戸城の土塁を利用していると思われる。
同じく小石川門のある東方面。古地図をみると、神田川の流路は、この平べったいビル群と車道の方にあったようだ。右側、JR線の土手は江戸城の土塁を利用していると思われる。
 外堀・神田川の南岸、その土塁下を歩く。「ここが江戸城の水堀だった」と思いを馳せながら歩く人間は稀なんだろうな。
外堀・神田川の南岸、その土塁下を歩く。「ここが江戸城の水堀だった」と思いを馳せながら歩く人間は稀なんだろうな。
 一方、外堀・神田川の北岸では、船河原橋から小石川橋~水道橋までが「市兵衛河岸」であった。河岸には、昌平橋との間を往復する船着き場(客船用)や物揚場があった。1732年の『江戸砂子』によれば、岩瀬市兵衛の屋敷があったことに由来する。※写真は船河原橋から小石川橋の間で、首都高速と外堀・神田川が重なっている地域。
一方、外堀・神田川の北岸では、船河原橋から小石川橋~水道橋までが「市兵衛河岸」であった。河岸には、昌平橋との間を往復する船着き場(客船用)や物揚場があった。1732年の『江戸砂子』によれば、岩瀬市兵衛の屋敷があったことに由来する。※写真は船河原橋から小石川橋の間で、首都高速と外堀・神田川が重なっている地域。
 ※現地の説明板では船河原橋~水道橋の範囲を市兵衛河岸と言っているが、幕末の古地図(大江戸今昔めぐり)では小石川橋~水道橋までになっている。
※現地の説明板では船河原橋~水道橋の範囲を市兵衛河岸と言っているが、幕末の古地図(大江戸今昔めぐり)では小石川橋~水道橋までになっている。
 岩瀬市兵衛の屋敷は船河原橋に近く、現在の住友不動産飯田橋ビル5号館あたり。幕末の古地図には、その場所は稲生出羽守の屋敷と記載されている。
岩瀬市兵衛の屋敷は船河原橋に近く、現在の住友不動産飯田橋ビル5号館あたり。幕末の古地図には、その場所は稲生出羽守の屋敷と記載されている。
【 江戸城 探索TOP および目次 】



