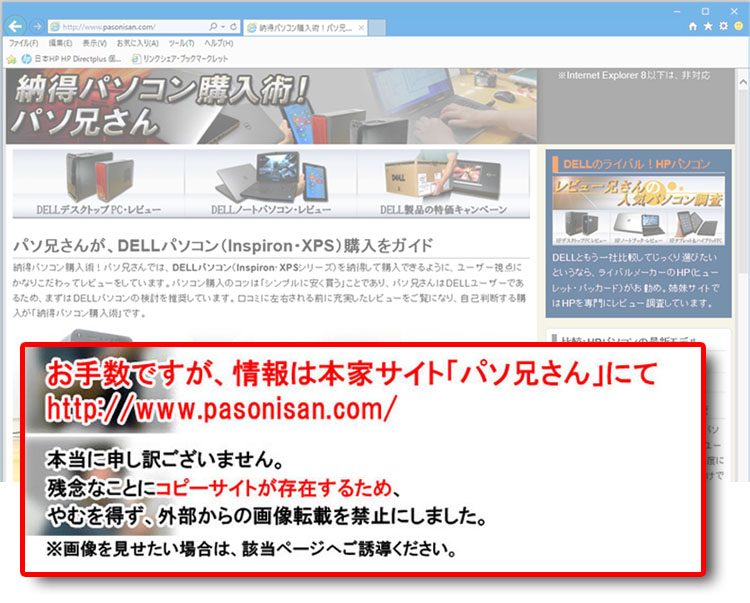

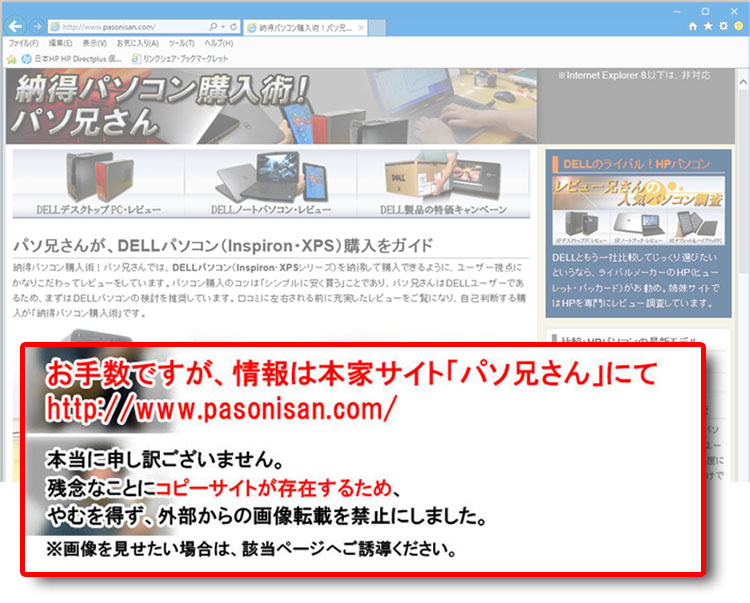
- HOME
- DELLパソコン・モバイル旅行記
- 東京都
- 江戸城(千代田区・中央区ほか)
江戸城 外堀の見附
常盤橋門(国史跡)
常盤橋門は1629年出羽・陸奥の大名によって築造された。大手門(江戸城の正門)に接続する外堀側の門であり、軍事上重要な位置にある。奥州道中(日光街道・奥州街道)につながる江戸五口のひとつであり、「追手口」とも呼ばれた。また、この街道が浅草に通じていることから「浅草口橋」ともいわれた。徳川家康が江戸に入封して日本橋が交通の軸になる以前は、この常盤橋(元・大橋)が交通の軸であった。【 江戸城の外堀に配置された見附の位置 】
 常盤橋門の構造は内枡形門の形式で、北側に渡櫓とそれを支える石垣がある。門をくぐると大番所が配置されている。東には冠木門、ほかの三方には土手が巡らされていた。
常盤橋門の構造は内枡形門の形式で、北側に渡櫓とそれを支える石垣がある。門をくぐると大番所が配置されている。東には冠木門、ほかの三方には土手が巡らされていた。
 現在は常盤橋公園として整備されている。
現在は常盤橋公園として整備されている。
 明治時代になると、常盤橋門の建造物は破却されたが、残った枡形石垣の一部が国史跡に指定された。
明治時代になると、常盤橋門の建造物は破却されたが、残った枡形石垣の一部が国史跡に指定された。
 北側、渡櫓の石垣。
北側、渡櫓の石垣。
 南側の護岸石垣。
南側の護岸石垣。
 常盤橋公園では、石垣保存に功績のあった渋沢栄一像が建っている。
常盤橋公園では、石垣保存に功績のあった渋沢栄一像が建っている。
明治時代に架けられた、常磐橋
 明治時代になると常盤橋門の建造物は破却され、1877年(明治10年)には、堀に架かっていた木橋が石橋のアーチ橋に架け替えられた。木造から新たに石橋になったので、常磐橋(漢字が石を指す「磐」)と漢字表記が変更された。「盤」から「磐」へ・・・。
明治時代になると常盤橋門の建造物は破却され、1877年(明治10年)には、堀に架かっていた木橋が石橋のアーチ橋に架け替えられた。木造から新たに石橋になったので、常磐橋(漢字が石を指す「磐」)と漢字表記が変更された。「盤」から「磐」へ・・・。
 現存している石橋の常磐橋。東京都内で現存する石橋では最古である。関東大震災で崩落の危険があったが保存運動があり国史跡に指定され復旧整備された。2011年の東関東大震災でも甚大な被害を受けたが、2012~2020年にかけて修繕事業が行われた。この際の調査で、基礎に小石川門の石材を転用していることが判明した。
現存している石橋の常磐橋。東京都内で現存する石橋では最古である。関東大震災で崩落の危険があったが保存運動があり国史跡に指定され復旧整備された。2011年の東関東大震災でも甚大な被害を受けたが、2012~2020年にかけて修繕事業が行われた。この際の調査で、基礎に小石川門の石材を転用していることが判明した。
 常磐橋を渡ると城外の位置に日本銀行がある。江戸時代では金座が置かれた。金座とは金貨の鋳造、鑑定や検印を行った場所である。牢屋敷が伝馬町に移転するまでは本石町にあったとされるので、だいたいこの付近である。
常磐橋を渡ると城外の位置に日本銀行がある。江戸時代では金座が置かれた。金座とは金貨の鋳造、鑑定や検印を行った場所である。牢屋敷が伝馬町に移転するまでは本石町にあったとされるので、だいたいこの付近である。
昭和に架橋された、道路橋の「常盤橋」
 こちらはもうひとつの常盤橋。もはや江戸城とは関係のない常盤橋である。常盤橋公園より70mほど離れた下流にある道路橋の「常盤橋」は、関東大震災後の復興計画で建設された橋であ。ちなみに、こちらは「盤」の字を用いた常盤橋になっており、明治期に架けられた「磐」の常磐橋と区別されている。さらに下流で一石橋に差し掛かる。
こちらはもうひとつの常盤橋。もはや江戸城とは関係のない常盤橋である。常盤橋公園より70mほど離れた下流にある道路橋の「常盤橋」は、関東大震災後の復興計画で建設された橋であ。ちなみに、こちらは「盤」の字を用いた常盤橋になっており、明治期に架けられた「磐」の常磐橋と区別されている。さらに下流で一石橋に差し掛かる。
一石橋(日本橋川と外濠川の分流点)
見附ではないが、一石橋は日本橋川と外濠川(江戸城の外堀)の分流点に架けられた橋で、現在では外堀通りを通している橋である。ここで分岐した外濠川は、東京都道405号外濠環状線(通称・外堀通り)あたりとなっており、赤坂門まで水堀が埋め立てられ消失している。日本橋川は隅田川まで続いており、途中で日本橋に差し掛かる。
江戸時代初期に一石橋の元となった木橋が「武州豊島郡江戸庄図」で確認されている。橋が破損した際、近くに屋敷を構える呉服商・後藤縫殿助と金座御用・後藤庄三郎の援助により再建された。後藤を五斗にもじって、「ふたりの後藤」=「五斗+五斗」で一石とする洒落が橋の名称由来だと伝わっている。
 1922年(大正11年)、RCアーチ橋として改架された。親柱が都内最古であることが認められ、区民有形文化財建造物に指定されている。
1922年(大正11年)、RCアーチ橋として改架された。親柱が都内最古であることが認められ、区民有形文化財建造物に指定されている。
 一石橋の橋詰には、迷い子探しの情報交換に使われる石標「迷い子のしるべ」 が設置されており、迷い子の保護に利用された(東京都指定有形文化財)。湯島天神や浅草寺、両国橋など往来の多い場所に同様の石標があったが、現存しているのは一石橋のものだけである。
一石橋の橋詰には、迷い子探しの情報交換に使われる石標「迷い子のしるべ」 が設置されており、迷い子の保護に利用された(東京都指定有形文化財)。湯島天神や浅草寺、両国橋など往来の多い場所に同様の石標があったが、現存しているのは一石橋のものだけである。
 日本橋川は日本橋方面へと隅田川に向かって流れているが、一石橋から分岐して呉服橋門へと流れる水濠が外濠川である。幸橋門あたりで汐留川に合流するまで続いているが、現在は埋められ消失している。
日本橋川は日本橋方面へと隅田川に向かって流れているが、一石橋から分岐して呉服橋門へと流れる水濠が外濠川である。幸橋門あたりで汐留川に合流するまで続いているが、現在は埋められ消失している。
【 江戸城 探索TOP および目次 】



