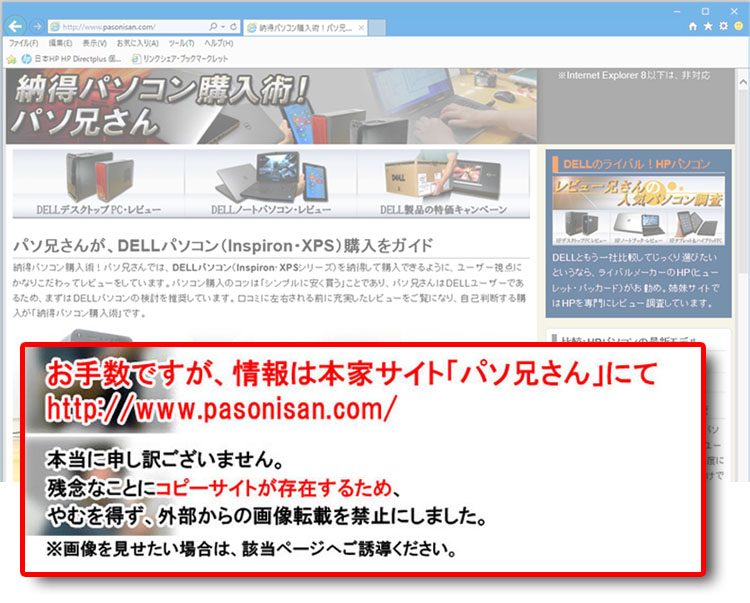

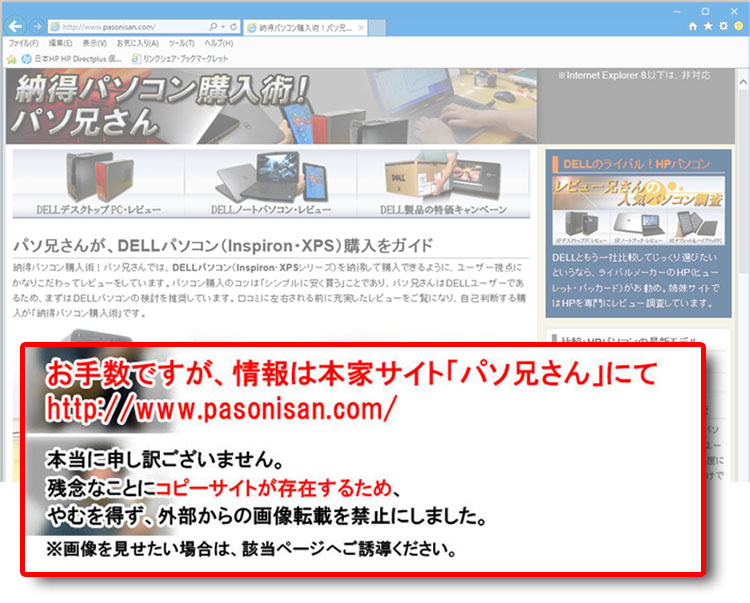
- HOME
- DELLパソコン・モバイル旅行記
- 東京都
- 江戸城(千代田区・中央区ほか)
江戸城 外堀の見附
呉服橋門
呉服橋門は1636年に築造された。名称は、門前(日本橋側・中央区八重洲1丁目)の町名が呉服町であったことに由来する。呉服町には幕府御用を勤めた呉服師の後藤家の屋敷があった。1871年(明治4年)、呉服橋門は撤去されたが枡形石垣と橋は残っていた。しかし戦後、外濠川が埋め立てられるとその姿も消した。【 江戸城の外堀に配置された見附の位置 】
 1871年の呉服橋門。
1871年の呉服橋門。
 呉服橋門跡は永代通り(国道20号線)で、TOKYO TORCH Parkの文字がみえるところ。目印に説明板があるが、跡地の名残りは一切ない。呉服橋門は常盤橋門の約200mほどの距離にあり近接していた。呉服橋を挟んで外濠川の東岸が呉服町、西岸には大名屋敷が立ち並んでおり、武家町と町人町との境目であった。
呉服橋門跡は永代通り(国道20号線)で、TOKYO TORCH Parkの文字がみえるところ。目印に説明板があるが、跡地の名残りは一切ない。呉服橋門は常盤橋門の約200mほどの距離にあり近接していた。呉服橋を挟んで外濠川の東岸が呉服町、西岸には大名屋敷が立ち並んでおり、武家町と町人町との境目であった。
 2024年現在。江戸時代では呉服橋近く、今のTOKYO TORCH Parkにあたりに「道三堀」があり銭瓶橋が架かっていた。
2024年現在。江戸時代では呉服橋近く、今のTOKYO TORCH Parkにあたりに「道三堀」があり銭瓶橋が架かっていた。

道三堀は和田倉堀につながっていた船入り堀(運河 / 輸送路)で、徳川家康入封の際、居住区を整備した後、物資運搬路が優先事項であり、江戸で初めて造られた堀である。近くに幕府の侍医、曲直瀬道三の屋敷があったことがその名前の由来。
呉服橋門の南100mほどの所に北町奉行所跡がある。外堀(外濠川)の西岸で武家町、つまり呉服橋門内と呼ばれた地域にあった。町奉行は、寺社奉行、勘定奉行とともに徳川幕府三奉行のひとつ。1806年から幕末まで北町奉行所が置かれた。時代劇で有名な遠山景元は1840年~1843年まで当所で執務していた。
 一石橋、呉服橋あたりから日本橋川は外濠川へ分岐するが、外濠川は汐留川に合流し、溜池へ至る。そこが見附が置かれた江戸城の外堀である。
一石橋、呉服橋あたりから日本橋川は外濠川へ分岐するが、外濠川は汐留川に合流し、溜池へ至る。そこが見附が置かれた江戸城の外堀である。
 外堀通りの呉服橋交差点。この交差点名には呉服橋の名がついているが、実際、橋や門があった呉服橋見附は外堀通りから少し離れた西側に位置している。ここから一石橋が見えるが、かつての一石橋は日本橋川と外濠川の合流点で、2つの川の東岸を結んでいた橋である。一石橋の以南、外堀の外濠川は埋め立てられ東岸が外堀通り(東京都道405号外濠環状線)となっている。外濠川では戦後の瓦礫処理のために埋め立てられた経緯がある。
外堀通りの呉服橋交差点。この交差点名には呉服橋の名がついているが、実際、橋や門があった呉服橋見附は外堀通りから少し離れた西側に位置している。ここから一石橋が見えるが、かつての一石橋は日本橋川と外濠川の合流点で、2つの川の東岸を結んでいた橋である。一石橋の以南、外堀の外濠川は埋め立てられ東岸が外堀通り(東京都道405号外濠環状線)となっている。外濠川では戦後の瓦礫処理のために埋め立てられた経緯がある。
外堀通りは外堀跡のルートを探る目安にはなるが、注意点として神田を通っているルートはまったく外堀跡ではないし、それに外堀の流れに沿ってはいるが外堀跡の真上ではない事が多い。
呉服橋門~鍛冶橋門までの外堀(東京駅八重洲口)
 呉服橋門から鍛冶橋門までの外堀跡を巡る。東京駅八重洲口に面した外堀通りは、外濠川の東岸であり町屋側、駅前のロータリーあたりが外濠川の真上に位置する。
呉服橋門から鍛冶橋門までの外堀跡を巡る。東京駅八重洲口に面した外堀通りは、外濠川の東岸であり町屋側、駅前のロータリーあたりが外濠川の真上に位置する。
 八重洲口 タクシー降車場前の外壁モニュメントが、外濠川東岸の境界目安。この外壁モニュメントには、「鍛冶橋門」の北方で出土した石垣の石が使われている。ただし、この外濠川東岸は町屋側なので石垣があった位置ではない(本来、石垣があるのは武家屋敷のある西側)。石垣を用いるのは紛らわしい。
八重洲口 タクシー降車場前の外壁モニュメントが、外濠川東岸の境界目安。この外壁モニュメントには、「鍛冶橋門」の北方で出土した石垣の石が使われている。ただし、この外濠川東岸は町屋側なので石垣があった位置ではない(本来、石垣があるのは武家屋敷のある西側)。石垣を用いるのは紛らわしい。
 鍛冶橋門の北方で出土した外堀石垣(黄色い枠)。津山藩 松平三河守 上屋敷の東にあった外堀石垣であり、外濠川の西岸の石垣。現在の超高層ビル「パシフィックセンチュリープレイス丸の内」に位置する。石は先述の通り、外壁モニュメントとして八重洲口に移築再現された(赤枠)。
鍛冶橋門の北方で出土した外堀石垣(黄色い枠)。津山藩 松平三河守 上屋敷の東にあった外堀石垣であり、外濠川の西岸の石垣。現在の超高層ビル「パシフィックセンチュリープレイス丸の内」に位置する。石は先述の通り、外壁モニュメントとして八重洲口に移築再現された(赤枠)。
この外堀石垣は1636年の天下普請にて、丹波園部藩の小出吉親によって築かれた。石材は真鶴(神奈川県)産の安山岩で、角の部分は瀬戸内海沿岸から運ばれた花崗岩が使われている。
 江戸城の総構えでは東側に町屋が集中している(黄色系:武家町 / グレー:町屋)。神田橋門~幸橋門までの外堀が、武家町と町屋のはっきりした境界線となっている。よく武家町を門内、町屋を門外と表現される。
江戸城の総構えでは東側に町屋が集中している(黄色系:武家町 / グレー:町屋)。神田橋門~幸橋門までの外堀が、武家町と町屋のはっきりした境界線となっている。よく武家町を門内、町屋を門外と表現される。
次は鍛冶橋門へ向かう。
【 江戸城 探索TOP および目次 】



