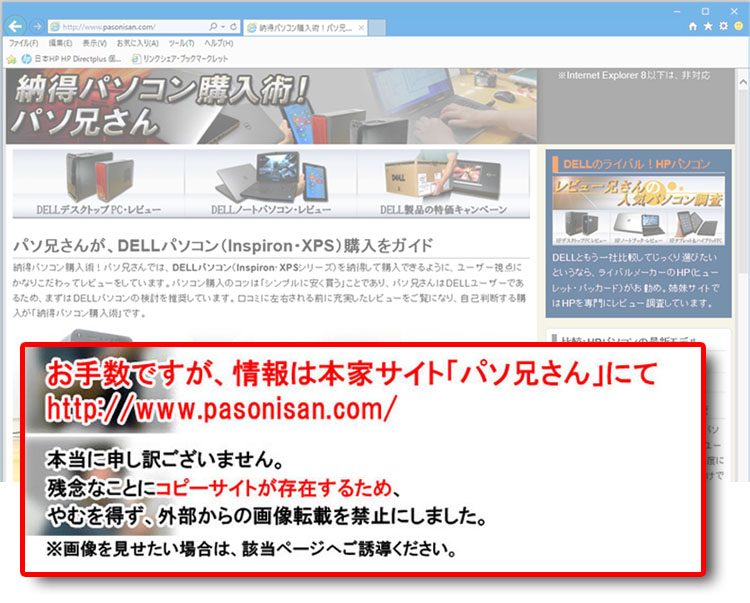

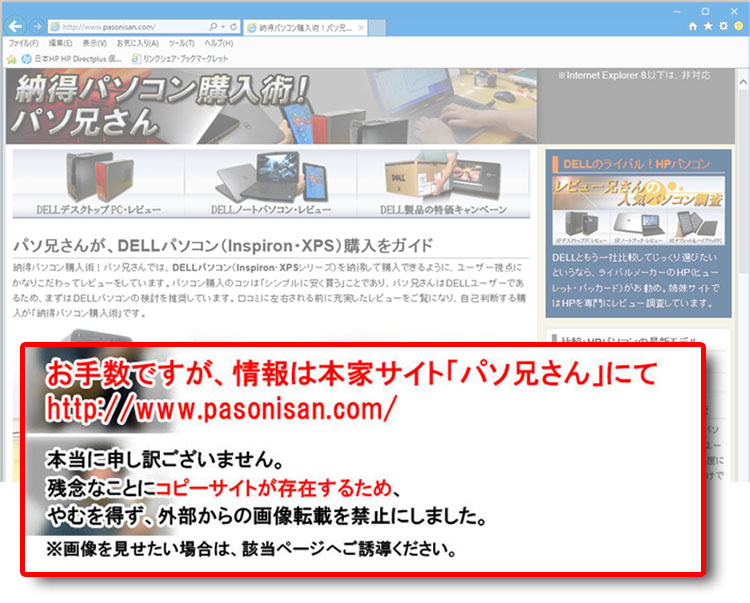
- HOME
- DELLパソコン・モバイル旅行記
- 東京都
- 江戸城(千代田区・中央区ほか)
江戸城 外堀の見附
市谷門と牛込堀
1636年、市谷門は津山藩 森長継によって築造された。1871年(明治4年)に枡形石垣と土橋を残して撤去され、のちに枡形石垣も撤去された。【 江戸城の外堀に配置された見附の位置 】
 1871年(明治4年)の市谷門。
1871年(明治4年)の市谷門。

写真でも記録されている明治初期の市谷門。橋の下に水位調節のために堰が確認できる。
 麹町警察署市ヶ谷見付交番の東隣、駐輪場の奥に、市谷門橋台の石垣がごく僅かに残されている。
麹町警察署市ヶ谷見付交番の東隣、駐輪場の奥に、市谷門橋台の石垣がごく僅かに残されている。
 囲いの石垣ではなく、4つほど並んだ黒っぽい石がそれ。
囲いの石垣ではなく、4つほど並んだ黒っぽい石がそれ。
 説明板はあるが、僅かすぎる史跡。
説明板はあるが、僅かすぎる史跡。
市谷門の土橋
 市谷門土橋の石垣。市谷門土橋は、現在の五番町・九段北四丁目と市谷田町・市谷八幡町を結んでいる。
市谷門土橋の石垣。市谷門土橋は、現在の五番町・九段北四丁目と市谷田町・市谷八幡町を結んでいる。
 橋の上からだと想像できない江戸城の遺構である。
橋の上からだと想像できない江戸城の遺構である。
 土橋なので堰が設けてある。
土橋なので堰が設けてある。
 市谷門の北西、市ヶ谷台に「防衛省市ヶ谷庁舎」があるが、かつて御三家・尾張徳川家の上屋敷があったところである。外堀の外側、見附の門外、つまり城外に位置している。明暦の大火(1657年)では、外堀の内側(門内)の大半が焼失した経緯があり、御三家の上屋敷は江戸城外(門外)に移転している。
市谷門の北西、市ヶ谷台に「防衛省市ヶ谷庁舎」があるが、かつて御三家・尾張徳川家の上屋敷があったところである。外堀の外側、見附の門外、つまり城外に位置している。明暦の大火(1657年)では、外堀の内側(門内)の大半が焼失した経緯があり、御三家の上屋敷は江戸城外(門外)に移転している。
陸軍士官学校跡を経て参謀本部(大本営陸軍部)だった頃は、1946年(昭和20年)に極東国際軍事裁判法廷で利用された。戦後、陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地になるが、1970年に三島事件が起きている。
 北東の牛込門方面(飯田橋駅方面)で、市谷門と牛込門の間の外堀。ここは本来であれば牛込堀であるが、明治期、堀の間に新見附橋が新たに架橋されたため、この南半分を「新見附堀」と呼ぶ場合がある。しかし江戸時代にあった堀の区画ではないので、あまり呼びたくはない名称である。牛込堀内 新見附堀とでもしておくか。
北東の牛込門方面(飯田橋駅方面)で、市谷門と牛込門の間の外堀。ここは本来であれば牛込堀であるが、明治期、堀の間に新見附橋が新たに架橋されたため、この南半分を「新見附堀」と呼ぶ場合がある。しかし江戸時代にあった堀の区画ではないので、あまり呼びたくはない名称である。牛込堀内 新見附堀とでもしておくか。
 新見附堀とJR総武線。奥に市ヶ谷橋が見える。新見附堀の底には東京メトロ有楽町線 市ヶ谷駅があって、景色を観るだけでは想像もつかない。
新見附堀とJR総武線。奥に市ヶ谷橋が見える。新見附堀の底には東京メトロ有楽町線 市ヶ谷駅があって、景色を観るだけでは想像もつかない。
 JR総武線に乗っていて「かねふく」の看板が見えたら、「新見附堀を走っているのか・・すぐに市ヶ谷駅だ」と認識できる。
JR総武線に乗っていて「かねふく」の看板が見えたら、「新見附堀を走っているのか・・すぐに市ヶ谷駅だ」と認識できる。
牛込堀
先述の通り、明治時代、牛込堀の中間に新見附橋が架けられたため、明治期以降は南側を新見附堀、北側を牛込堀と呼ぶことがある。江戸城の遺構としては牛込堀なので一部でも「新見附堀」と呼びたくはないものだが、ここでの説明は便宜上分けて呼ぶことにする。新見附というものの、江戸時代に見附が存在したわけでもなく、紛らわしいだけの受け入れ難い名称だ。
 牛込堀は明治時代に新見附堀と牛込堀に分かれた。
牛込堀は明治時代に新見附堀と牛込堀に分かれた。
 牛込門へ向かって土手を歩くが、突き当りに新見附橋が見える。先述の通り、ここは牛込堀内の新見附堀。
牛込門へ向かって土手を歩くが、突き当りに新見附橋が見える。先述の通り、ここは牛込堀内の新見附堀。
 新見附堀の北端。そして新見附橋の土橋の様子。
新見附堀の北端。そして新見附橋の土橋の様子。
 新見附堀の土橋で北側。仕切られた以上、この先から牛込堀と呼ばれる。
新見附堀の土橋で北側。仕切られた以上、この先から牛込堀と呼ばれる。
 明治中頃、牛込橋と市谷橋の中間点を埋め立てて新見附橋が架けられた。旧麹町区と旧牛込区の住民が行き来する橋であった。鋼橋である現在の新見附橋は昭和4年(1929)に架橋された。
明治中頃、牛込橋と市谷橋の中間点を埋め立てて新見附橋が架けられた。旧麹町区と旧牛込区の住民が行き来する橋であった。鋼橋である現在の新見附橋は昭和4年(1929)に架橋された。
 新見附橋近辺の土手。
新見附橋近辺の土手。
 新見附橋の北に続く牛込堀。400m先の飯田橋駅が見えるが、そこが牛込門。
新見附橋の北に続く牛込堀。400m先の飯田橋駅が見えるが、そこが牛込門。
 牛込堀を眺めながら北方の牛込門を目指す。東側には法政大学のキャンパスがある。
牛込堀を眺めながら北方の牛込門を目指す。東側には法政大学のキャンパスがある。
 牛込橋(JR線の真上)から眺めた牛込堀。
牛込橋(JR線の真上)から眺めた牛込堀。
 同じく、牛込橋から牛込堀を臨む。
同じく、牛込橋から牛込堀を臨む。
 高い位置から。
高い位置から。
 昭和初期の牛込堀と土塁(土手)
昭和初期の牛込堀と土塁(土手)
【 江戸城 探索TOP および目次 】



