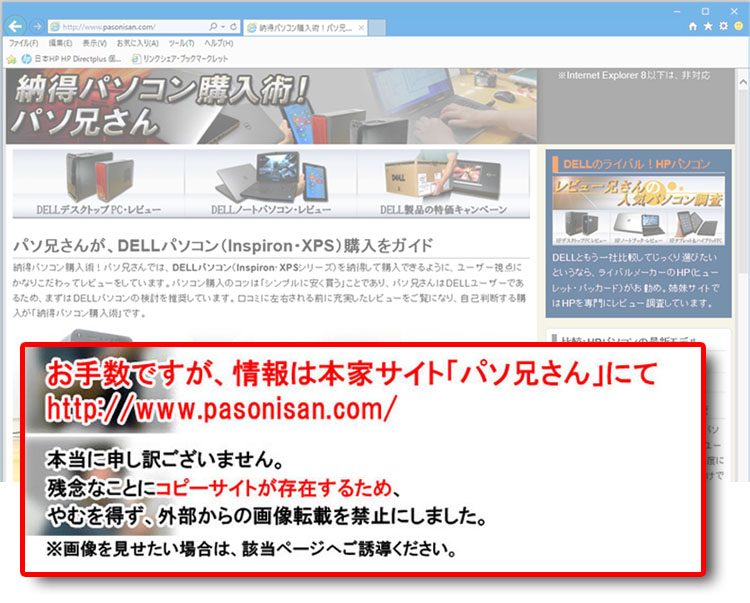

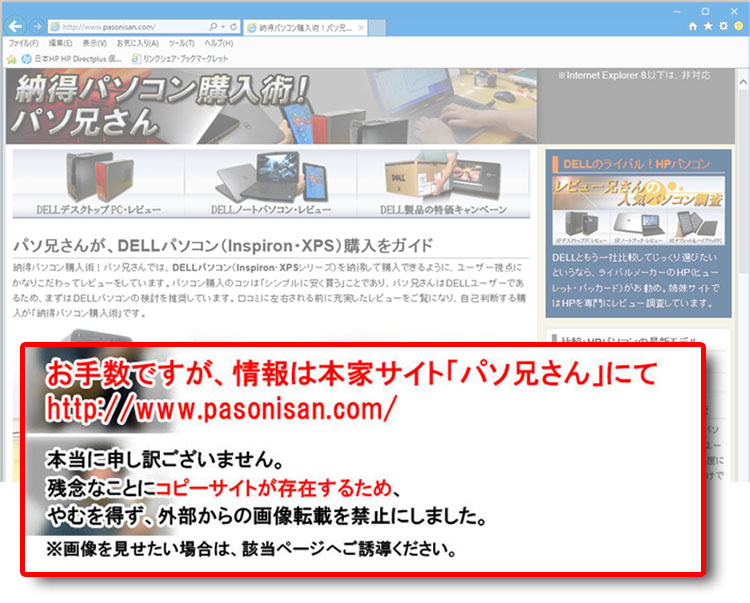
- HOME
- DELLパソコン・モバイル旅行記
- 東京都
- 江戸城(千代田区・中央区ほか)
江戸城 外堀の見附
牛込門
牛込門は1636年、徳島藩 蜂須賀忠英により築造された。門の北西(牛込方面)には、かつて小田原北条氏家臣で牛込氏が居城していた牛込城があり、牛込門という名称の由来と考えられる。四谷から牛込にかけては神田川支谷の広い谷が広がっており、その地形を外堀に利用している。堀幅が広く、急峻な土手を築いており防御性が高い。江戸城北の丸 田安門を起点とする上州道の出口といった交通の要衝地で、周辺には楓が植えられ紅葉時は見ごたえがあったという。【 江戸城の外堀に配置された見附の位置 】
 神楽坂側から観た牛込見附(1871年・旧江戸城写真帖牛込見附図)。堀に面している土塁や、土橋の堰、荷揚げと思われる船が確認できる。手前の堀は、昭和47年の市街地再開発事業で埋め立てられてしまった飯田濠のようだ。
神楽坂側から観た牛込見附(1871年・旧江戸城写真帖牛込見附図)。堀に面している土塁や、土橋の堰、荷揚げと思われる船が確認できる。手前の堀は、昭和47年の市街地再開発事業で埋め立てられてしまった飯田濠のようだ。

牛込門跡はJR飯田橋(西口)のあたり。土手道を歩いてきたのなら、枡形石垣のところに到着する。国指定史跡の外堀跡は赤坂門からここまでの範囲である。
現在のJR飯田橋駅ホームは、2020年に従来の位置から200mほど西に移設している。江戸時代であれば、牛込堀と飯田濠の中間。1894~1928年までは甲武鉄道(JR 中央線の前身)の「牛込駅」があった場所である。1928年に牛込駅と近くの飯田町駅が統合され、両駅ホームの中間に「飯田橋駅」が開業した。この従来の飯田橋駅ホームは外堀に沿った急カーブであったため、停車した電車とホームの隙間が広く、転落事故が起きていた。
1871年(明治4年)に門は撤去された。明治35年には石垣の大部分が撤去されたが、一部は残っており、江戸城外堀の見附のなかでも比較的当時の面影を残している。
 牛込見附の構造図。石垣を方形にめぐらし(枡形石垣)、土橋から入る冠木門(高麗門)、渡櫓と一体化した大御門の二重の門を配置している。これを枡形門という。土橋を渡り冠木門を通り枡形石垣に侵入した敵を渡櫓や石垣の上から一斉攻撃する仕組みである。
牛込見附の構造図。石垣を方形にめぐらし(枡形石垣)、土橋から入る冠木門(高麗門)、渡櫓と一体化した大御門の二重の門を配置している。これを枡形門という。土橋を渡り冠木門を通り枡形石垣に侵入した敵を渡櫓や石垣の上から一斉攻撃する仕組みである。
 橋を渡ると冠木門があったわけだ。この奥が江戸城内。
橋を渡ると冠木門があったわけだ。この奥が江戸城内。
 もうワンショット。
もうワンショット。
牛込門の櫓台
 櫓台南西側の枡形石垣。
櫓台南西側の枡形石垣。
 南西側の土塁と櫓台
南西側の土塁と櫓台
 飯田橋駅ホーム(外堀の中)から見た様子。
飯田橋駅ホーム(外堀の中)から見た様子。
 当時だったら、大御門の目の前である。
当時だったら、大御門の目の前である。
 南東(江戸城 北の丸・田安門の方面)の枡形石垣跡。タイルのデザインを変えて跡地が判るようになっている。
南東(江戸城 北の丸・田安門の方面)の枡形石垣跡。タイルのデザインを変えて跡地が判るようになっている。
 手前の石垣は無くなったが、この頂きに渡櫓が載っていたわけだ。横断歩道を越えた先にも飛び地のようにタイル・デザインが続いている(石垣跡の規模は横断歩道を越えているが、横断歩道までデザインを変えられない)。
手前の石垣は無くなったが、この頂きに渡櫓が載っていたわけだ。横断歩道を越えた先にも飛び地のようにタイル・デザインが続いている(石垣跡の規模は横断歩道を越えているが、横断歩道までデザインを変えられない)。
 北東の枡形石垣、飯田橋駅のほうから観た様子。
北東の枡形石垣、飯田橋駅のほうから観た様子。
 北東の枡形石垣、道路側(東側)からみた様子。
北東の枡形石垣、道路側(東側)からみた様子。
 富士見教会の建て替えで発見された、牛込門の基礎として地中に設置された石垣石。「~阿波守内」という銘文があり蜂須賀家が普請した裏付けになっている。
富士見教会の建て替えで発見された、牛込門の基礎として地中に設置された石垣石。「~阿波守内」という銘文があり蜂須賀家が普請した裏付けになっている。
牛込橋と堰
 当時の牛込橋は土橋であった。真田堀から牛込までの堀は、牛込に向かって段々と水位が低くなっていくため、牛込見附の土橋には堰を設けて水堀の水位を調整していた。
当時の牛込橋は土橋であった。真田堀から牛込までの堀は、牛込に向かって段々と水位が低くなっていくため、牛込見附の土橋には堰を設けて水堀の水位を調整していた。
 上から牛込橋。
上から牛込橋。
 牛込橋からセントラルパークを結んでいる橋のあたりに堰(落口)の名残りを感じる。
牛込橋からセントラルパークを結んでいる橋のあたりに堰(落口)の名残りを感じる。
 堰から水が流れている様子。
堰から水が流れている様子。
 上から堰を見る。
上から堰を見る。
 牛込堀と牛込橋と堰。
牛込堀と牛込橋と堰。
 堰の水路面で使用されていた石材が、駅舎工事にあたり発掘された。
堰の水路面で使用されていた石材が、駅舎工事にあたり発掘された。
 牛込門に通じる交通の要衝、神楽坂。江戸城外であるこの坂の周辺には、善國寺(毘沙門天)・若宮八幡・赤城神社など多くの寺社が散在する。明治時代には、城外(新宿区側)の武家屋敷が空き家となるが芸姑置屋や料亭になり、大正時代には隆盛を誇った「神楽坂花街」が形成された。関東大震災後は日本橋や銀座から商人が流入し夜店が多くなり、一時は「山の手銀座」とも呼ばれた。
牛込門に通じる交通の要衝、神楽坂。江戸城外であるこの坂の周辺には、善國寺(毘沙門天)・若宮八幡・赤城神社など多くの寺社が散在する。明治時代には、城外(新宿区側)の武家屋敷が空き家となるが芸姑置屋や料亭になり、大正時代には隆盛を誇った「神楽坂花街」が形成された。関東大震災後は日本橋や銀座から商人が流入し夜店が多くなり、一時は「山の手銀座」とも呼ばれた。
一方、城内(千代田区側)の武家屋敷跡は学校などが建てられた。
名称の由来に諸説ある。高田穴八幡の祭礼で神輿が通るときに神楽を奏した、「若宮八幡の社」の神楽の音がこの坂まで聞こえた、津久戸明神(築土神社)が移転した時に神楽を奏すると容易に御輿を担いで上ることが出来たなど。
牛込見附とそれに連なる土塁
 櫓台と連なっている牛込見附の土塁(南側)。かつて牛込駅の駅舎があった場所でもある。駅舎跡は土塁に食い込むようにして薬局が建っており、駅舎の石垣が残されている。飯田橋駅ホームもここまで延びており、移設工事中では「牛込駅の復活か」などと噂されたとか。
櫓台と連なっている牛込見附の土塁(南側)。かつて牛込駅の駅舎があった場所でもある。駅舎跡は土塁に食い込むようにして薬局が建っており、駅舎の石垣が残されている。飯田橋駅ホームもここまで延びており、移設工事中では「牛込駅の復活か」などと噂されたとか。
 牛込駅の駅舎跡。土塁に食い込んでいる薬局と飲食店。
牛込駅の駅舎跡。土塁に食い込んでいる薬局と飲食店。
 土塁を固めている石垣は、牛込駅の駅舎の名残りのようだ。
土塁を固めている石垣は、牛込駅の駅舎の名残りのようだ。
 今度は牛込見附の北側の土塁。1915年、4代目広重(菊池貴一郎)が書き留めた幕末から明治期の様子。
今度は牛込見附の北側の土塁。1915年、4代目広重(菊池貴一郎)が書き留めた幕末から明治期の様子。
 その北東に延びている土塁のイメージが復元されている。かつて芝で覆った土手に松杉の苗を二列植えて、土留と遮蔽の役割を担わせたという。明治期の道路拡張や鉄道敷設により土手は数度に渡り削り取られてきたが、地中には江戸時代の土塁の一部が残っているそうだ。
その北東に延びている土塁のイメージが復元されている。かつて芝で覆った土手に松杉の苗を二列植えて、土留と遮蔽の役割を担わせたという。明治期の道路拡張や鉄道敷設により土手は数度に渡り削り取られてきたが、地中には江戸時代の土塁の一部が残っているそうだ。
 飯田橋駅二階テラス「史跡眺望デッキ」から観た復元土塁
飯田橋駅二階テラス「史跡眺望デッキ」から観た復元土塁
 復元だが無いよりはマシか・・・
復元だが無いよりはマシか・・・
【 江戸城 探索TOP および目次 】



