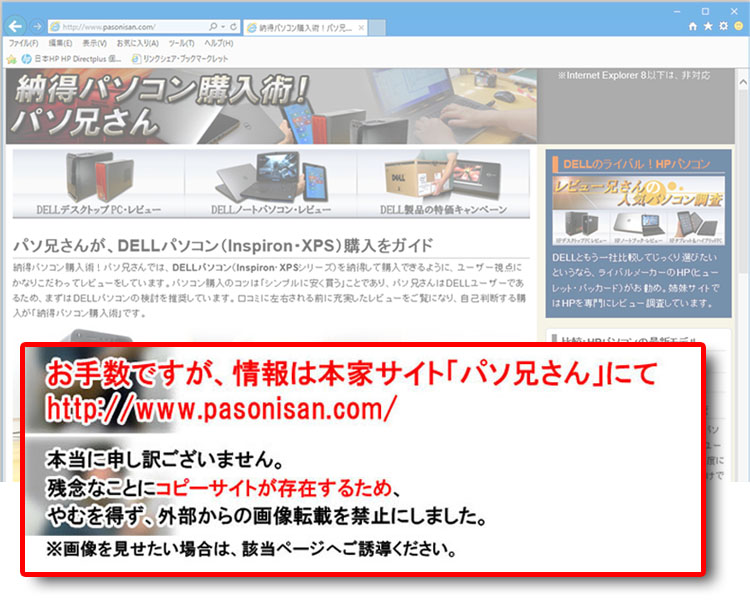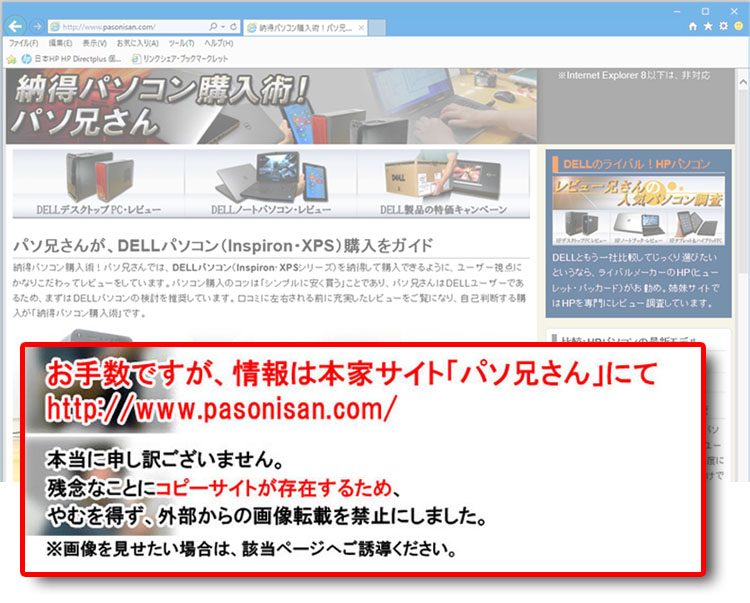

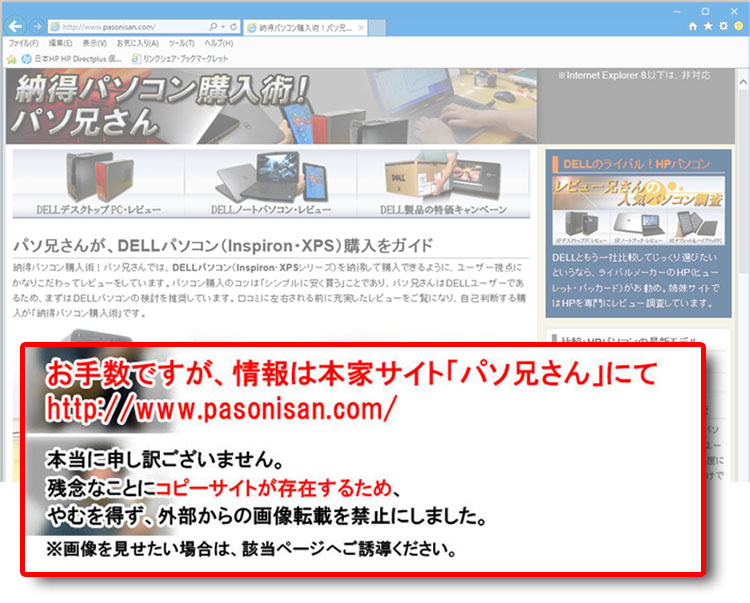
戦国期の城下町の名残を探す
須賀川城にまつわる城館・史跡
須賀川市の探訪にて赴いた、城館・砦跡のまとめ。まずは市立博物館にあった須賀川城攻防図を参考に、城館、古戦場、砦、布陣などを確認して現地を訪問してみた。また須賀川城から自転車で行動できる範囲で、近辺の城館跡もチェックしている。資料として日本城郭大系を概ね参考にしている。なお、おまけとして須賀川城とはあまり関係ない近隣の史跡もまとめている。
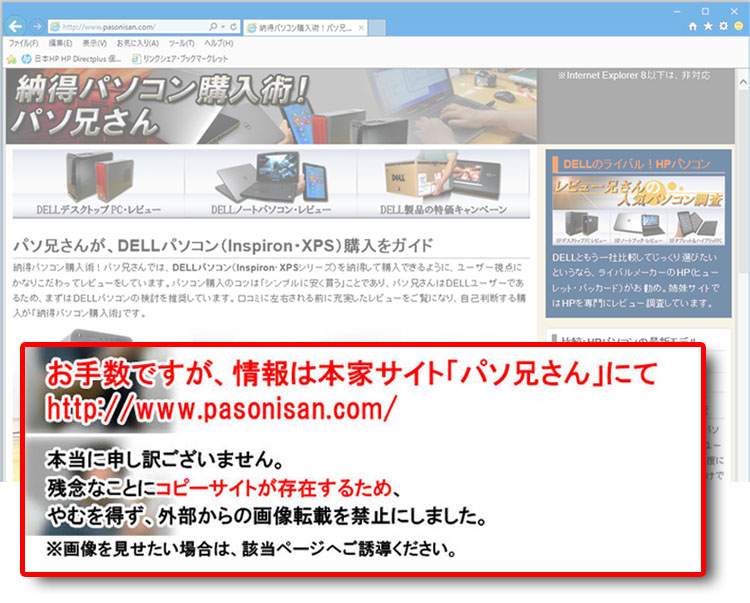 須賀川城の近隣には、二階堂氏ゆかりの城館が多い。当方、須賀川城跡を起点に自転車でこの範囲を移動するため、結構辛い登城となっている。参照:文化遺産総合活用推進事業の須賀川市歴史文化基本構想(2019年3月29日)による歴史・文化資源一覧。
須賀川城の近隣には、二階堂氏ゆかりの城館が多い。当方、須賀川城跡を起点に自転車でこの範囲を移動するため、結構辛い登城となっている。参照:文化遺産総合活用推進事業の須賀川市歴史文化基本構想(2019年3月29日)による歴史・文化資源一覧。
須賀川・郡山市・鏡石町の歴史探訪記録
- 須賀川城と二階堂氏について
- 須賀川城の攻防図と古戦場~二階堂氏VS伊達政宗。各家臣の配置と、今の古戦場跡を巡る!
- 旧記事(ボツ記事): 須賀川城攻防戦の史跡を巡る
- 第一次 須賀川城(愛宕山城 / 岩瀬山城) ~かつて二階堂氏が居城としていた一帯(現・翠ケ丘公園)
関連史跡: 愛宕山城の主郭、新池、琵琶池、ビワ首山(御隠居岳)、十日山、妙見山、栗谷沢の滝、五老山、南館、保土原館、守谷館 - 稲村城(新城館)~二階堂氏が岩瀬郡を支配した、鎌倉時代初期の拠点
- 稲村御所~関東公方 足利満兼の命を受けた足利満貞が下向して、御所として使用
- 篠川御所~篠川公方・足利満直の居城。ちなみに弟の満貞は稲村公方
- 下宿御所館~二階堂氏に領主の座を譲ってから移住した岩瀬氏の城館
- 蓮池跡(金徳寺と十念寺あたり)~須賀川城水堀の水源となっていたと思われる
- 千本館~(現:須賀川ボタン園)二階堂氏の庭園跡と伝えられている
- 和田城、伏見館~二階堂四天王で、実質的な総大将を務めた須田盛秀の居城
- 市野関館(万力館)~館主は二階堂氏家臣の須田秀泰であるが、彼には江藤万力という家臣がいた
- 平館、蛭館(東館)、西館、石見館~須賀川東部の館
- 滑川館(柏木城)~滑川は多賀城への通過地点であり、古代より岩瀬郡の重要な防衛線
- 越久館~城主は稲村二階堂の家臣・矢部豊前。会津中路への要衝
- 一夜館~一夜館公園の北西部に土塁の遺構。伊達軍が一夜で土塁を築いたという言い伝えがある。
- 江泉館~稲村城の東南の守りをとして新造された城館
- 松山城~田村氏・蘆名氏の同盟軍から攻撃を受けたりと、近隣大名での攻防戦となっている
- 今泉城~二階堂家臣・岩瀬 浜尾氏の居城、人取橋合戦では二階堂ら連合軍の集結地
- 長沼城~軍事や交通で要地であるため、蘆名氏と二階堂氏でたびたび争いが起きている
- 守山城~三春田村氏が本城としていたが、三春城へと居城を移した
- 上人壇廃寺跡~奈良・平安時代の寺院跡。見た目は残念な国指定史跡
- 宇津峰城(うづみねじょう)~南朝方・北畠顕信が率いた拠点で、天然の要害を利用した山城
- 方八丁館~南ノ原口の出城、須賀川城の南の防衛
- 陣馬山(山寺城)~伊達政宗の本陣
- 高久田館(鹿島館)~城主は箭部紀伊守、高久田義兼らが居住。鹿島神社を城に勧請した
- 常松館(岩渕館)~二階堂家臣・常松氏の居城
- 日本三大火祭の松明あかしに参加~須賀川二階堂氏の慰霊祭
- 江持洞門~鬼亀こと佐久間亀五郎が手掘りによって貫通させた洞門
小規模記事
以下の史跡は記事規模が小さいため、このページにて集約している。※このページ内でスキップ
- 岩瀬森館~現・鎌足神社。藤原義政が1185年に岩瀬郡四ッ清水城として在城したとある
- 金剛院~須田盛秀の先祖代々菩提寺
- 片岸館~そもそも城郭なのか怪しい
- 籾山御所宮館~籾山は当時では要衝地。お偉い方の館でもあったのだろうか。
- 古館~館主は二階堂氏の重臣・須田秀信の5男、須田源蔵。古くは古墳時代の遺跡跡。
- 探索予定の史跡
要害館、舘ケ岡城、新田館、横田陣屋、桙衝館、矢田野城、大久保館、大里城、関場山館、浜尾館、木之崎館、乙字ヶ滝と上代館、木舟城(狸森城)、矢柄城、細桙城、刑部内館・松が館、成山館、雨田館、滑津館、しどみ柄館、弥六内館、泉田館跡、松塚館、城の内館、岡の内館、磯部館、宝徳館、臥竜城、蛇山館、前田川館、日照田館
岩瀬森館(四ッ清水城・岩瀬森古墳・鎌足神社)
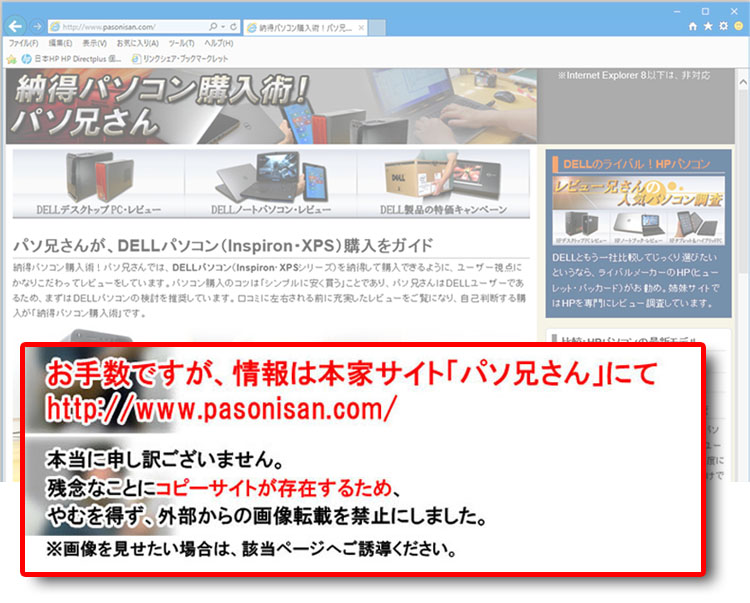
須賀川駅から南東の位置にみえる小さな森が鎌足神社。かつて岩瀬森館と呼ばれたところだ。その名の通り藤原鎌足に起因する神社だが、現地案内板によると「藤原義定の次男、義政が1185年に岩瀬郡四ッ清水城に在城し、鎌足霊を奉斎した」とある。この四ッ清水城がこの岩瀬森だという。二階堂氏は藤原氏の流れを組むので、何らかの関係性があったことは間違いない。もとは古墳だったようで、岩瀬森古墳跡とも呼ばれる。
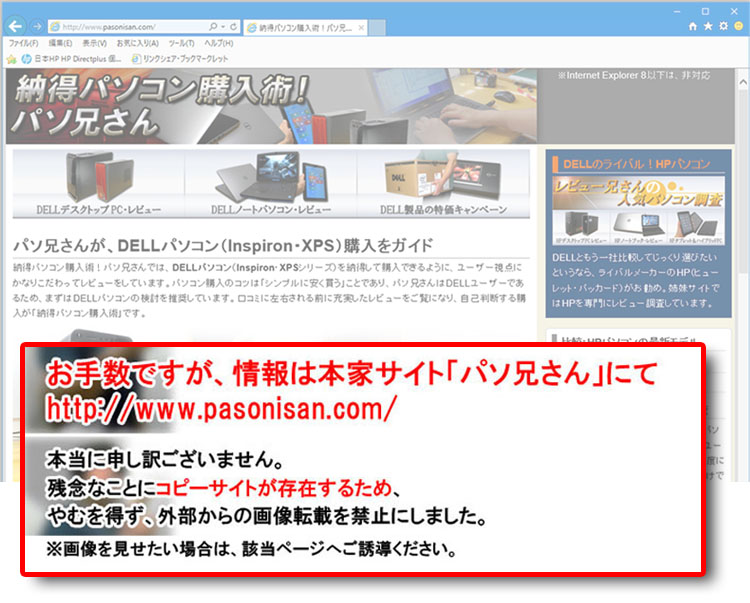
岩瀬森館の西側に「釈迦堂川花火通り」が開通しているが、1970年代の航空写真を見ると南北に伸びた池が確認できるので、水濠が存在していたようだ。そして岩瀬森館の東側では、北西に位置する上人檀廃寺跡に続く官道(東山道-とうさんどう)が縦断していたと推測されている。さらに東側で釈迦堂川の左岸(東部環状線あたり)はうまや遺跡だそうだ。岩瀬森館はちょっとした森になっており周囲には民家が並ぶ。須賀川城から見て釈迦堂川の外側にあるため、伊達軍の部隊が布陣したかもしれない。
金剛院 (須田盛秀・先祖代々の菩提寺)
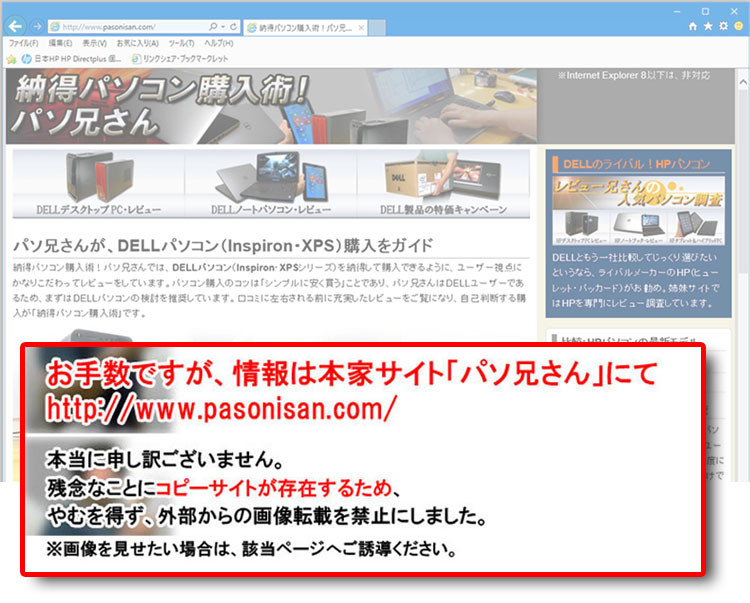 曹洞宗の寺院である堅固山・金剛院(須賀川市和田宿62)。伊達政宗との須賀川城攻防戦(1589年)では、実質的な総大将を務めた二階堂家臣・須田盛秀の先祖代々の菩提寺。入り口に「須田美濃守秀行公開創道場」とある。須田秀行は須田盛秀の養父とされ、和田城主であった。須賀川城攻防戦の前に死去している。
曹洞宗の寺院である堅固山・金剛院(須賀川市和田宿62)。伊達政宗との須賀川城攻防戦(1589年)では、実質的な総大将を務めた二階堂家臣・須田盛秀の先祖代々の菩提寺。入り口に「須田美濃守秀行公開創道場」とある。須田秀行は須田盛秀の養父とされ、和田城主であった。須賀川城攻防戦の前に死去している。
須賀川落城後、須田盛秀は居城であった和田城に火をかけ、常陸国に落ちのびた。佐竹義宣に仕え、茂木城主、角館城、横手城の城代となった。須田盛秀の墓は晩年を過ごした秋田県横手市の金剛山天仙寺にある。享年96だという。
徳川家臣・本多正純が、宇都宮城に釣天井を仕掛けて徳川秀忠の暗殺を図った嫌疑の事件(1622年)が起った。本多正純は改易させられ流罪先の横手城で生涯を終えたが、このとき、横手城城代の須田盛秀が監視役を務めた。
片岸館
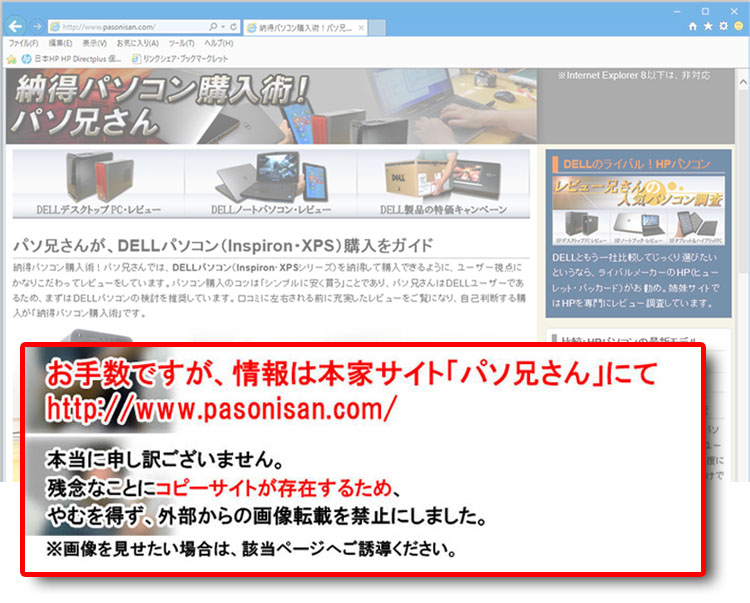 存在が眉唾ものであるが、須賀川市大字仁井田字片峰にある片岸館へ行ってみた(2016年8月)。地名が片峰なので片峰館じゃないのかと思うのだが、そもそも城郭なのかが怪しい。ただ、地図には切通とあるので、その可能性は否定できない。
存在が眉唾ものであるが、須賀川市大字仁井田字片峰にある片岸館へ行ってみた(2016年8月)。地名が片峰なので片峰館じゃないのかと思うのだが、そもそも城郭なのかが怪しい。ただ、地図には切通とあるので、その可能性は否定できない。
仁井田小学校のすぐ西側の墓地が目印になるので発見しやすい。西に森、東に墓地という低い丘陵地であり、間を突き抜けている道路は堀跡だったのか、新たにぶち抜いたのかは不明。墓地は削平したと考えられる。
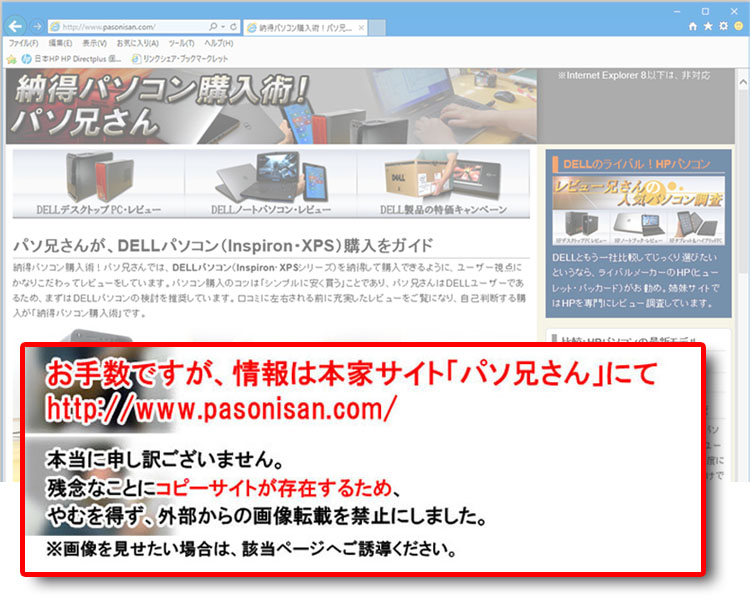 堀切(仮)の脇から横堀のような通路があり入ってみたが、墓地への小路だった。新たに道を作るならわざわざ堀にする必要がないので、堀跡に手を加えたと思うのだが、もはや遺構のレベルではない。それにしても、夜であれば肝試しになりそうな雰囲気だった。突入する前にこの暗がりからオジさんがひょこっと現れてびっくりしたが、中に入ると立ち小便の形跡があった。後々、親戚に聞いたら、墓参りで立ち小便する人が多々いるらしい。ここの南600mのところに浜尾氏の館跡(現・常林寺)があるので、浜尾氏と関係があるのかもしれない。
堀切(仮)の脇から横堀のような通路があり入ってみたが、墓地への小路だった。新たに道を作るならわざわざ堀にする必要がないので、堀跡に手を加えたと思うのだが、もはや遺構のレベルではない。それにしても、夜であれば肝試しになりそうな雰囲気だった。突入する前にこの暗がりからオジさんがひょこっと現れてびっくりしたが、中に入ると立ち小便の形跡があった。後々、親戚に聞いたら、墓参りで立ち小便する人が多々いるらしい。ここの南600mのところに浜尾氏の館跡(現・常林寺)があるので、浜尾氏と関係があるのかもしれない。
籾山御所宮館
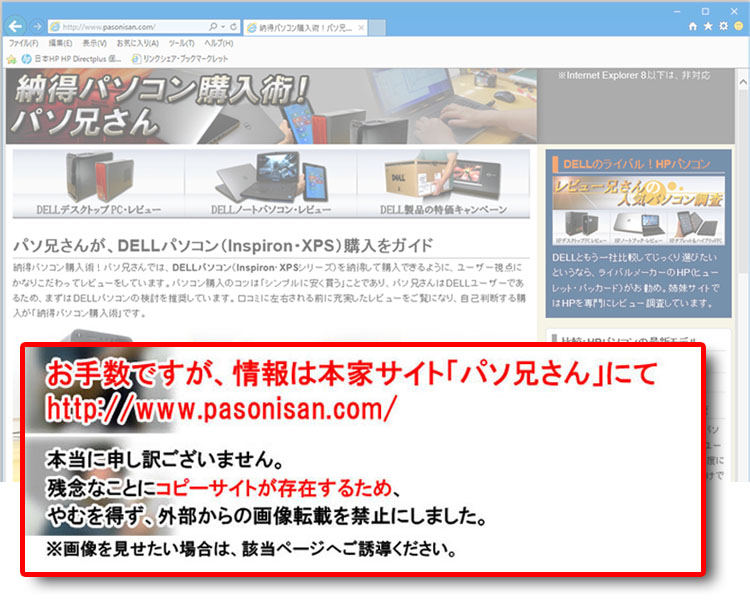 須賀川市森宿御所宮にある籾山御所宮館。滑川と東北新幹線が交差する場所で、地名を頼りに訪れてみたが、どこを見るべきなのかさっぱりわからない。棚田なのか郭なのかわからないところと、その丘陵地を撮影しておいた。
須賀川市森宿御所宮にある籾山御所宮館。滑川と東北新幹線が交差する場所で、地名を頼りに訪れてみたが、どこを見るべきなのかさっぱりわからない。棚田なのか郭なのかわからないところと、その丘陵地を撮影しておいた。
日本城郭大系によると、会津街道は往古、須賀川から中宿、山寺、籾山、越久、袋田、矢沢、畑田、住田、七ツ石を経て諏訪峠を抜け、会津中路に通じていたという。籾山は当時では要衝だったみたい。御所というくらいだから、お偉い方の館でもあったのだろうか。
古館
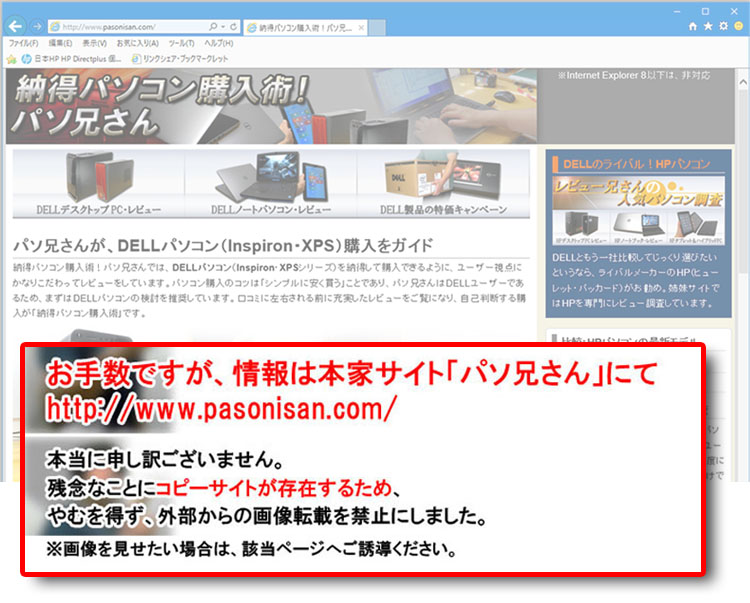 須賀川市の東部を流れる阿武隈川の西岸台地にあった「古館」は、須賀川市古館に位置する。古い住所では須賀川市中宿字古館なので「中宿古館」と日本城郭大系で書かれている。
須賀川市の東部を流れる阿武隈川の西岸台地にあった「古館」は、須賀川市古館に位置する。古い住所では須賀川市中宿字古館なので「中宿古館」と日本城郭大系で書かれている。
館主は二階堂氏の重臣・須田秀信の5男、須田源蔵で、江持と堤を領していたという。ゆえに城館の別名は「源蔵館」。古くは古墳時代の遺跡跡のようで、古墳跡が7基発見されている。阿武隈小学校のある位置と見ていたが、日本城郭大系によれば、40年も前の話になるが「平坦な畑になっている」と記されている。ピンポイントではわからなかったが、この河岸段丘の台地上にあったようだ。
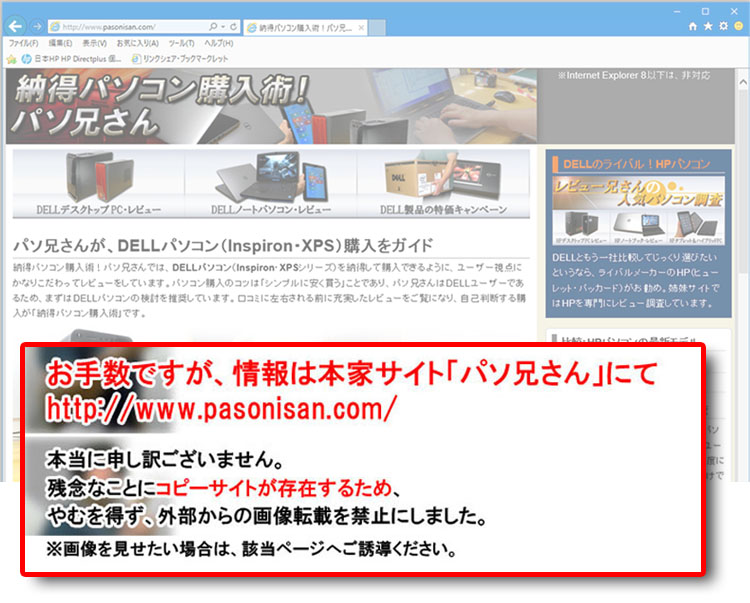 古館は、川に面して絶壁になっている、河岸段丘の丘陵地(比高20m)に築かれた城館である。現在では新町街道と呼ばれているが、かつて須賀川城への進入路である田村口であり、その要衝地であったようだ。調査により、間口60m、奥行き8mの大規模な屋敷だったことが分かっている。100m四方の平場で中央に井戸跡があったという。
古館は、川に面して絶壁になっている、河岸段丘の丘陵地(比高20m)に築かれた城館である。現在では新町街道と呼ばれているが、かつて須賀川城への進入路である田村口であり、その要衝地であったようだ。調査により、間口60m、奥行き8mの大規模な屋敷だったことが分かっている。100m四方の平場で中央に井戸跡があったという。
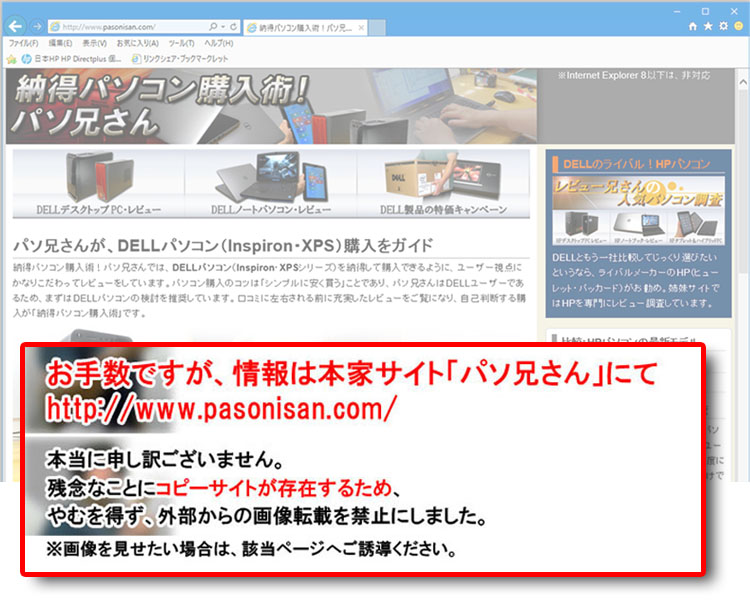 丘陵地の上から阿武隈川を見下ろす。
丘陵地の上から阿武隈川を見下ろす。
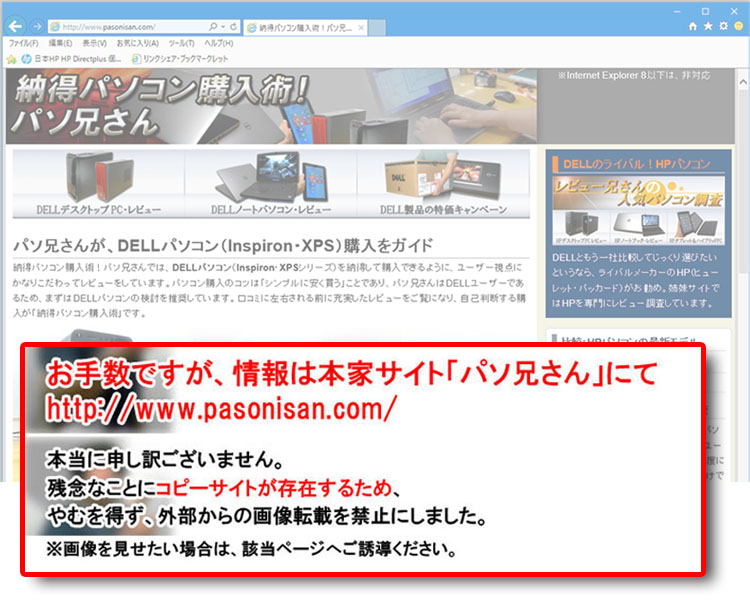 古館のある丘陵地直下の阿武隈川。
古館のある丘陵地直下の阿武隈川。
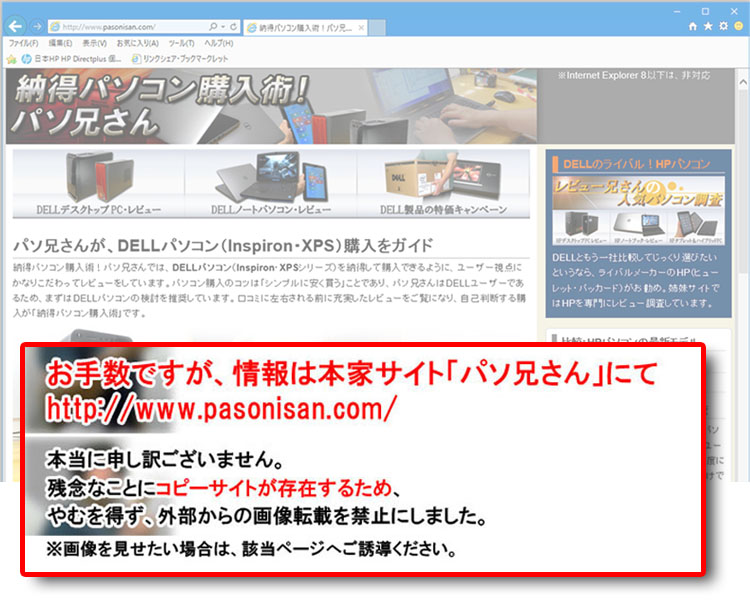 須賀川城攻防図に、古館が描かれている。田村口というのは、現在の新町街道(54号線)
須賀川城攻防図に、古館が描かれている。田村口というのは、現在の新町街道(54号線)
取材予定地リスト
以下、取材予定
要害館
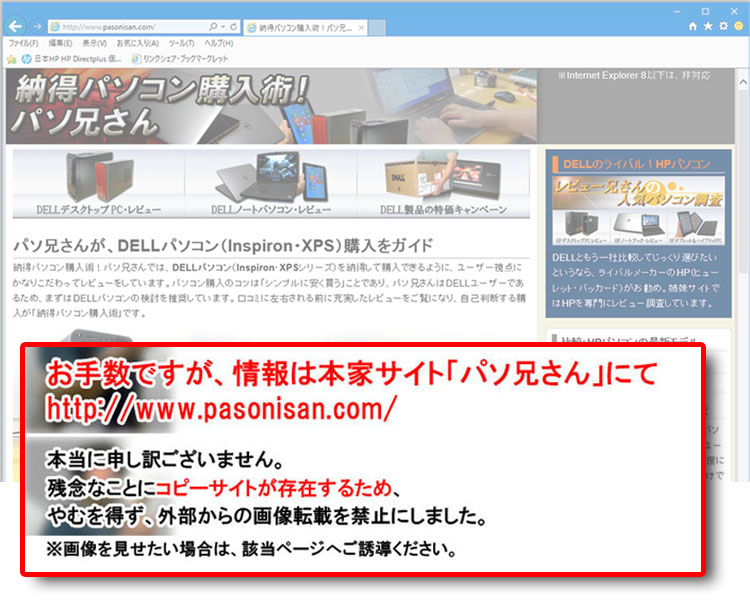 詳細不明。須賀川市の史跡上人壇廃寺跡保存活用計画書の「埋蔵文化財包蔵地」によれば、中宿公会堂の南東側。空き地でしか無いので、遺構は期待できない。
詳細不明。須賀川市の史跡上人壇廃寺跡保存活用計画書の「埋蔵文化財包蔵地」によれば、中宿公会堂の南東側。空き地でしか無いので、遺構は期待できない。
舘ケ岡城
須賀川市舘ケ岡舘山に位置する。現在は、市指定史跡「舘ケ岡磨崖仏及び供養碑群」 となっており、舘ケ岡地区を流れる滑川の南岸で、向山丘陵の西崖面にある。和田大仏と並ぶ岩瀬地方の磨崖仏で、安山岩の崖面を彫って造られている。天長元年(824年)の記年銘が彫られており、像の高さは約2.2m、肩幅約1.2m (和田大仏よりやや小柄)。この向山丘陵は中世、二階堂家臣・須田氏の居城として使われたという。
新田館
須賀川市仁井田舘内(常林寺があるところ)に新田館はあった。岩瀬西部衆の浜尾氏の館跡地。
1449年に常林寺が浜尾氏によって開基されたが、二階堂氏滅亡後は、新田館の跡地に移されたと伝わっている。※願成寺を新田館とする記述もあるが、すかがわ広報誌(1981年)では常林寺と書かれている。
二階堂氏家臣・浜尾種泰は新田館を居館とし、新田開発および町割りを行った。もともとは誉田(ぼんた)村だったそうだが、仁井田の村名の起源となった。1449年に常林寺が浜尾氏によって開基されたが、二階堂氏滅亡後は、浜尾氏館跡地に移されたと伝わっている。(仁井田神社の祭神は誉田別命(ホンダワケノミコト)だったので、もとは誉田村だったのであろう)。
横田陣屋
横田陣屋は須賀川市横田字北之後にあった陣屋跡。護真寺の西にあり、松山城の近く。「横田陣屋の御殿桜」の案内板が建っている。
桙衝館
桙衝(ほこつき)館は、東の江花川を外堀として、北には水堀と土塁の遺構が残る。南朝方の支配下であったが、1347年に北朝方の伊賀盛光が入城した。南北朝時代後の動向は不明だが、戦国期、二階堂家臣の塚原伊予が城代を務めていたと伝わっている。桙衝館の北側土塁の下にある五輪塔は、塚原伊予のものらしい。
矢田野城
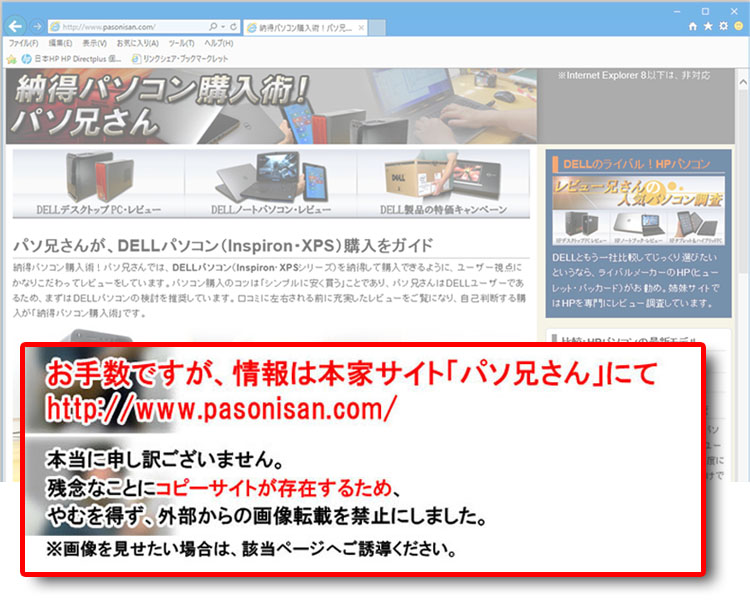 須賀川市矢田野藤原にあった矢田野城は、二階堂行泰の弟・行綱を祖とする矢田野氏の居城とされる。畑に囲まれた矢田野行政地区のほぼ全域が城の推定範囲で、規模は東西280m、南北200m。主郭は郵便局および集会所付近とされ、主郭を取り囲む土塁や堀跡がある。
須賀川市矢田野藤原にあった矢田野城は、二階堂行泰の弟・行綱を祖とする矢田野氏の居城とされる。畑に囲まれた矢田野行政地区のほぼ全域が城の推定範囲で、規模は東西280m、南北200m。主郭は郵便局および集会所付近とされ、主郭を取り囲む土塁や堀跡がある。
大久保館
須賀川市宮田字宮田の瑞巌寺付近にあった大久保館は、1570年代に大久保資近(二階堂照行の4男)によって築城された。北に位置する稲川が天然の堀になっている。1589年に伊達政宗が須賀川城を落とすと、大久保氏は主君二階堂氏とともに滅亡した。瑞巌寺に大久保資近の墓がある。1682年には、播磨国から本多政利が入封して1万石の岩瀬大久保藩が立藩される。政利は江戸に居るため、その家臣を陣屋に置き政務にあたっていた
大里城
高さ350mの山頂にあり、比高は50m。三方が急斜面で西には空堀を設けてある。山頂の本丸は25m × 20m、東南に二の丸がある。大里城の南方には、「羽黒山」と「開場山」があるが、二階堂氏家臣の矢田野氏が大里城で籠城した際、伊達軍の来攻に備えて攻撃拠点に使われたという。
1589年に伊達政宗が二階堂を滅ぼすと、二階堂家臣の矢田野義正は伊達軍として取り込まれる。1590年、政宗に従って小田原に参陣するが、逃亡して大里城に籠城し、政宗に反旗を翻した。政宗は、新たに須賀川城主となった石川昭光や片倉小十郎に命じて大里城を包囲させた。矢田野は鉄砲のほかに、石や木を投げて反撃。入城できない伊達軍は水の手を攻めるが落城せず。最終的に浅野長政の意見(秀吉による仲裁)を聞き入れ、政宗は大里城の包囲を解いて終結した。
浜尾館
浜尾氏の館跡か。
木之崎館
二階堂氏を祖とする木ノ崎右近大輔の居館と伝わる。矢田野城、桙衝館、横田館、今泉城などと同じく会津蘆名氏の侵略に備えていた。現在でも5mほどの土塁や堀跡が残る。
乙字ヶ滝と上代館
調査
木舟城(狸森城)
南北に長い丘陵地に置かれている。主郭は南北に並ぶ3つの郭で、堀切によって区画されている。その南端の郭が本丸のようだ。城主は二階堂氏家臣・矢部氏で、1444年に矢部定清が二階堂為氏の家臣になり、須賀川へ入ったとされる。ただ、矢部氏はもともと狸森地方で勢力を持っていた氏族だとされる。木舟城に入城したのは、4代目である矢部清通。
1589年に、伊達政宗が二階堂氏を滅ぼすと、木舟城は廃城となった。
矢柄城
矢柄(やい)城は宇津峰城の西2kmの位置にある。宇津峰登山口の木曽集落の南側にある丘が城跡。宇津峰城の外郭防衛用の支城のひとつである。1352年、北畠顕信は宇津峰に籠城したが、吉良貞家が率いる北朝軍の総攻撃により、矢柄城が落城、続いて宇津峰城も落城した。これにより南奥州の南北朝の騒乱は終結した。
細桙城
細桙(ほそほこ)城は、二階堂氏家臣・塩田氏の居城とされる。主郭は東西100m、南北40mの規模。細桙城の南にある「新館山」という砦は新造された出城と考えられる。1589年、伊達政宗が二階堂氏を滅ぼすと、細桙城も多くの城館とともに廃城となった。細桙城主・塩田重政の嫡男であった「塩田政繁」は、須賀川城の攻防図によると八幡山の大黒石口側に布陣している(塩田右近大夫の名がある)。須賀川城の落城により自害したとされるが、一説には石川郡に落ち延びたところを捕らえられて処刑されたとも言う。
刑部内館・松が館
刑部内館は、宇津峰城の南西麓に位置する丘陵地にある。比高45mほどの輪郭式山城。館主は二階堂氏家臣、遠藤藤蔵之介とされる。遠藤氏は蛇頭館に在城していたが、戦国期に田村氏が脅威となり、刑部内館を築城して移ったと考えられる。北東では堀切で切られた松が館があり、そこは二階堂氏家臣・佐久間主殿助が館主を務めていたという。刑部内館と松が館を合わせて一つの城として機能したと考えられる。松が館は刑部内館の増設部分とみてよさそうだ。
なお、鎌倉時代に、田村一族の刑部仲能は鎌倉幕府の評定衆であり勢力があった。その刑部と関係があるのだろうか・・?
成山館
郡山市成山町(成山公園)にあった城館。応永年間(1394年~1428年)に、伊東満祐の居城だったと伝わっているが、築城年代も含め不明とのこと。篠川御所が近いので、何らかの関係性はありそうだ。
★Alienwareノートの一部モデルに、24%オフ クーポン。★そのほか、17%~23%オフ クーポンの対象モデル多数あり!★8年連続世界シェア1位!DELLモニタがオンライン・クーポンで最大20%オフ!
クーポンコード掲載はこちら ⇒ 【DELL公式】 お買い得情報ページ
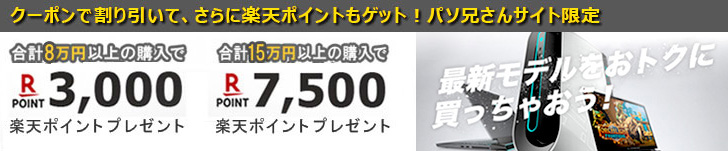
★DELL直販合計8万円(税抜)以上購入で、楽天ポイント3,000ポイントプレゼント!★合計15万円(税抜)以上購入なら、楽天ポイント7,500ポイントプレゼント!
※パソ兄さんサイトの経由特典となっており、リンク先の優待専用ページでの手続きが必要になります。(それ以外の注文では対象外) ※予告なく変更または終了する場合があります。
8万円以上購入なら ⇒ 【 3,000ポイント付与の優待専用ページへ招待 】
15万円以上購入なら ⇒ 【 7,500ポイント付与の優待専用ページへ招待 】
※DELLは、「顧客満足度調査 2019-2021年 デスクトップPC部門3年連続1位」 ※出典-日経コンピュータ 2020年9月3日号より
DELL法人モデル(Vostro、Precision、OptiPlex、Latitudeシリーズ)の購入を希望なら、当サイトの「特別なお客様限定クーポン情報」を御覧ください。掲載コンテンツ・ページはこちら!
コンテンツ ⇒DELLパソコンをもっとお得に購入!クーポン情報

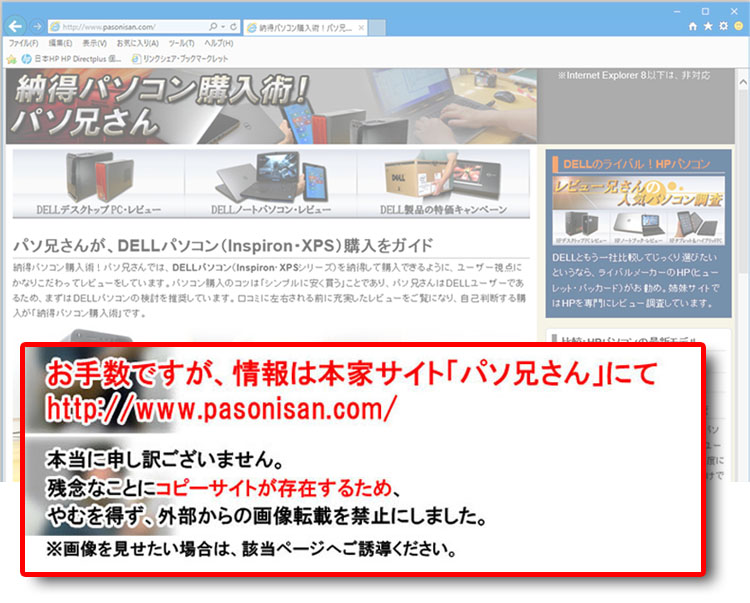 金剛院境内の様子。
金剛院境内の様子。