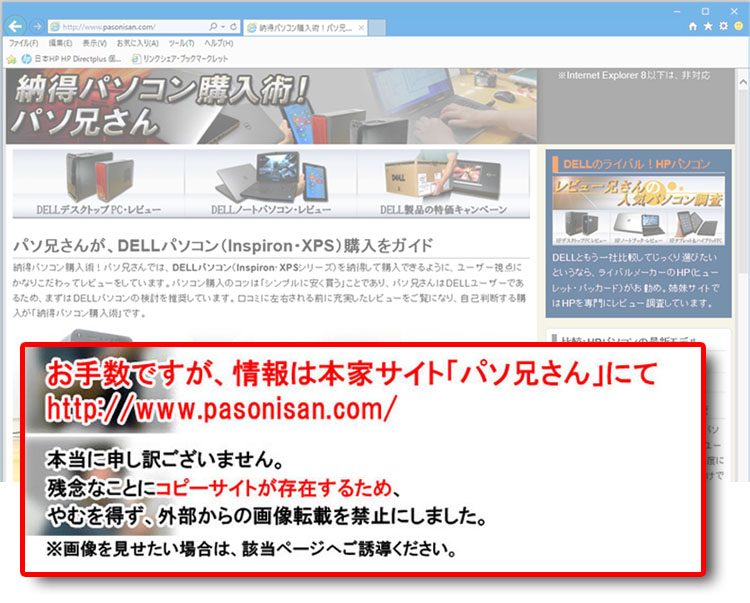

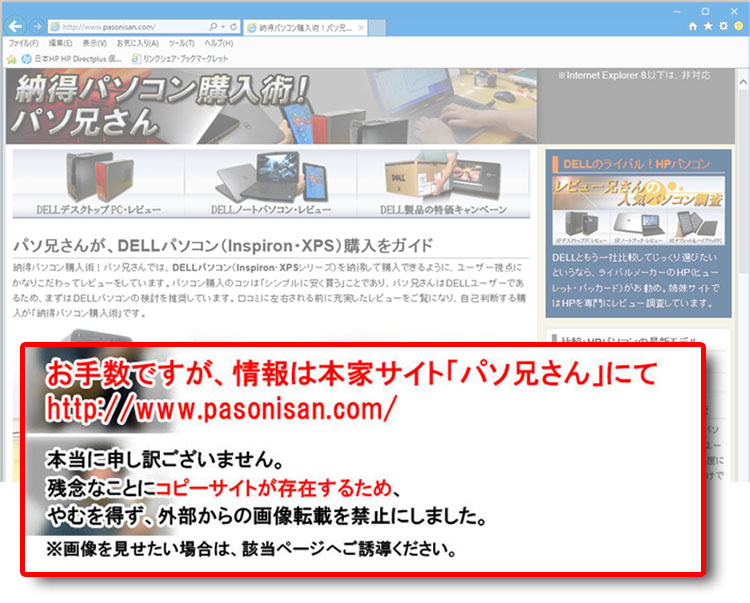
- パソ兄さん HOME
- DELLパソコン・モバイル旅行記TOP
- 東京都
- 深大寺城/東京都調布市
小田原北条氏にスルーされちゃった城
扇谷上杉氏の深大寺城
東京都調布市深大寺元町にあった深大寺城(じんだいじじょう)を登城した(2014年4月、ならびに2022年11月再登城)。武蔵野台地南部に位置し、多摩川によって形成された河岸段丘(武蔵野段丘)の崖上に築城されている。湧水が豊富なため崖端が浸蝕された谷であり段丘崖の地勢が城に利用されている。太田道灌の主君で知られる 扇谷上杉氏 が主に改修した中世の城として知られる。
1524年、上杉朝興は江戸城を北条氏綱に攻略される。朝興は江戸城を奪還すべく河越城から出陣するも度々敗退している。1530年、北条氏康は深大寺に近い多摩川対岸の小沢城に陣を敷き、小沢原で合戦が行われたが、上杉氏は敗退している。
南武蔵での北条氏との戦いにおいて、上杉氏は深大寺城が築城される前、そこにあった創築年代不明のふるき郭(古城)という城を利用していた。つまり深大寺城の基礎となる砦はすでにあった。1537年、上杉朝興の跡を継いだ上杉朝定は難波田広宗に深大寺城の普請(ふるき郭の再興)を命じた。そして深大寺城を江戸城奪還の拠点とした。対する北条氏は、江戸城の守りに牟礼(三鷹市)と烏山(世田谷区)に砦を築いている。
1537年、北条氏綱は深大寺城をスルーして、扇谷上杉氏の居城である河越城を攻略した。扇谷上杉氏は江戸城の奪還どころか河越城まで奪われることになる。そのため敗走する形で、上杉朝定は居城を武蔵松山城へ代えた。その後、北条氏による深大寺城の改修が見られないことから同年に廃城されたと考えられる。河越城を攻略した北条氏にとって、深大寺城に軍事的な価値はもはや無かったのだろう。
 深大寺城は1998年の東京都指定史跡を経て、2007年に国史跡に指定された。北条氏の眼中になく改修されなかったことにより、今もなお扇谷上杉氏の築城技術を伝える貴重な史跡となっている。
深大寺城は1998年の東京都指定史跡を経て、2007年に国史跡に指定された。北条氏の眼中になく改修されなかったことにより、今もなお扇谷上杉氏の築城技術を伝える貴重な史跡となっている。
その後の扇谷上杉氏は、河越夜戦で滅亡....
1546年、上杉朝定は北条氏から河越城を奪還すべく行動に出る。山内上杉氏(上杉憲政)、古河公方(足利晴氏)と連合して8万の軍勢で河越城を包囲する。河越城(城代)の北条綱成は3千で立て籠もり苦戦。北条氏康が8千騎率いて援軍に向かい、夜戦で奇襲をかける。これに呼応して城兵も城門を開き打って出たので、東明寺を中心に激しい市街戦となった。結果、軍勢の多さから油断していた上杉・足利連合軍は敗走。上杉朝定は討ち死にし、扇谷上杉氏は滅亡する。
※遡ること1486年、主君(上杉定正)に暗殺された太田道灌は「当方滅亡」と予言している。上杉朝定を最後に扇谷上杉氏は事実上の滅亡となった。
深大寺城の縄張り図

一郭(本丸)・二郭・三郭の連郭式城郭。空濠に敵兵を誘導して矢で殲滅する、扇谷上杉氏の城のスタイルを取っている。これは築城技術の発展途上であり横矢や切岸に弱点がみられる。たびたび扇谷上杉氏と戦った北条氏は築城の研究材料としていたことだろう。
現在では主に一郭、二郭が公園化されている。二郭・三郭間の空堀付近はテニスコートになっており、さらに東西に広がる三郭は住宅地開発で破壊されている。

深大寺城は比高14mの多摩川河岸段丘の地形を活用している。
水生植物園に残る、深大寺城跡
調布市の北西部に位置する水生植物園は、神代植物公園分園である。南北300m,東西60m,面積1.33ヘクタールの谷戸地に位置する。かつては水田であったが、環境保全の目的で昭和60年に水生植物園として開園した。この水生植物園が深大寺城跡である。多くの観光客は、深大寺城跡まで足を伸ばすことはなさそうだ。

深大寺城の北のバス通り(深大寺通り)は湿地帯の堀だったと観るべきだろう。

水生植物園ならびに深大寺城址は柵で囲まれているため、時間に注意しないと散策できない。入園は16:00までと書かれている。

入り口に置かれている水生植物園のマップ。東に位置する湿地帯はかつての堀跡である。

東の堀跡。国分寺崖線上の深大寺から湧き出す湧水によって沼地(水生植物園)となっている。深大寺城の防衛に利用されたことは言うまでもない。この位置から右側の丘陵地が深大寺城である。深大寺城の南側は野川が水堀の役割を果たしている。

水生植物園から本丸に向かう階段。少し上がると腰曲輪がある。腰曲輪とは斜面の中腹に築かれる曲輪で、斜面が緩やかな場合に防御機能を補う。

当時のまま思われる腰曲輪の石垣を発見したが、当時のものかは不明。バス通りにある整備された石垣とは違って趣が感じられる。水生植物園を見下ろすと、中世の城にきた実感が味わえる。上杉朝定が改修する以前、創築年代不明のふるき郭(古城)という城の基礎があったようだ。
一郭(主郭)

高台を登り第一郭(主郭)に到着。主郭は東西50m・南北90mほどの規模。案内板には、「深大寺城は半島状台地の先端に位置し、当時は南方が一望できた」と書かれている。
 標柱の後方は重要な役割である櫓台として小高い土塁が残る。
標柱の後方は重要な役割である櫓台として小高い土塁が残る。
 本丸と二の丸の間にある虎口。
本丸と二の丸の間にある虎口。
深大寺城の二郭~掘立柱建物があった

主郭から二郭につながる土橋と、その二郭の空堀跡と土塁。当時はもっと深い堀であったはず。深大寺城は郭を土塁で取り囲んでいるところが特徴的。

建物跡が発見された二の郭。二の郭では建物跡の位置表示のため石柱が置かれている。発見された掘立柱建物のうち2棟の柱穴の位置である。

「建物は武士の屋舎であろうと考えられる。一般的に戦国時代の城の建物は丸柱・板葺き屋根で、床は中心的な屋形のみにあった」と彫られている。

二郭側の土塁は一部復元されたものらしい。深大寺城の西側では空堀で防衛している。

西側へと続く縄張りでは、二の丸の空堀、そして三の丸はテニスコートならびに宅地化によって破壊されている。

二郭の隅では深大寺小学校5年生が種まきをするそば畑があり、おそらく課外授業用と思われる。収穫した蕎麦は地元の蕎麦屋が手打ちそばにして、深大寺小学校の生徒に振舞っているらしい。観光客が食べる蕎麦は現地のものではない。深大寺そばが名物と言いながら、現在は現地でまったく栽培していないのは「なんだかなあ」と感じる。真の「深大寺そば」が食べられるのは、深大寺小学校の生徒だけということか。
ふるき郭(古城)との関連?狛江入道館跡
先述の通り、深大寺城は創築年代不明のふるき郭(古城)を再興したものであるが、古城についてはよくわかっていない。しかし、これに関連する遺構が狛江入道館跡(現在の晃華学園)である。深大寺城から東に1kmほどの場所にあり、同じ武蔵野段丘の崖上にある。伝承では狛江入道 増西(道西)の館というが証拠はない。江戸後期の「新編風土記稿」によれば、狛江入道館跡であろう古舘の遺構があったと記している。狛江入道館跡については吾妻鏡(1208年)にみられ、鎌倉時代初期にはあったとうかがえる。かつて武蔵七党の西党であった狛江氏の領地であったのだろう。

南側にある「里の稲荷」は佐須村の里正三郎左衛門の先祖が建立したものと伝わる。この稲荷神社の北側の丘は「古屋敷の跡」と言われて、東西15m、南北50mほどの規模でその4辺が空堀によって断ち切られていたという。学園内では土塁や空堀が割合残っているらしいが、戦国末期に領主が築いたものと考えられている。
 「里の稲荷」に面した坂道は切り通しとなっている。
「里の稲荷」に面した坂道は切り通しとなっている。
せっかくなので、さくっと深大寺の観光
 道中にさくっと深大寺観光に興じた。天台宗の浮岳山深大寺は、733年に満功上人が開基したとされ、白鳳仏を安置している。深大寺だるま市で知られ、日本三大だるま市の1つである。
道中にさくっと深大寺観光に興じた。天台宗の浮岳山深大寺は、733年に満功上人が開基したとされ、白鳳仏を安置している。深大寺だるま市で知られ、日本三大だるま市の1つである。

深沙大王堂(じんじゃだいおうどう)では、秘仏の深沙大王像が安置されている。むろん深大寺の寺号はこの深沙大王に由来する。
 延命観音。昭和41年の秋田県象潟港工事の際、海底より偶然、延命観音が彫刻された大石が引き上げられ、深大寺に奉安された。
延命観音。昭和41年の秋田県象潟港工事の際、海底より偶然、延命観音が彫刻された大石が引き上げられ、深大寺に奉安された。

薬医門という形式の深大寺山門は境内で最も古い建物で、数少ない茅葺き。元禄八年(1695年)に普請されたと伝わる。石段は平成20年改修工事が行われ、緩やかな傾斜となった。
 境内にはいくつかの湧水源があり、不動の滝は「東京の名湧水57選」に選定されている。蕎麦の栽培や調理、水車に利用される湧水によって、名物の「深大寺そば」が発展したと言われる。ただし、現在では現地での蕎麦栽培は無く、青森県産などが使われているようだ。
境内にはいくつかの湧水源があり、不動の滝は「東京の名湧水57選」に選定されている。蕎麦の栽培や調理、水車に利用される湧水によって、名物の「深大寺そば」が発展したと言われる。ただし、現在では現地での蕎麦栽培は無く、青森県産などが使われているようだ。

深大寺 本堂。幕末の火災で焼失したが、大正八年に現在の本堂が完成した。旧本堂は茅葺屋根であったが、桟木に引っ掛けて固定する瓦を使った棧瓦葺き(さんがわらぶき)に変更されている。現代の瓦屋根の一般的な葺き方である。


